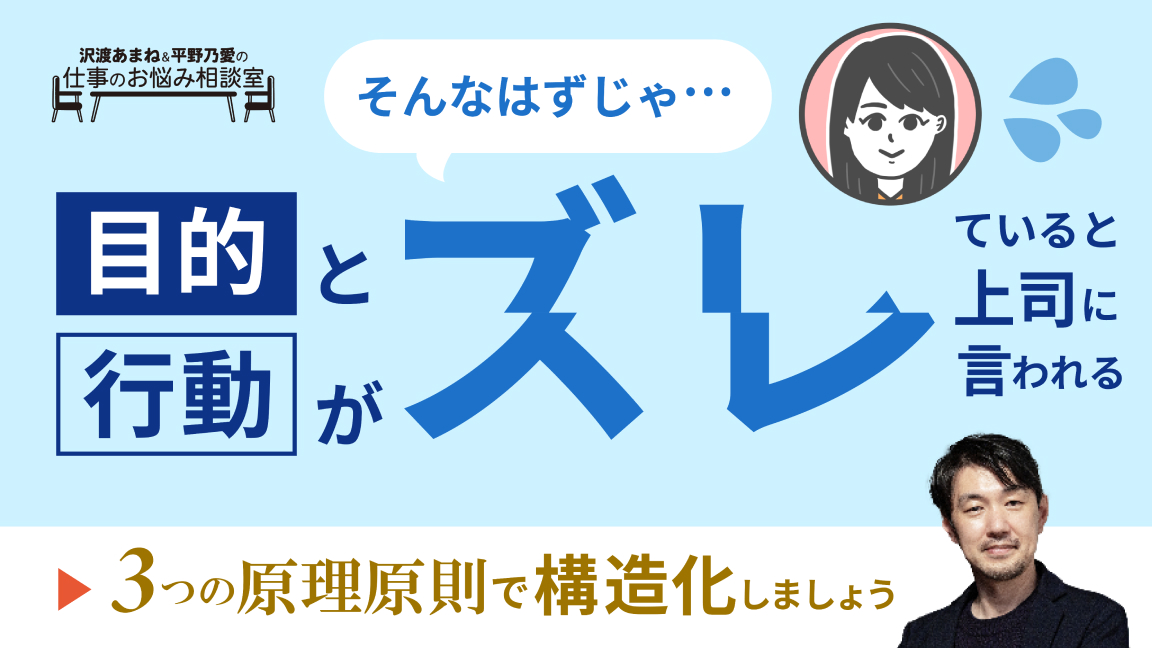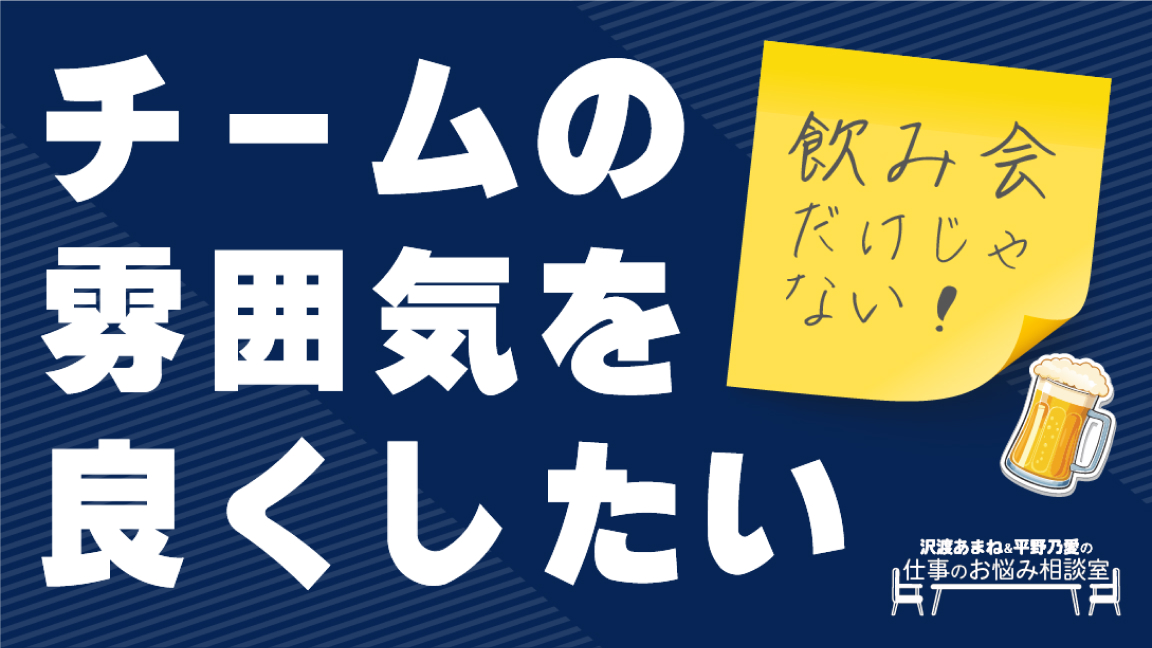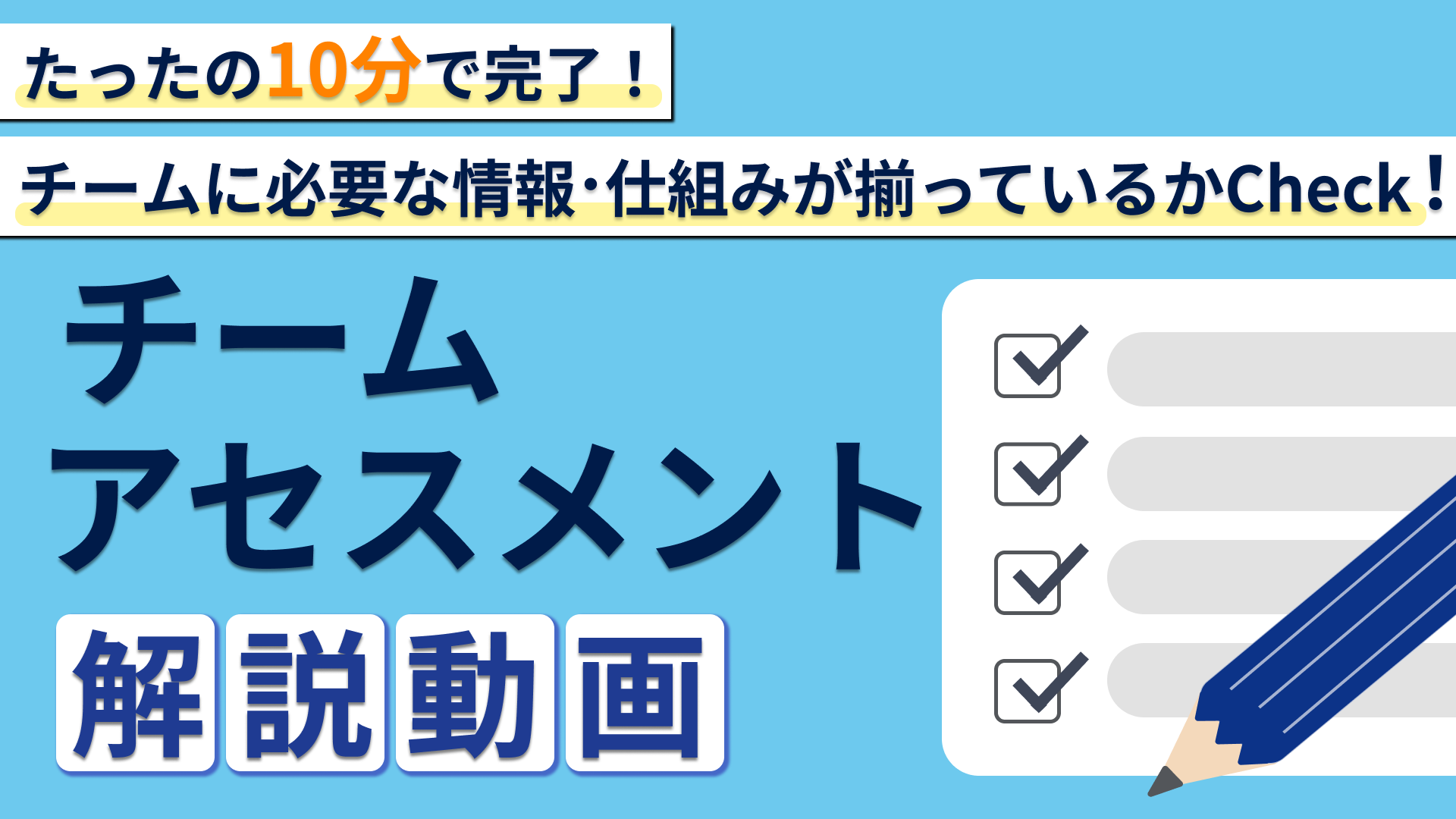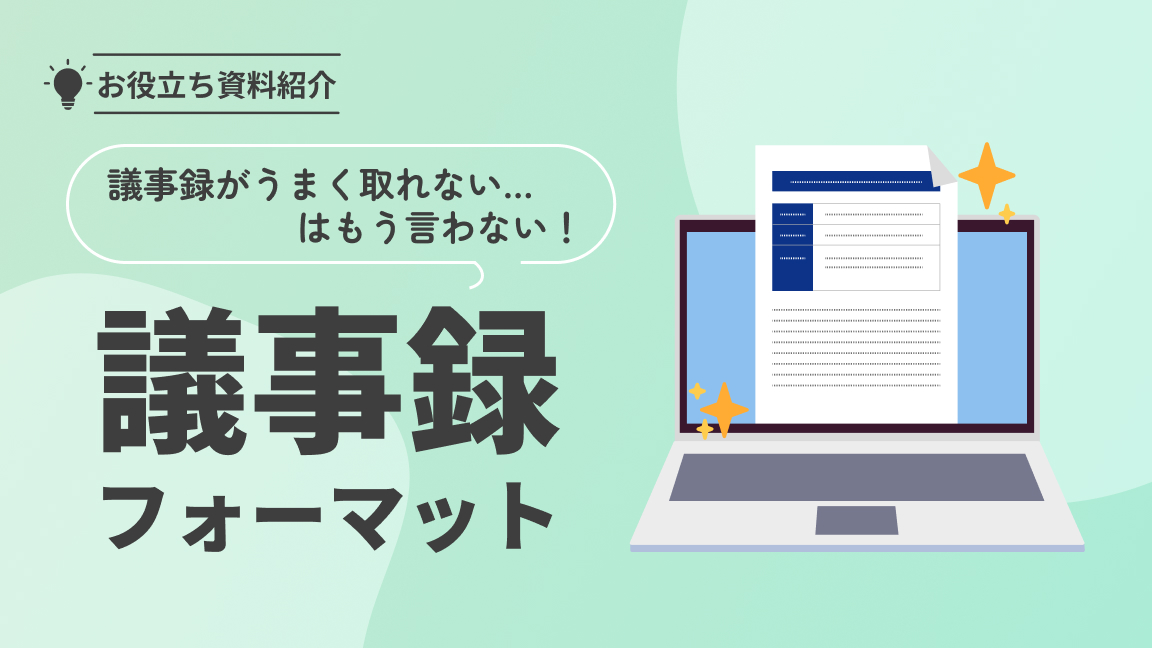業務一覧作成のポイントは、プロジェクト開始時にまず作成すること,軸の取り方に迷ったら、 まず思い出せる限り書き出すこと,社内関係者のレビューでブラッシュアップすることです。 以下進め方を参照ください。 ①類似業務の情報や経験者からヒアリングを行い、必要な作業をすべてリストアップする ②作業の性質や関連性を考慮してグループ化する例)定常/非定常、設計/構築、担当別 など ③業務を作業単位に詳細化する ④納期や頻度を記載する ⑤想定工数を算出する ⑥品質基準を満たす為に、抜け漏れや無理が無いかを確認する。
[参考資料] リスク管理表
おすすめ記事
ファシリテーションを上達させるコツ
みなさんは、「会議のファシリテーションがなかなかうまくできない」といった経験はありませんか? 元々当社入社前の前職ではたらいていた時、ファシリテーションに強い苦手意識を持っていた ”てぃーさん” は、 当社に入社してから、様々な取り組みを行う中で ファシリテーションの上達へ自信をつけることができました。 このコンテンツでは、そんなてぃーさんに、 「ファシリテーションを上達させる方法」について聞いてみました。 〈目次〉 登場人物紹介 ファシリテーションが苦手だった私の意識変化 取り組みの概要 振り返りと分析 情報収集と検討 実践 まとめ 関連資料 1. 登場人物紹介 話すことと食べることが好きな人。 MBTIは、INTJ(建築家)か ISTP(巨匠) 社会人歴 8年 経歴 1社目:個別指導塾の教室運営 一人で働くことがメインだったので ファシリテーション経験ゼロ 2社目:建築系コンサルティング企業で本社勤務 初めてチームで働き、 ファシリテーションに苦手意識を持つ 3社目:当社 このコンテンツでは、私がファシリテーション克服のために、どんな取り組みをしたのかご紹介します。 2. ファシリテーションが苦手だった私の意識変化 今までは、ファシリテーションは向いていない・・・と諦めていたけれど、 練習や準備をすれば、上達ができること、 さらに、うまく進行できると、チームとしても仕事が進めやすくなることを実感できるようになりました! それでは、どんな練習・準備を繰り返してきたのか、お伝えします! 3. 取り組みの概要 ここからは、私が行った取り組みのステップをお伝えします。 「振り返りと分析」 自分がなぜファシリテーションを苦手と感じているのか原因を考えました 「情報収集と検討」 ファシリテーションのコツを収集しました 「実践」 学んだコツを、段階的に実践していきました その結果、苦手意識を克服することができました。 4. 振り返りと分析 なぜ苦手意識を持ち始めたのか、まずは前職での失敗談から振り返りを行いました。 前職での失敗談 私と同僚は上司からとある指示を受けた際に、上司からの指示内容について、 同僚とのミーティングを設定し話し合うことになりましたが、 その時、決めなければいけない事柄について、同僚からの意見がなかなか出ず、 ”私ばかり 意見を出し、自分だけで話しを進めてしまう・・・” という状態になってしまいました。 結局ミーティング内で決めるべき内容がしっかり話し合いできないまま終了し、 その後ミーティングの中で決まった内容を、上司に提案しましたが、 上司から「考えが浅い」と指摘を受けてしまい、やり直しになってしまいました・・・。 この時の経験から、 「なぜ上手くミーティングを回せなかったのか」 その要因を考えるために、 マインド・ミーティング前・ミーティング中の三つに分けて振り返ってみました。 振り返ってみると以下のことに気づきました。 マインド(自身の気持ちの持ち方)は、 参加者から発言があるのが当たり前だと思っていた ミーティング前は、 事前準備が足りなかった ミーティング中は、 進め方のコントロールができていなかったこと これらのことを克服するための情報収集と、どのようにすれば良いのかを検討しました。 5. 情報収集と検討 ここからは、どんな情報収集を行い、ファシリテーションの苦手克服のための検討を行ったかをお伝えしていきます。 マインド 編 ファシリテーションが得意な人がどのように実践しているか聞いてみたり、 インターネットでファシリテーションについて調べたりしたところ、 私はファシリテーションの役割について、 サポート役に回ること 意見を述べてくれた方に対して感謝を伝えること これらが有意義な意見交換のために必須であることを学びました。 ミーティング前 編 ミーティング前は、ゴール設定と、事前準備が大切なことを学びました。 ゴール設定ミーティングを何のために開催するのかその日のミーティングで決めなければいけないことはなにかを、明らかにすることが大切です。ここで決めたゴールは、ミーティングの冒頭で必ず確認するようにしました。 事前準備その日のミーティングで決めなければいけないことに対して、どのようなアジェンダが必要かを決めて書き出します。 そして各アジェンダに対しての時間を決めます。ここで、無理のない、現実的な時間設定にすることが大切です。 ミーティング中 編 ミーティング中は、時間管理と質問の仕方と話の粒度を意識することが大切なことだと学びました。 時間管理を行う ミーティング前に決めた時間どおりに進んでいるかを確認します。 質問方法の工夫する 参加者からの意見が出ないからと言って、意見がないとは限りません。 どの点に対して意見を言えば良いのか困っている可能性もあります。 そんなときは参加者に「あなたはどう思いますか?」と聞くのではなく、 「この点についてはどう思いますか?」と、聞きたい範囲を限定して質問することで、 相手も考えやすくなるため、意見を言いやすくなります。 話の粒度を意識する ミーティングで議論が盛り上がった時、気づいたら話が逸れていて、 その日決めるべきことよりも、細かい内容ばかりを話してしまう・・・といったことはありませんか? そうならないために、実施前に決めたゴールを達成するために必要な議論となっているか、 話の粒度は適切かどうかを考えるようにしましょう。 もし話が逸れてしまっていたら、理由を説明した上で、適切な粒度に修正することが大切です。 たくさんの情報を見聞きしましたが、自分の課題に対応する対策を選び、取り組みました。 6. 実践 どれだけ何を対策するか考えていたとしても、一度にすべてを挑戦していくのは簡単ではありませんよね? そのため、私は実践の場を三段階に分けて設定し、実践していきました。 社内の定例ミーティングで時間管理のみを行う 社内の上司に報告する際などのミーティングでゴール設定・質問の工夫を行う参加者とゴールをすり合わせすることや、 前述の「ミーティング中」で記載したとおり、参加者に対しての質問の仕方を変えること、そして議論の粒度を意識した進行を実践しました。 社外のミーティングで全体的なファシリテーションを行う最後に1,2を踏まえて、社外の方々と緊張する場面であってもファシリテーションが行えるようになりました。 各段階で実践と振り返りを行い、次回に向けて気を付けることを決めることで、 自分の中の目標を明確にし、ステップアップをしていくことができました。 7. まとめ このように振り返りと分析を行い、それに対する対策を知り実践したことで 上手にミーティングを回せるようになり、成長実感を得ることができました。 最後に、このコンテンツで伝えたいことは、 私は今まで、ミーティングの参加者は「自発的に意見を言ってくれる」 「ミーティングのゴールを理解してくれている」と思い込んでいましたが、 ミーティング参加者の意見は、”ファシリテーターである自分が引き出すもの” だと考えが変わりました。 また、苦手なものをそのままにせずに挑戦してみたことで、成功体験を積むことができました。 この経験が少しでもみなさまの参考になれば嬉しいです。 8. 関連資料 ▶▶【🎥動画】ファシリテーション~苦手克服までの体験記 はこちら ▶▶【🎥動画】らくらく議事録フォーマット はこちら ▶▶【📝記事】議事録作成のコツ はこちら
育成計画について
メンバーの育成を計画的に行うために、チームの能力開発計画を作成しましょう。 具体的には、そのチームに求められるスキルと現有状況を可視化した「スキルマップ」を作り、 チームやメンバーに不足しているスキルや経験をどう補っていくかスケジュールを組み立てていくとよいでしょう。 重要なポイントは、「目的」「達成範囲」「達成基準」「達成手段」「達成スケジュール・期限」です。 最終的に計画完了後にチームがどういう状態になっていることを目指すのか、 メンバーにどの範囲までを任せたいのか、上長やチーム内で事前に認識を合わせた上で育成計画に反映してください。 以下は、スキルマップの参考事例です。スキルマップは年1回程度アップデートすることをお勧めします。
目標を達成するためにコントロールするべきQCDSとは?
〈目次〉 QCDSとは QCDSの設定 QCDSの調整 関連資料 1. QCDSとは QCDSとは、目標を実現する上での前提条件のような性質を持つものであり、 目標を達成するためにチームでコントロールすべき重要な指標です。 ここでは、QCDSの整理の順番、優先順位のつけ方などQCDSの基礎を説明します。QCDSは、目標を達成する為にチームでコントロールすべき主要指標の頭文字を取った略語です。 関係者との共通認識は取るためには、QCDSの観点を踏まえ、高い解像度の目標地点を定めて具体的な計画を作成していきましょう。 ┃ Q Quality 品質基準 Qはクオリティー、品質の基準のことです。 品質基準の設定には二つパターンがあります。 パターン① 目標とは別の品質的な付帯要件がある場合は、それを設定するパターンです。 例: 業務の処理件数が月に1000件目標で、品質基準が処理の不備率は5%以下に抑えることという場合、 「不備率5% 未満」というのが、仕事の質に対する付帯要件です。 不備率が多いことは仕事の質が低いことになるので、あらかじめ要件として設定されていることがあります。 Point 質に対する期待は、顧客の頭の中には当然のこととして存在し、あえて言葉で伝えられない場合もあります。 そのため「何かしらの条件はありますか?」とこちらから 確認するようにしましょう。 パターン② 目標や、KPIをそのままQ(クオリティー)として設定するパターンです。 特に、質に対しての追加要件が無い場合は、目標やKPIをそのまま「Q」として設定しても構いません。 ┃ C Cost 予算/コスト Cはコスト、予算のことです。 予算は絶対に変えられない場合もあれば、状況によって変更が認められる場合もあります。 チームの取り巻く環境において、どの程度変更の余地があるのかを確認しておきましょう。 Point また自チームが活動する工数も、人件費というコストであり、管理されなければいけないものです。 納期が遅れる場合は、その分の人件費がかかることが多いです。 自チームが主導となって、コストをコントロールできるかどうかは別としても、工数はコストである、という認識をもつことが大切です。 ┃ D Delivery 期日/納期 Dはデリバリー、期日、納期のことです。 納期は以下二つのパターンがあります。 パターン① サイトリニューアルのような、いつまでに完了するか全体のスケジュール期日 パターン② 「PC交換対応」のような、何年かに一回定期的に繰り返し対応が必要な時の 1回1回の完了締め切り ┃ S Scope 業務範囲 Sはスコープ、業務範囲のことです。 業務の対象範囲については、コストや納期に比べて曖昧になることが多いですが、曖昧であるがゆえに、 あとから想定外に工数が増えるといったこともあるので、しっかり確認する必要があります。 例① サイトリニューアルの場合は、追加機能の範囲などがスコープにあたります。 例② 「PCの交換対応」のような業務の場合は、「交換対象は3年以上利用が条件」といった、条件がスコープにあたります。 Point 特に例②のような、長年継続している業務の場合は、少しずつ範囲が広がっていき、 知らないうちに工数が膨れ上がっているということもあります。 その場合は、業務はどこまでを対象とするか、改めて明確にすることが大切です。 チームの業務範囲(やるべきこと)を洗い出すためには「業務一覧」や「WBS」を活用しましょう。 2. QCDSの設定 全てのQCDS条件が関係者側であらかじめ決まっている場合は、その条件を漏れなく確認するようにしましょう。 しかし多くのケースでは、一部の条件しか決まっていません。 「例えば納期、予算は明確だが、品質、範囲は不明」といった一部条件は決まっているが、その他の条件は流動的で決まっていないことも多くあります。 その場合は、自分たちで変更可能な条件下で実現可能なプランを検討し、提案をしていきましょう。 もしすべての条件を自チーム主導で決めていけるのであれば、以下の順番でQCDSを設定します。 実施順 項目 内容 1 Quality 目標を仮決めする 2 Scope やるべきことに対する想定作業量を見積もる 3 Delivery 想定スケジュールに落とし込む 4 Cost 概算工数、想定人員数、ファシリティ費用などを見積もる 5 Quality 目標、KPIを満たすために十分であるかを確認する 3.QCDSの調整 Q、C、D、Sは、互いにトレードオフの関係にあります。 ・品質を高めようと思えば、コストが上がる ・コストを下げるためには、品質を低くするか、範囲を狭める ・今のままだと品質目標基準に到達できないが、納期を遅らせることで到達可能となる などです。 全ての要件が達成できればそれに越したことはありませんが、現実的には想定通りに物事が進まず、 QCDSいずれかの条件が満たせなくなる場合も多くあります。 そのような場合に備え、何が優先されるかをあらかじめ確認していくことが重要になります。 優先順位は、組織や状況によって異なります。 予算は絶対に変更できない、という場合もあれば、株式上場や企業合併など、 対外的にも重要なイベントに関係する場合は納期が絶対となります。 この優先順位はその時の責任者の意向によって異なることもありますので、顧客のニーズや意向を踏まえて必ず事前に確認しておきましょう。 トレードオフスライダー 関係者間で、何を優先させるのかを定めておきます。 チームで業務を遂行する際の重要項目に優先順位をつけ、何を守り、何を捨てるかを、見える化したものです。 あらかじめ、どれを最優先とするのか、すり合わせをしておきましょう 4. 関連資料 ▶▶【🎥動画】目標設定を「苦手なもの」から「働きやすくする手段」に変える方法はこちら ▶▶【📝記事】目標設定を設定するコツ はこちら ▶▶【📝記事】計画の見直しをするには? はこちら
体制に必要な人数算出方法
業務一覧やWBSを基に必要工数を把握していきます。 基本的な算出方法例は以下となります。 例、定期的に繰り返される業務の人員数の算出 ※累積したデータに基づき繁閑を加味して算出する。 実工数・・400h/月(定常業務:300h/月 + 非定常業務:100/h) →1名あたり労働時間を160h/月とした場合 2.5人月の工数が必要 →必要人員数は3名と算出する また、改善を行っていくためには改善のための時間を予め確保しておく必要があります。 そこで重要となる考え方が稼働率です。 稼働率は、定常業務(サービスの提供のために常に発生する業務)+非定常業務(サービスの提供のために必要だが不定期で発生する業務)を月の総労働時間で割ったものです。 ※1(定常業務+非定常業務)÷月の総労働時間 例えば1人の月の総労働時間(※1)を160時間とし、 その人が行う定常業務が100時間、非定常業務が36時間だった場合は稼働率は85%という風に計算します。 残りの15%、24時間が改善や自己研鑽に使える時間、ということになります。 この稼働率が、改善し続ける組織体制を創るうえで最も重要です。 ではどの程度が理想か?それは、先の例にも挙げた85%です。 まず、稼働率とはチームがどの程度余裕があるのか?ということを図る指標ですから、 当然100に近づいていけばいくほどに余裕がない、忙しい状態となります。 それだと当然チームは疲弊していきます。 これまでチームのコンディションが悪化してきたチームの多くは稼働率が98%を超えていました。 こうなってくるともはや改善をする等という余裕はなくなり、衰退していく一方になります。 常に15%程度の余力を持っておくことが、業務を改善し組織が成長する上で重要です。 では余裕がたくさんあればいいのか?というと決してそんなことはありません。 稼働率が70%を切っているようなチームは「人」が成長しません。 そのチームでは良くても、他に行くと通用しないことが多いのです。 何故か?簡単に言えば稼働率が70%を切るような状態はヒマだと言えます。 そのため、頑張って改善する必要すらないのです。 こうなると組織も人も成長しなくなります。 ですので、15%の余力を持ち改善を進める、改善が進み更に余力が生まれたところで新たなチャレンジをしていく、 このサイクルを常に継続することがサービスの付加価値を上げる上でも、組織と人の成長の上でも重要です。