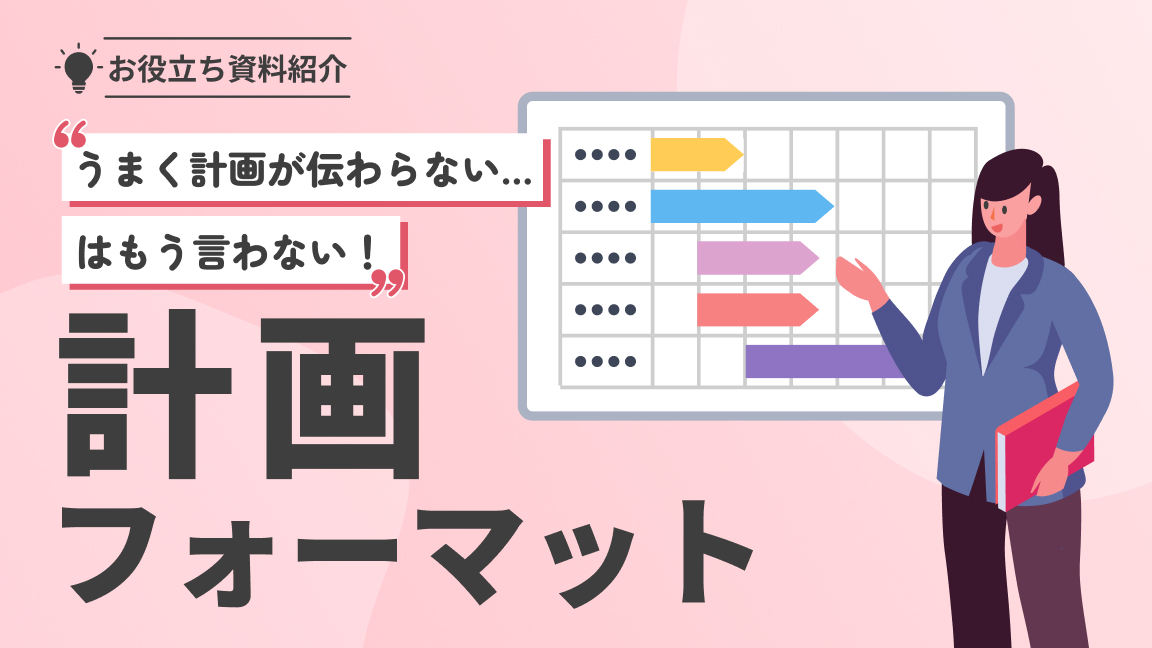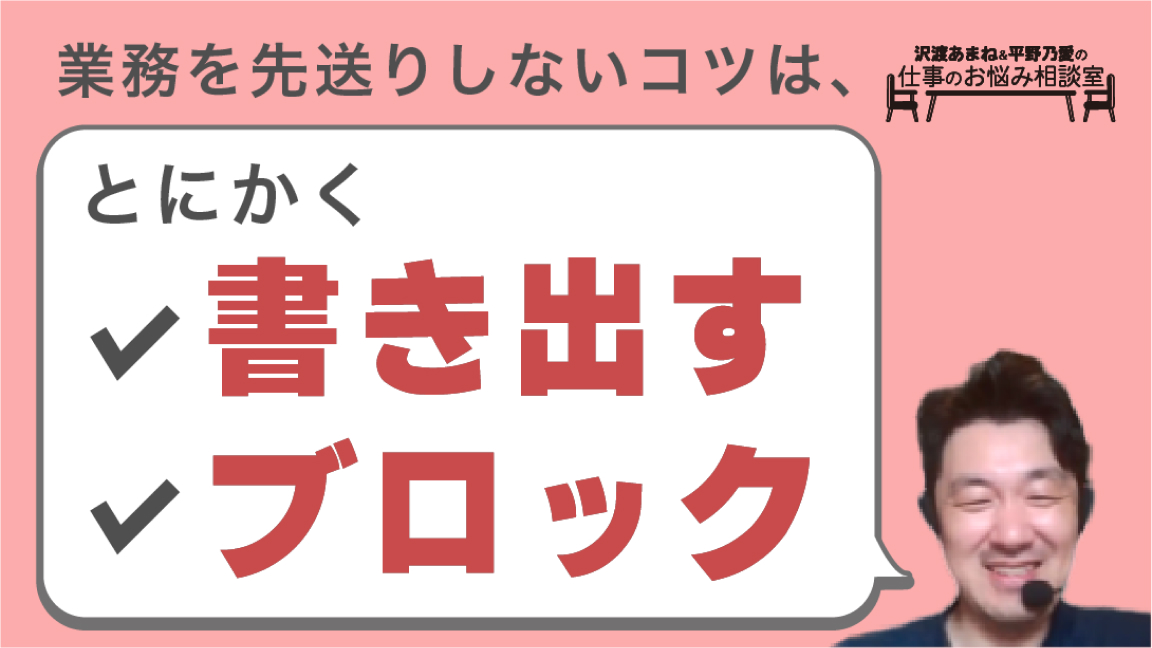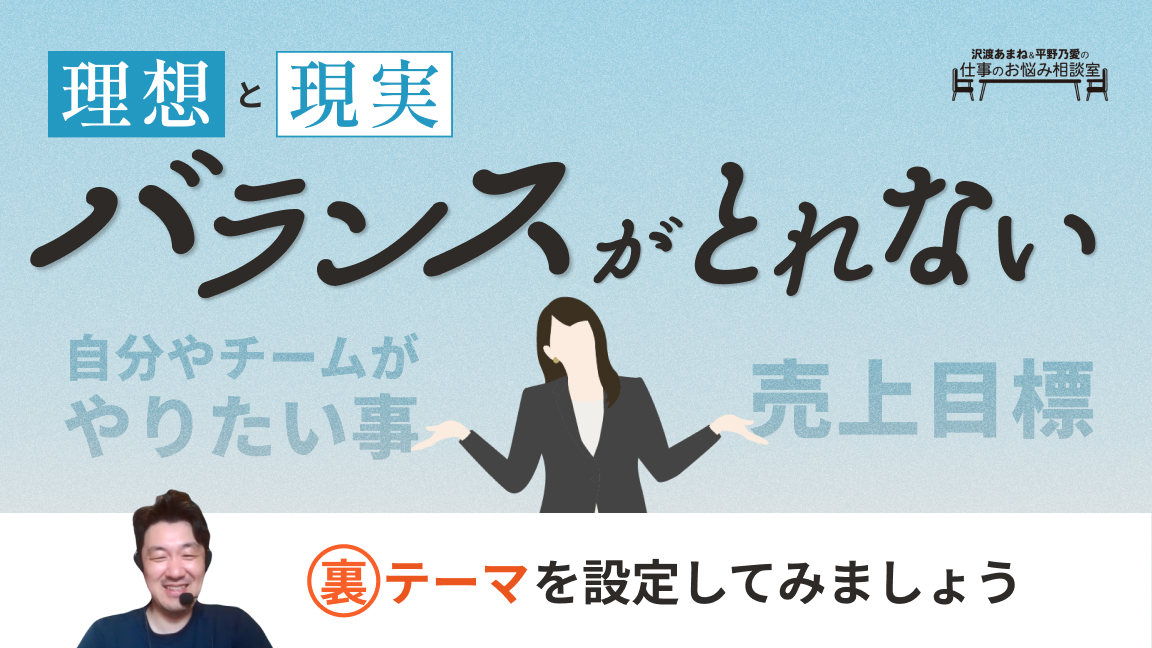管理者はログインして下さい。
おすすめ記事
KPIの設定の仕方
KPIとは、「目標の達成に向けて重要な要素を数値化したもの」のことです。 KPIをなぜ設定するのか? それは、目標達成に向けての進捗管理を確実に行うためです。 KPIの設定においては2つのことを可視化することが大切です。 とある営業組織で「1000万の売上金額」「月10件の受注」という目標を掲げている場合を例に解説します。 1つ目は行動の可視化です。 達成に向けて行動管理をするためには、やらねばならないことを行動に落とし、分解し数字にする必要があります。 例えば、「月10件の受注」をするためには、 ・受注数は見積り提出数の1/3を見込むとすると、見積提出件数は30件必要 ・見積提出のために必要な商談数は100件 ・これを1日にならすと5件の商談となる、など、 目標から逆算して必要な行動を洗い出していきます。更に既存案件からのリピート率も視野に入れると、 必要な数値がより明確になってきます。 2つ目は状態の可視化です。 「1000万の売上金額」を「月10件の受注」で達成するためには、 1件あたりの販売価格が平均100万円でなければいけません。 受注件数が順調でも、販売価格が想定を下回っていたら達成されないわけです。 このように案件の規模も考え、大型・小型案件の商談比率も設定するとよいでしょう。 このように、2つの視点(行動と状態の可視化)をもって目標を分解していくことで、 達成に向けての適切な行動とその進捗管理が容易になります。 定量的な指標を定められない場合は、定性的なアクションをKPI化するという場合もあります。 代表的な例は、目標に向かって設定したマイルストーンのタスク消化率などをKPI化するというケースです。
チャレンジングなアサインをするときに気を付けること【依頼編】
人の成長に影響を及ぼす要素は、70%は経験、20%は他人からの助言、10%は研修や書籍からの学びと気づきといった調査結果があります。人材育成の観点では、チームが関与する割合は非常に大きく、チーム内でいかにメンバーが成長する経験を積むことが出来るかが、チームの価値発揮に大きな影響を及ぼします。 そのため、ときには、チャレンジングなアサインが重要になってきます。 このアサインをする際には、以下のポイントに注意を払ってください。 ・依頼元が着地イメージを出来ていない 完了している状態が依頼元も分からない場合に、アサインを考えても失敗しやすくなります。 この着地イメージが湧いていないまま依頼することは、無茶振りといいます。 着地イメージが湧いていないと、本当に依頼先の方が適切なのかどうか(本人の志向性が合っているか、ハードルが高すぎ/低すぎないか)、判断が出来ません。 更に、アサイン後にフォローについても、イメージが無いままでは具体的なアドバイスが上手く出来ません。 このようなことの発生するリスクが高いために、依頼元は着地イメージを想定してから、アサインを検討する様にしてください。 ・本人の志向性とのマッチングについて 依頼先の方の志向性やチャンレジしたいことと、こちらからお願いしたいことが100%マッチすれば良いですが、必ずしもそうではないケースもあります。チャレンジすることで得られることは何か?をまとめて、依頼元の方に対して完了したときの成長した自分の姿や、達成した状態など、より具体的なイメージを持ってもらえるようになります。 そうすることで、アサインへの納得感を上げることに繋がります。 ただし、全く志向性と違うケースもあり得ます。その場合は、正直にそうせざるをえない理由を伝えて、双方で納得した上で進められるとよいでしょう。
QCDSの見直し
期の終わりのタイミングでは、目標とセットに、QCDSの見直しが必要かどうかを検討します。 振り返りをしてみると、QCDSのトレードオフはうまくいっていたとしても、 予定よりも多くのコストを投入して解決していることも多くあります。 期の変わり目については、関係者内では予算を組み直すため、QCDSそのものを新たに設定できることが多くあります。 このタイミングで振り返りを行い、QCDSそのものの見直しをするかどうか検討し、関係者と見直しを行いましょう。
ミッションの策定方法
〈目次〉 ミッションを策定する理由 ミッションを策定する時に考えること 関連資料 1. ミッションを策定する理由 ミッションとは、自チームの存在する理由のことです。 把握したニーズをその背景まで深堀し、チームで「やるべきこと」として落とし込んで、チームの「ミッション」を作成します。 ミッションというと、会社や事業部などの大きな組織単位のものという印象があるかもしれませんが、チーム単位であってもミッションを明確にすることで、チームの意識が統一されゴール達成に近づきます。 ミッションを策定することの効果 ミッションを明確に言語化しておくことで、初心に立ち戻るための仕組みを作ることができます。 対面で人と接する仕事の場合は、相手の反応が分かりやすく目標達成の実感を得やすいため ミッションの解像度を高く保ちやすい傾向があります。 一方、多くの人が関わる複雑な工程の中で、直接的な接点が少ない役割を担う場合は、相手の解像度が不鮮明になりがちです。 その結果、目の前の作業に意識がとらわれ、徐々に本来の仕事の目的意識が薄れてしまうことがあります。 このような状況に陥った時のためにも、初心に立ち戻る仕組みとしてミッションを策定しておくことは有効です。 ミッションが明確に定められていれば、目的意識を持続しやすくなり、結果として仕事の質が向上します。 Tips ミッションは迷ったときの道標となる北極星のようなもの北極星はほとんどその位置を変えない星のため、大昔には旅人を助ける夜空の目印とされていたそうです。ミッションにも、この北極星と同じような役割があります。具体的な目標の背景にある「何のためにやるのか」「何のためにチームが存在するのか」を ミッションで明文化することで、何か迷ったときに立ち返る拠り所になり、チームの結束を強めることができます。 2. ミッションを策定する時に考えること 大きな組織だけでなくチーム単位でもミッションを明確にすることで、結束が強まり効率的な目標達成が可能になります。 チームのミッションを作る際には、以下を考えましょう。 全員の納得と共感が得られるかチームメンバー全員が納得・共感できるミッションを見つけることが重要です。これには、関係者のニーズと総合的に紐づいている必要があります。関係者のニーズの例:顧客や組織の大方針、メンバー一人ひとりのキャリア志向やコンディション、チームの1年後のありたい姿 仕事の目的を明確にする問いに答えられるものであるか 「我々の仕事は誰のどのような問題を解決することなのか?」 「問題を解決をするために、我々は何をするべきなのか?」 上記のような「すべきこと」を明確にする問いに答えているミッションであると良いです。 シンプルで共感を得やすいかミッションは関係者のニーズに基づいて、チームの使命や判断の軸となるものですので、背景にある目的を明文化し、できるだけシンプルにまとめることでメンバーから共感を得やすくなります。 言語化の重要性 ミッションを言葉にすることは手間がかかりますが、チームが結束するための第一歩として非常に重要です。丁寧に言語化することで、チーム全体が同じ目標を共有し、一体感を持って行動することができるようになります。 このプロセスを丁寧に行うことで、チームのミッションが明確になり、 全員が同じ方向を向いて効率的に仕事を進めることができるようになります。 <ミッションの例> 策定したミッションは、チームに共有することで組織の一体感が生まれます。必ず共有するようにしましょう。 3. 関連資料 ▶▶【🎥動画】目標設定を「苦手なもの」から「働きやすくする手段」に変える方法はこちら ▶▶【📝記事】目標設定を設定するコツ はこちら