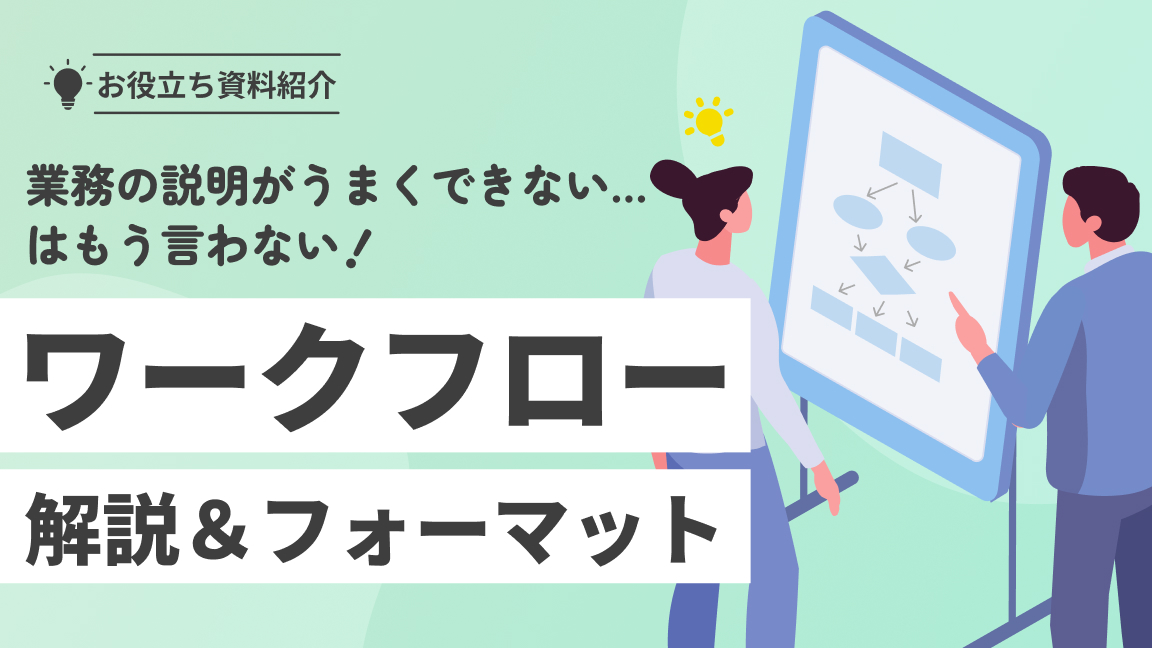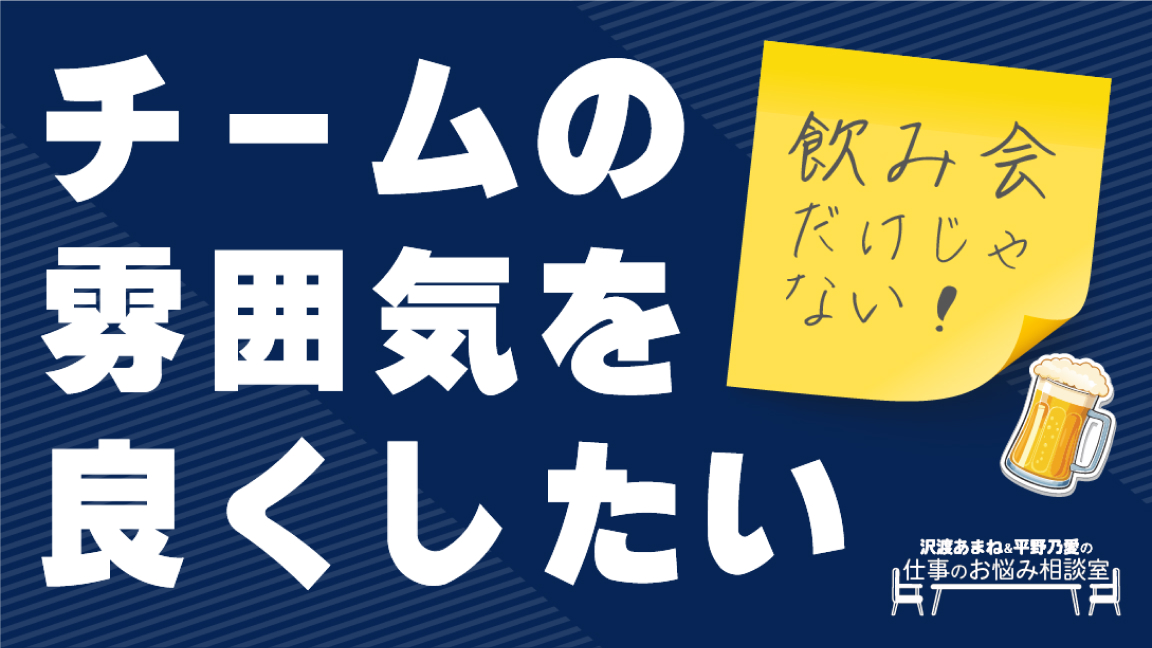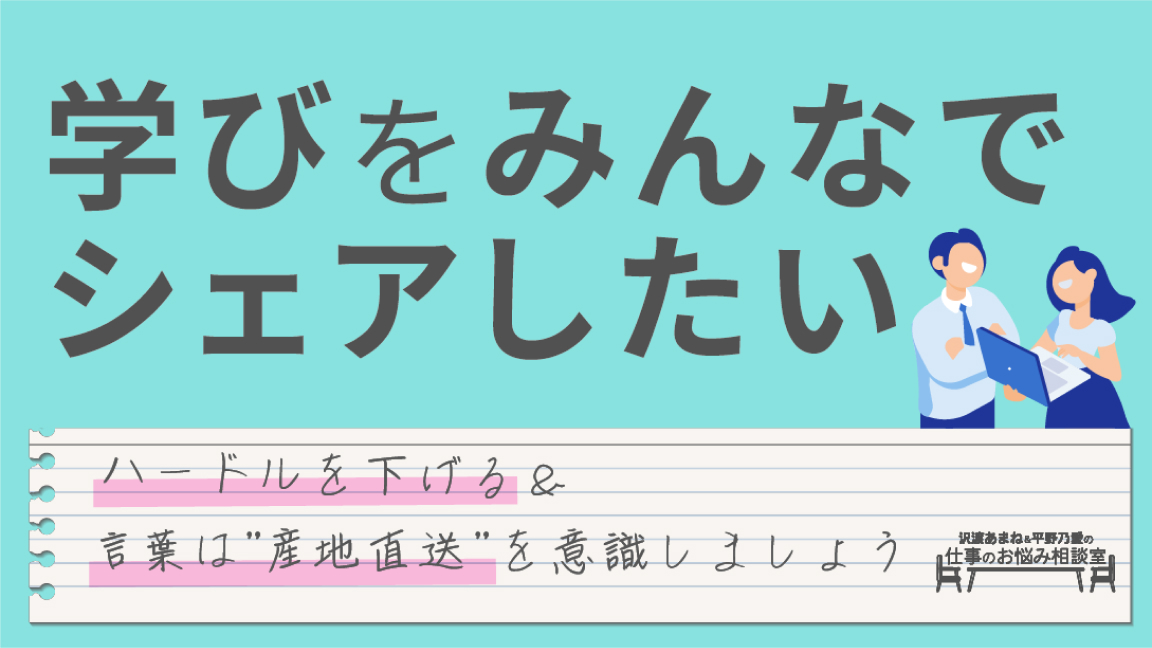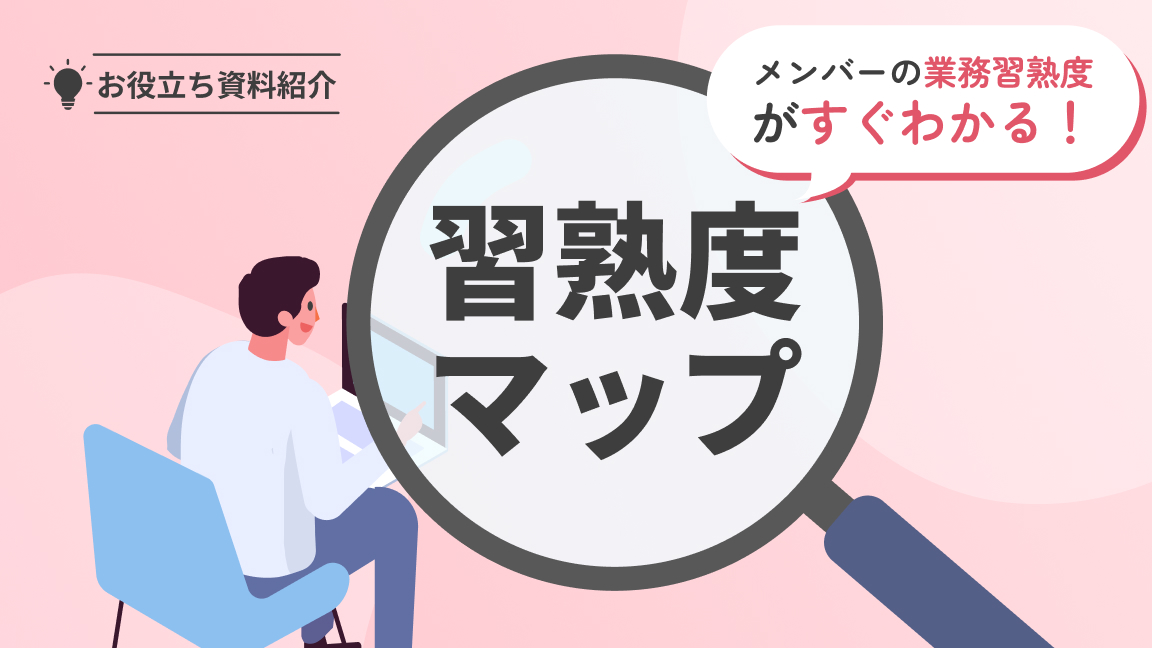管理者はログインして下さい。
おすすめ記事
計画の見直しをするには?
〈目次〉 振り返り用のデータを揃える 予実差を確認し要因分析を行う 振り返りを次期計画に反映させる 関連資料 計画は、期初に立てたものから予定通り行かなかったり、時間がなく立てたきり見直しを忘れてしまうことがあるかもしれません。 ここでは、期末など定期的なタイミングで行う計画の見直しについて考えていきます。 まずは今期の振り返りをし、それぞれの要因と対策を検討し、来期計画に反映させていきましょう。 1. 振り返り用のデータを揃える 振り返りをするために参照するべきデータは様々ありますので、以下を参考に必要なデータを揃えてください。 自チームに関すること チーム目標の進捗、結果 メンバーの個人目標の進捗、結果 自組織に関連すること 自社の今期目標の進捗、結果 自社の来期方針 顧客に関連すること CSアンケート(顧客満足度調査等) 顧客組織の来期方針・キックオフ資料 ※CSアンケートについて CSアンケートは、内容だけを確認するのではなく、 可能であれば、顧客に対してフィードバック・ヒアリングの機会を持つことが望ましいです。 せっかく行った施策も、相手のニーズを満たしていなかったり、 伝わっていないと意味が薄れてしまいますので、この機会にすり合わせしておくと良いでしょう。 施策が顧客のニーズに合っているか、効果が伝わっているかを確認することで、施策の精度を高めることができます。 2. 予実差を確認し要因分析を行う 振り返りを行う際は、予実差(計画(予) と 実際の結果(実) の間に生じた差)を確認します。 単純に結果を評価するだけでは、なぜその結果になったかの要因が分からないため、 過程も振り返った上で「なぜその結果・予実差になったのか」を深掘りし、原因分析を行い次期活動計画へ反映します。 過程については時間が経つにつれて思い出しづらくなってきますので、 3か月に1回の振り返りを行って、その学びを可視化しましょう。 <以下、イラストの予実差から見る要因分析の例> 過程と結果 4月 プロジェクトを進める中で、人員が足りないと判断し2名増員 6月 育成計画でトラブル発生 7月 1か月延期を決定 要因 計画当初は、作業工数を見積り通りに進められることを想定していたが、実際は想定以上に●●の作業に複雑さが増したため増員。 増員時に育成を実施したが、新メンバーに合わせた習熟期間の考慮が漏れており遅延。 分析におけるポイントは全体を俯瞰して考えることです。 例えば成果が出なかった時に「やり方が悪かった」「能力が足りない」と短絡的に捉えるだけでなく、 「そもそも成果の基準が適正でない」「目的と手段が合致していないため、モチベーションに影響を与えている」など 様々な要因を見つけるために、俯瞰的な視点で見直すことが重要です。 Tips フィッシュボーン図を活用する 要因分析の手法としてフィッシュボーン図を活用してみましょう。 これは、問題解決や、成功要因の分析時に結果がどのようにしてもたらされたかを図式化して、 成功要因や、問題点をあぶり出すのに用いられます。 また、チーム間で要因の共通認識を持ちやすくするためにも有効です。 3. 振り返りを次期計画に反映する 振り返り・分析の結果をもとに、来期計画へ具体的に反映します。 新しい計画に合わせアクションプラン調整することで、よりチームの目標達成に近づきます。 改めて設定した計画については、チーム内に共有し、顧客とのすり合わせをしておくと チームのパフォーマンス向上が期待できます。 4. 関連資料 ▶▶【🎥解説動画】計画フォーマット はこちら ▶▶【📅フォーマット】マスタースケジュール.pptx はこちら
人材要件の設定、見直し
人材要件はチームに配属されるメンバーに最低限必要なスキルや適性を定めたものです。 人材要件を定める理由は、チームメンバーや人事部門等の人員配置に関わる部署とでチームに求められるメンバー像を共有し、適切な人材配置を実現するためです。 人材要件の設定方法 人材要件は、業務の特性を考慮し、チームの一定要件に加えて各役割の必要条件を追加してください。 受入基準では主に次の3点「適性」「専門スキル」「ビジネススキル」を明示しましょう。 また受入基準に加えて配属されるメンバーが業務を通じて「どのような経験を得られるか」「どのようなキャリアに繋がるか」を明示すると良いです。 適性 業務特性と候補者の特性がマッチするかを判断する必要があります。 スピード、正確性、共感性など、どのようなことが求められるのか、チームの環境や業務特性によって、候補者に求められる適性は異なります。 特に変化対応が多い業務を進めていくには、柔軟性は重要な適正ポイントになります。 専門スキル 業務を遂行する上で必要な業務経験、専門スキルを第三者が見ても分かるように表記します。 業務経験(業務内容や経験年数) 専門スキル(保持資格や過去の成果) ビジネススキル ビジネススキルとは、一般的にビジネスパーソン/社会人として求められる素養のことを指します。以下に具体例を示します。 コミュニケーションスキル リーダーシップ 仕事に対する姿勢 社会人としてのモラル 社会人としての一般常識 人材要件を見直す際は、一定期間の稼働の実績と成果実績から、見直していきます。 例えば、日々・毎週の業務の中で冗長化を目的とした役割変更を行うことが多くあります。 この結果、当初は「スピード」が速い方が良いと想定されていた役割も、実際は「正確性」の高い方が、効率的に仕事が進んだ。 当初は「システムの知識」が必要と想定していたが、実際には知識が要求されるシーンは稀であった、などといった気づきを得ることが多くあります。 このような実績から、改めて要件を見直すとよいです。
業務の悩みや課題を解決するヒントを見つける!COROPS診断
あなたの気になる悩みを解消するヒントや、おすすめのコンテンツを見つけてみませんか? 仕事を進めるうえで、より良い方法やアイデアを探している方へ。 業務の悩みや課題を解決する情報がここにあります! この診断では、悩みや課題を解決する方法と、 COROPS WEBの中からあなたにぴったりのおすすめコンテンツをご紹介します! Q1 はい → Q2へ いいえ → Q3へ Q2 はい → Aタイプ いいえ → Q4へ Q3 はい → Bタイプ いいえ → Cタイプ Q4 はい → Q5へ いいえ → Q6へ Q5 はい → Dタイプ いいえ → Q6へ Q6 はい → Eタイプ いいえ → Q7へ Q7 はい → Q8へ いいえ → Bタイプ Q8 はい → Cタイプ いいえ → Bタイプ
生産性向上に紐づく問題解決とは
問題の種類は2種類あります。 ・設定型の問題 目の前では起きていない問題。1か月、半年、1年後という未来のあるべきをチームや顧客と設定し、そこから解決すべきことを考える ・発生型の問題 目の前で起きている問題。トラブルやミスなどが発生し、現況へ回復し元に戻すた目に解決すべきことを考える 生産性が向上していくということは、設定型の問題を解決しているということです。 設定型の問題解決は、期初、棚卸し、見直しのタイミングで考えることが多く、まずゴールのイメージから考え、現状を把握し、問題を設定していきます。 どうしても当初計画は粗くなりますが、これを踏まえた上で、直近のスケジュールから詳細化して進めていく事が重要です。 しかし、詳細化を行わないまま進めてしまっているケースは少なくありません。 例えば、1か月単位ではやることは分かっていても、そこから、1週間、日々と計画を立てられていないことは多いです。 期間を長く設定しているために、アクションがなかったとしても、明日、来週にリカバリーが出来ると思ってしまいがちです。 このままズルズルと1週間、1か月と経過し、いざ進捗を見ると全く進んでいない。そんな経験はないでしょうか。 少しでも前に進めていくためには、最低でも直近の1週間は何をすべきか、そこから一日の動き方を決めていくことが必要です。