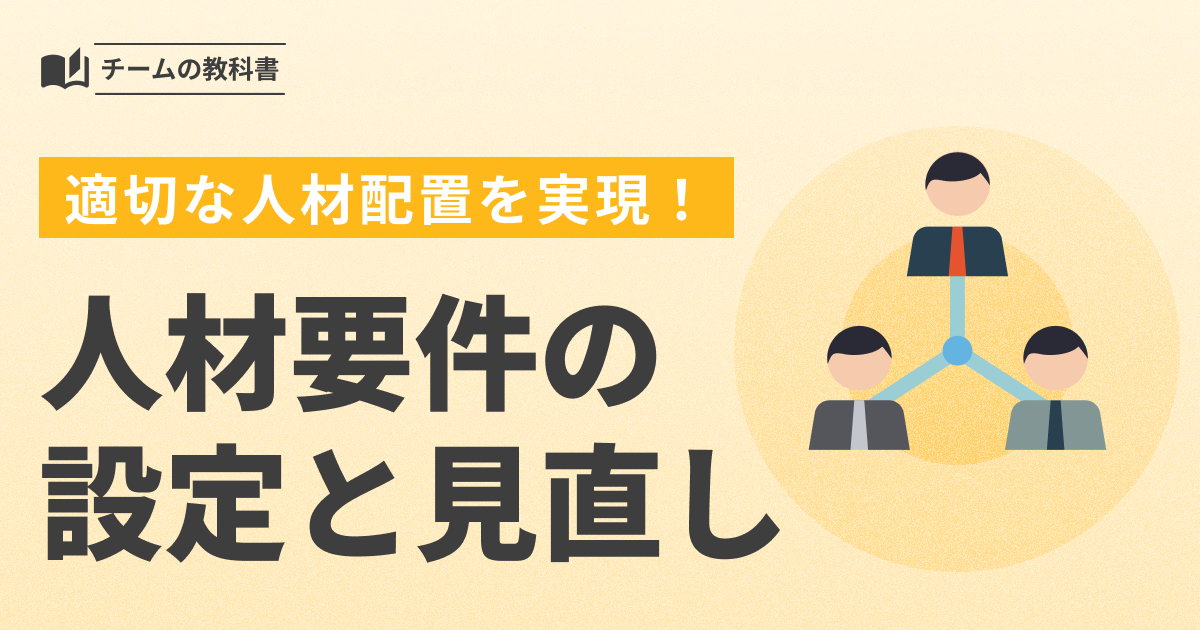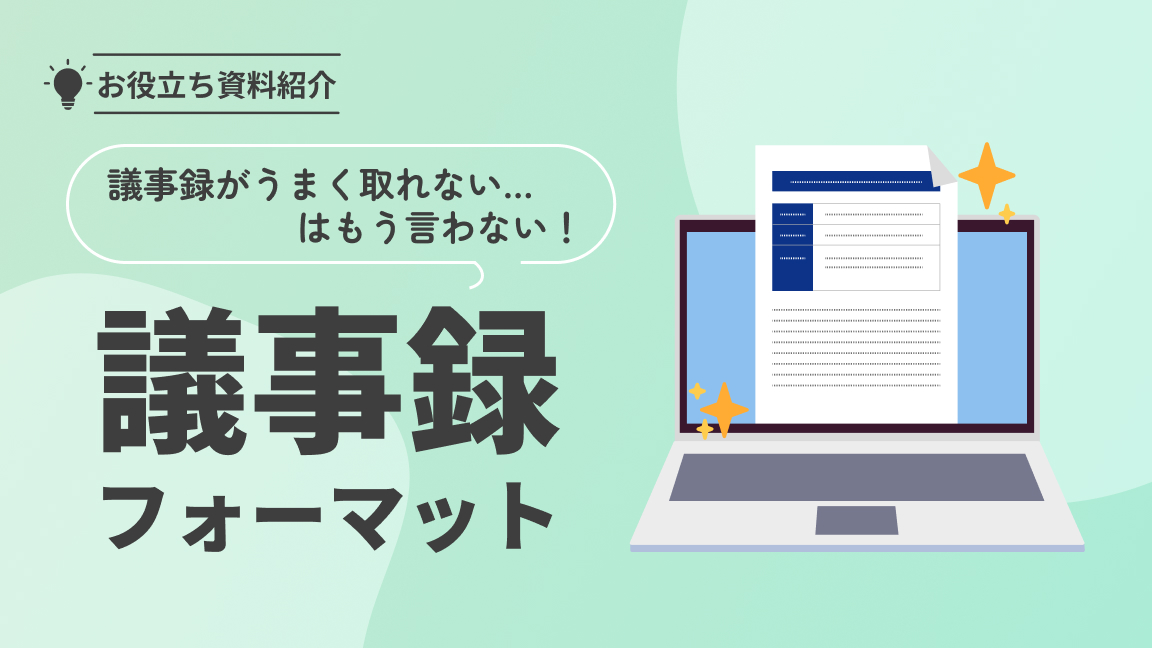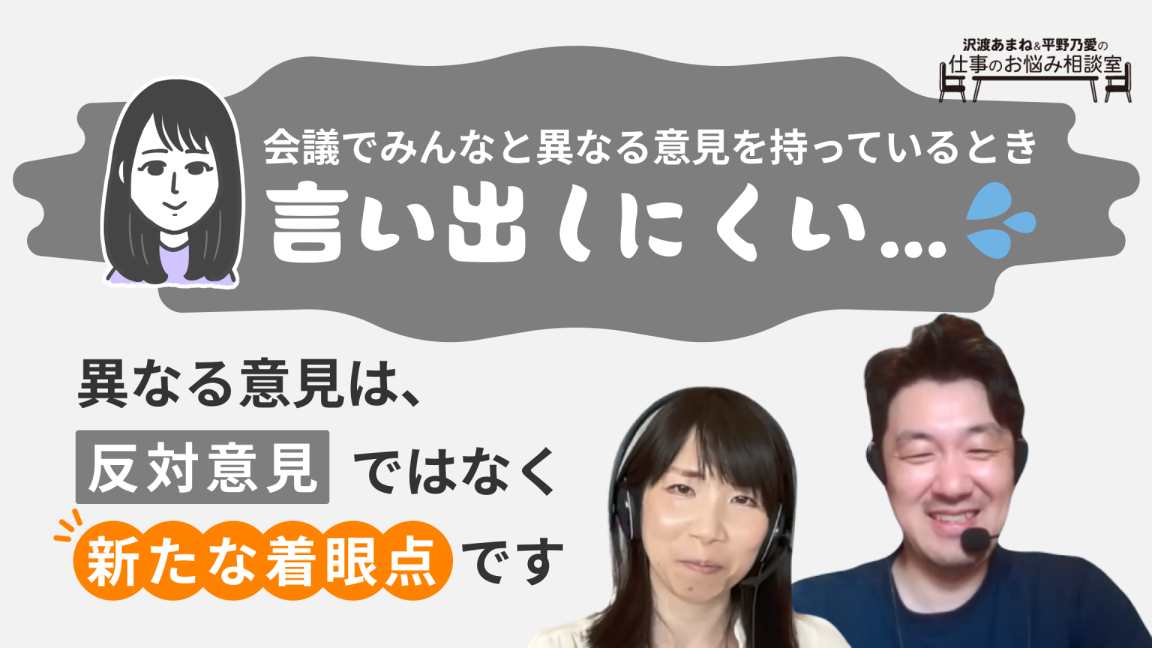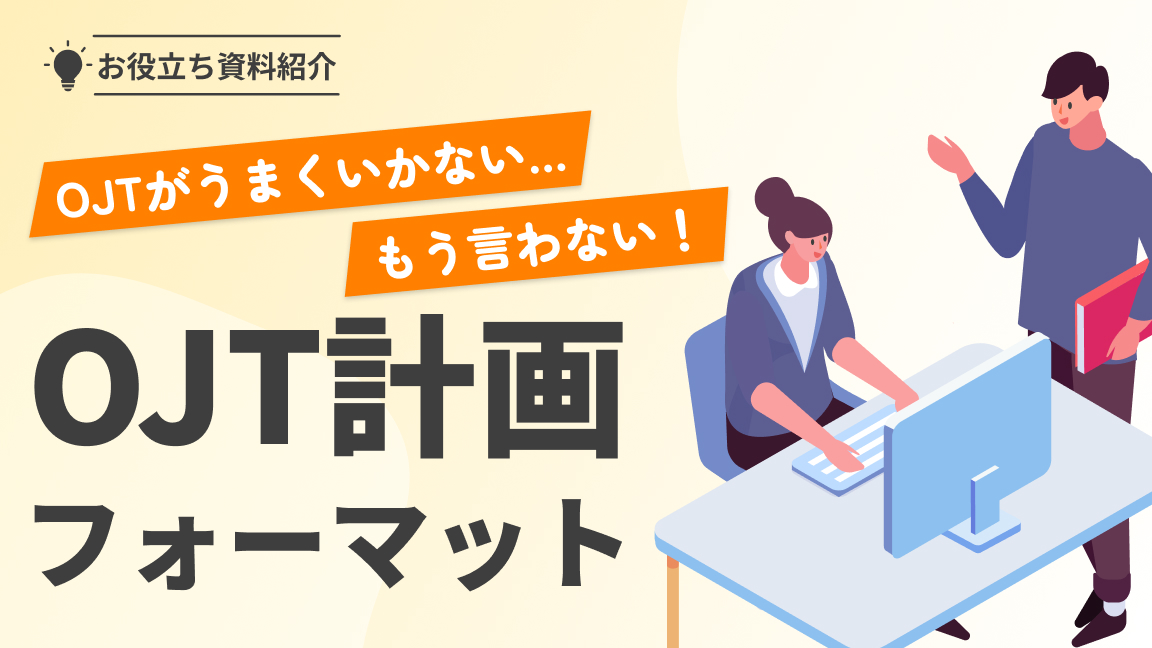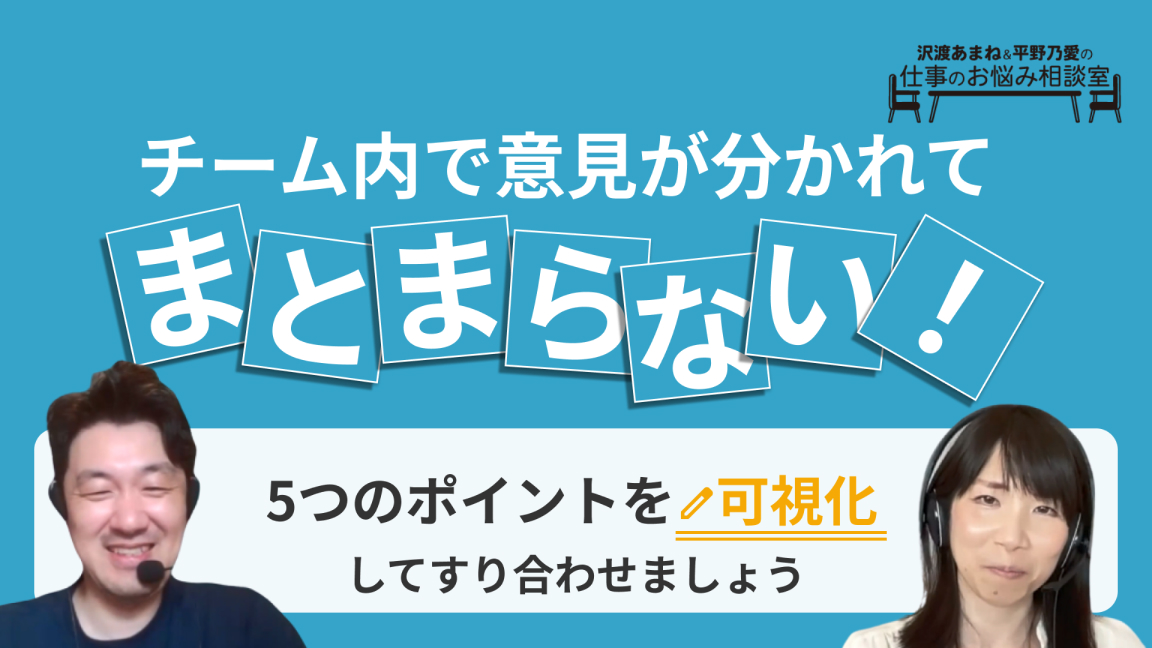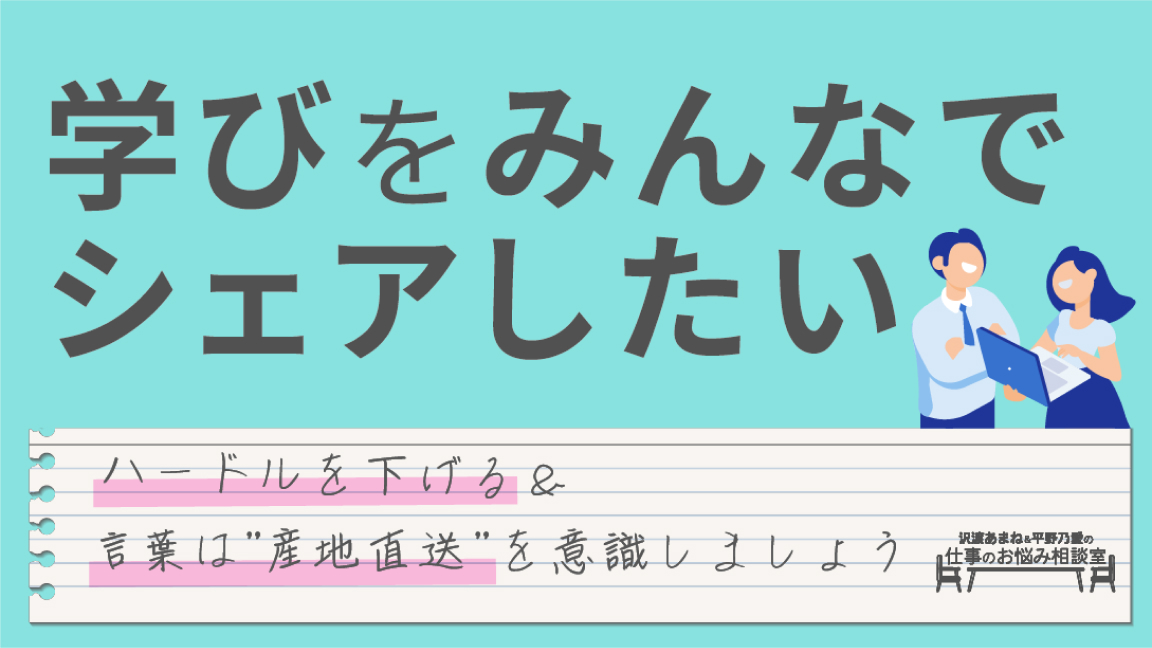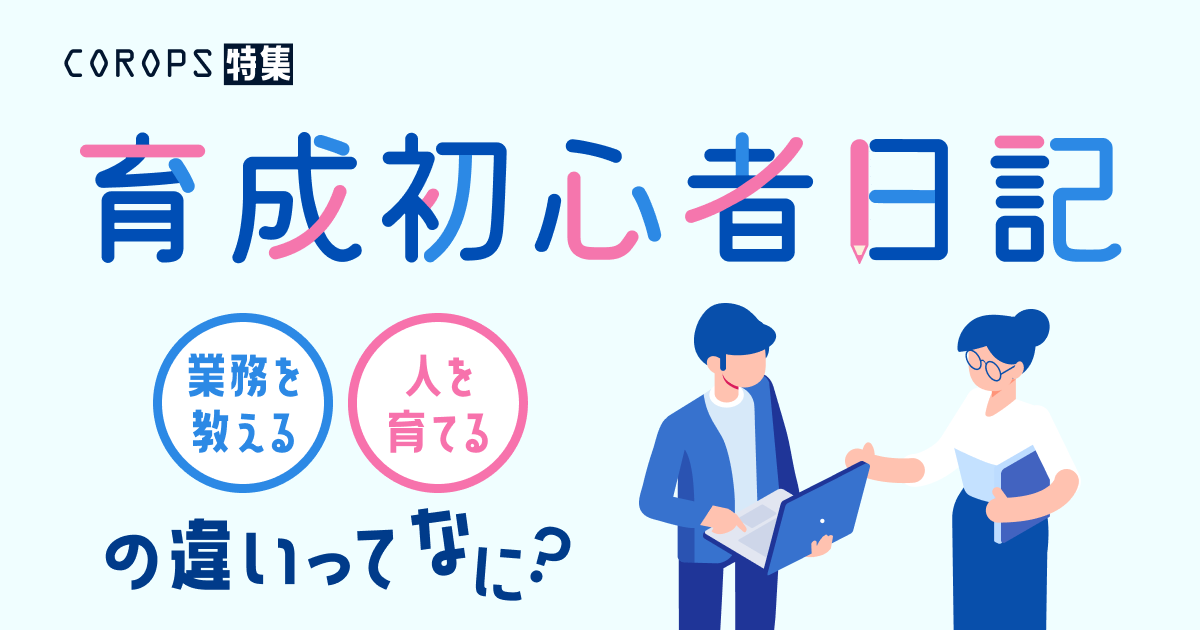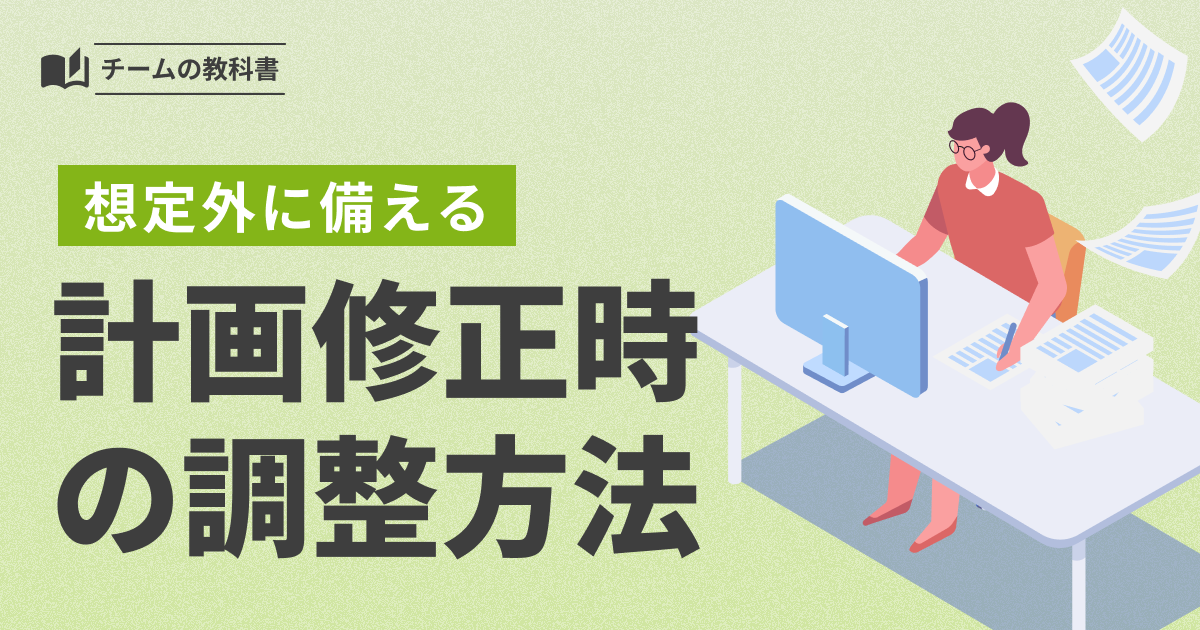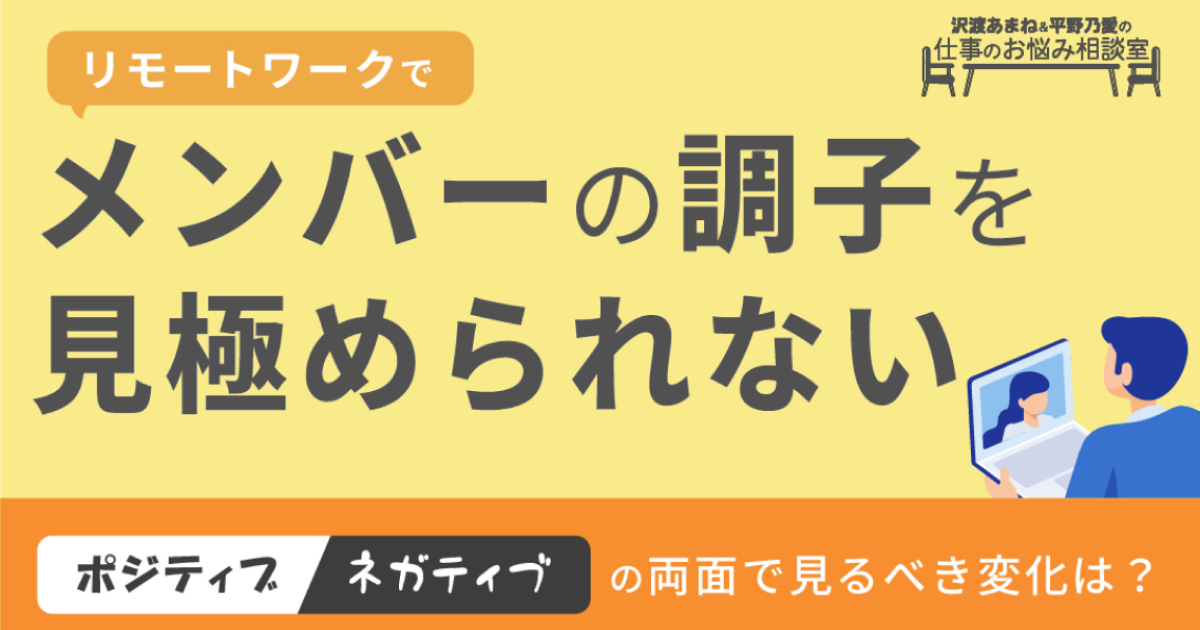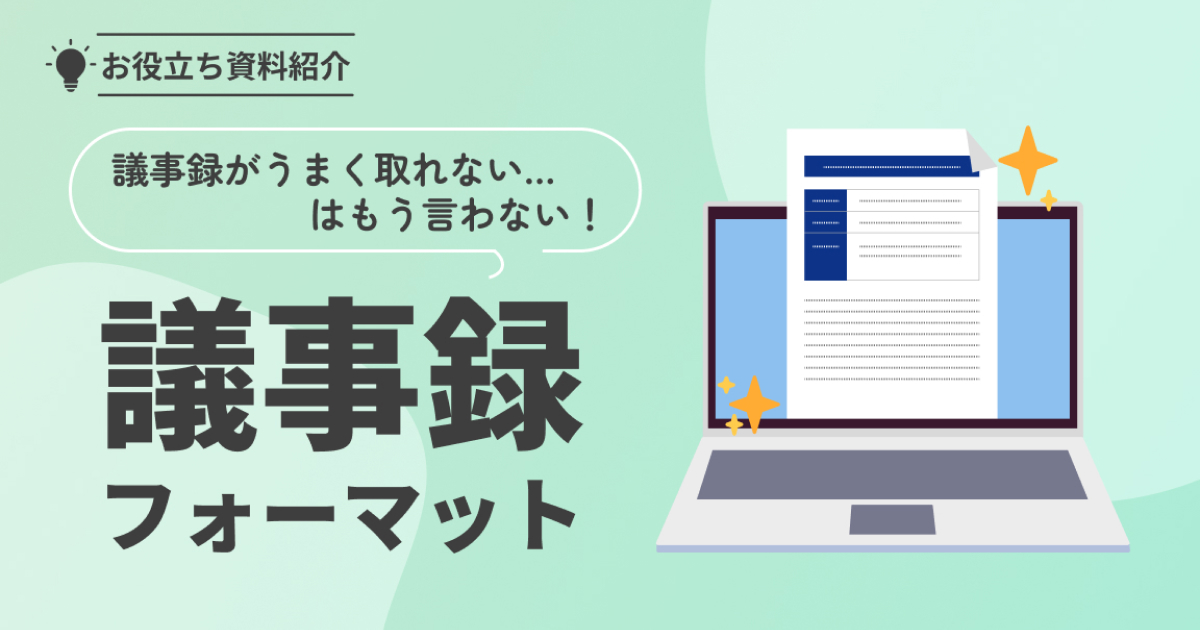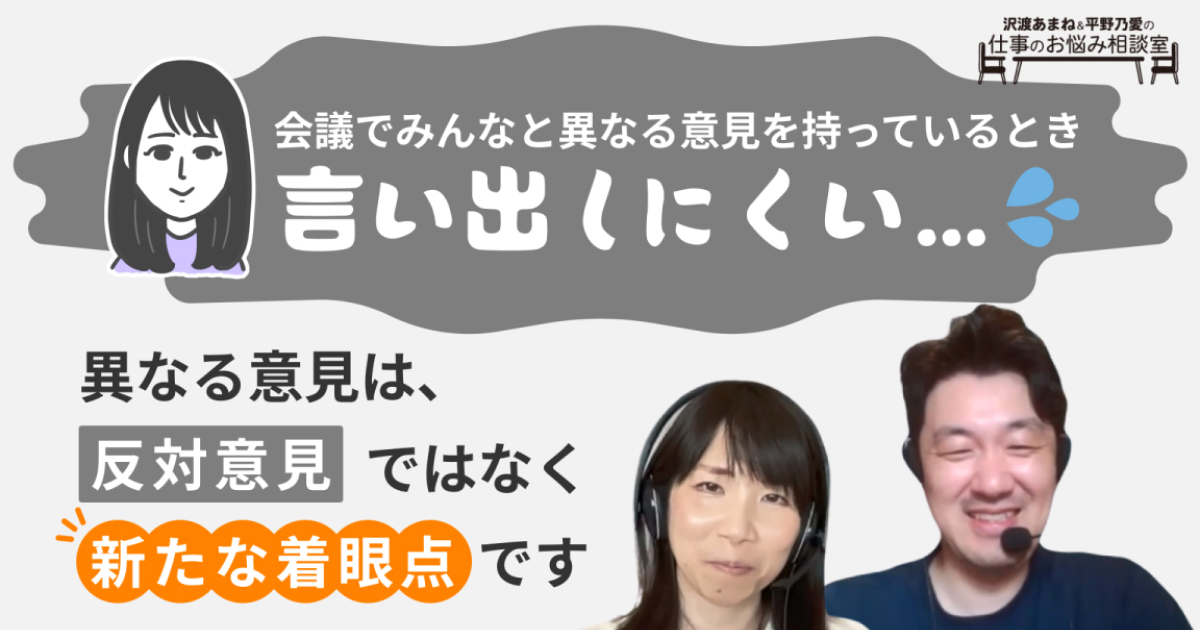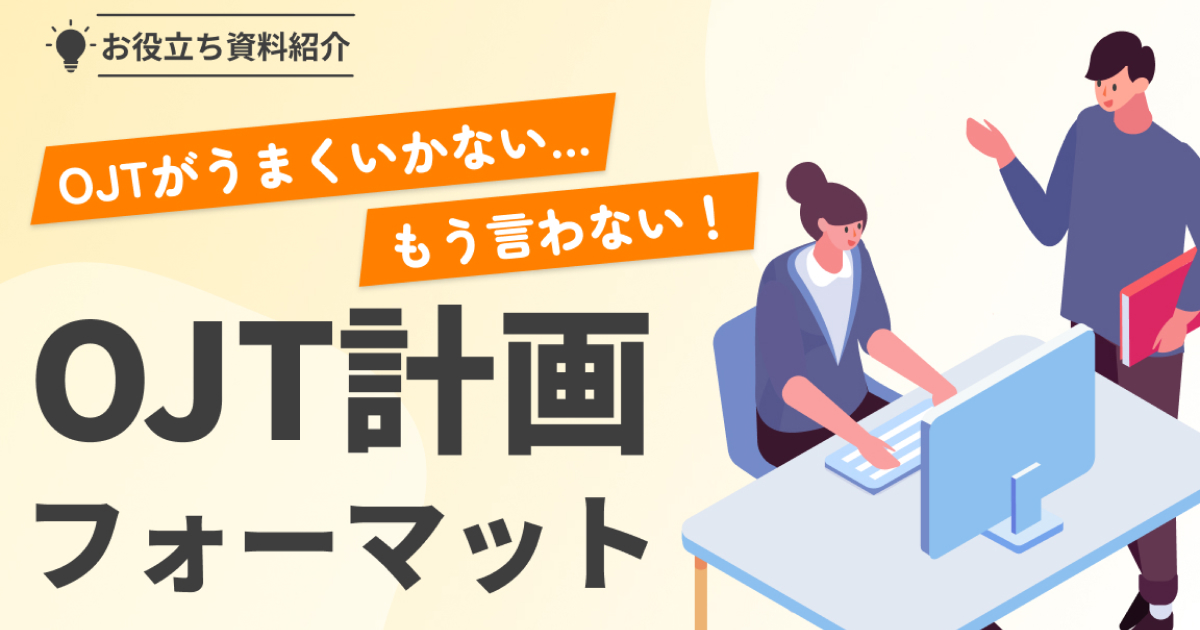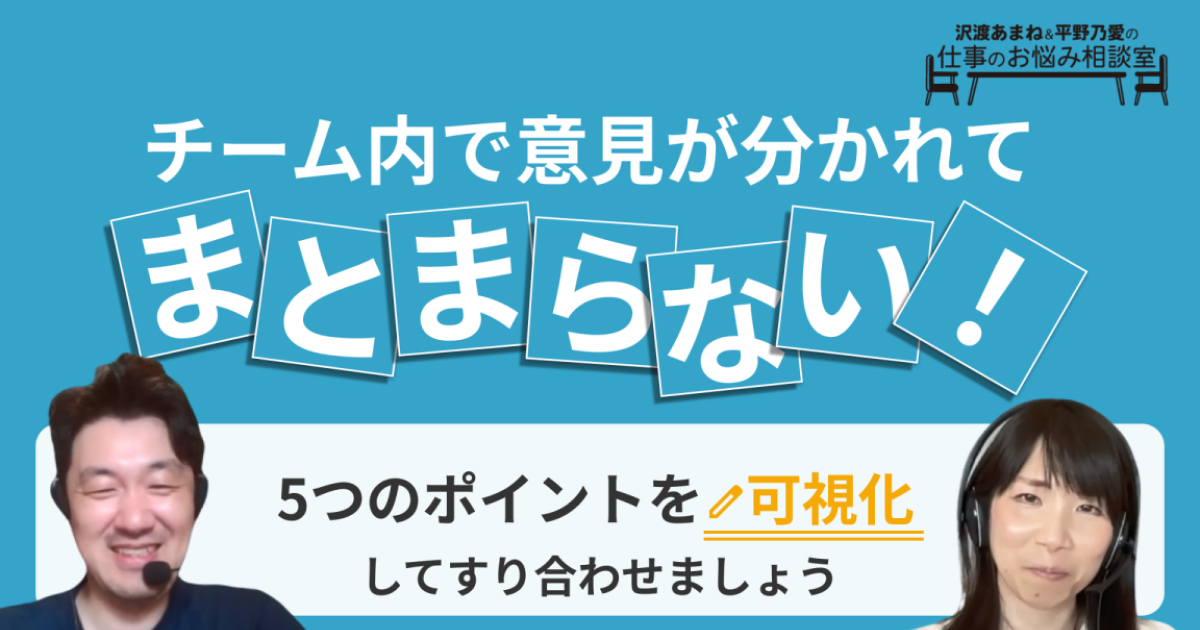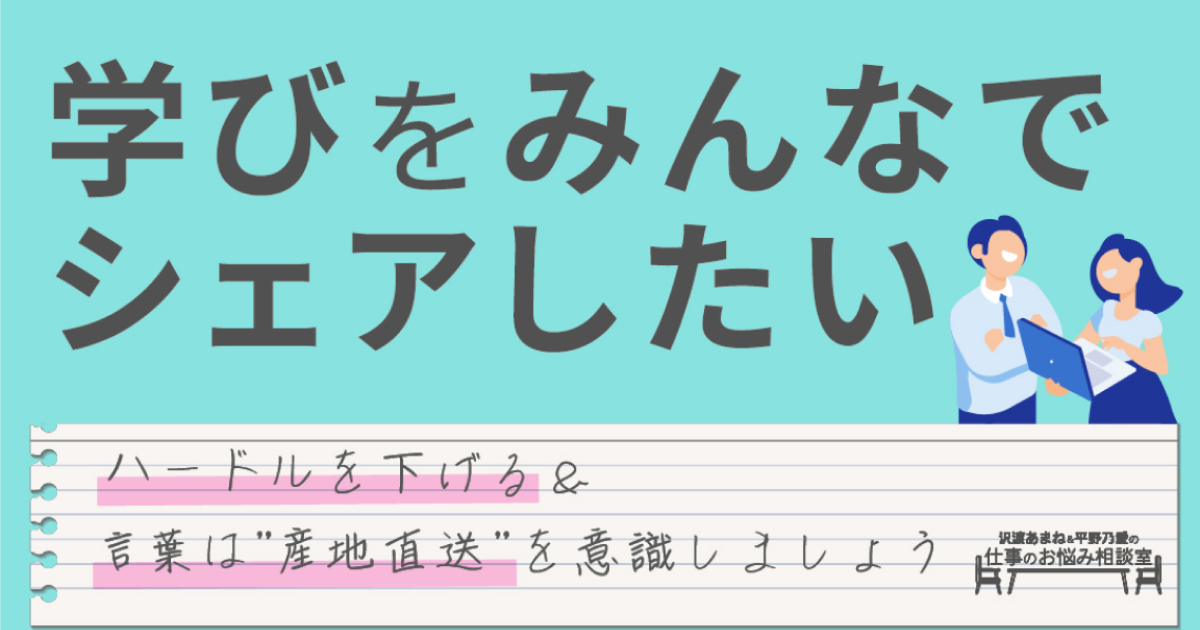成長を促すアサインの仕方とフォローの仕組み
チームの仕組み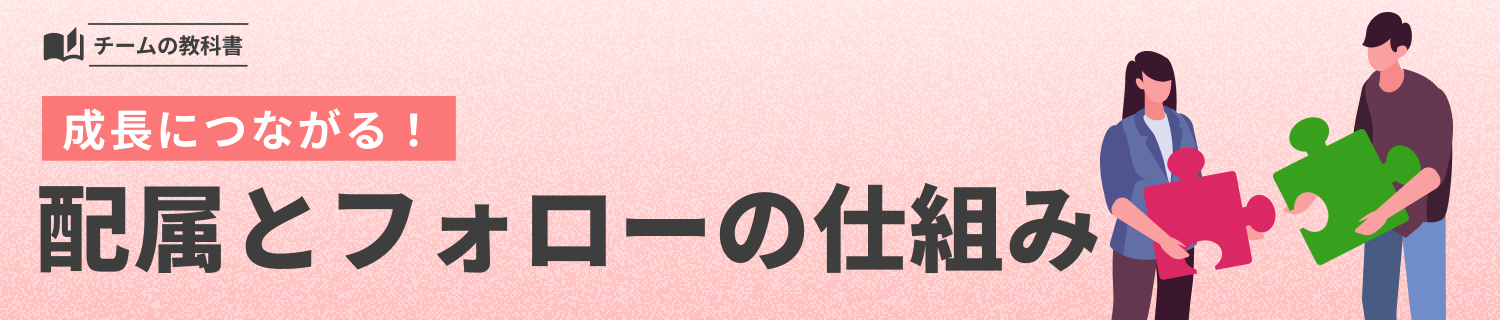
人材育成において、70%は「経験」からの学びが成長に影響すると言われています。
特に、メンバーがこれまで経験したことのない領域や、少し高いハードルに挑戦する
「チャレンジングなアサイン」は、成長を加速させる大きな機会です。
この機会を通じて、メンバーは新たなスキルや視点、自己効力感を獲得し、
その結果、チーム全体の価値向上にもつながります。
この記事では、チャレンジングなアサインの定義とその具体例を紹介した上で、
それを成功させるための「配属」と「フォロー」のポイント、さらにそれを支えるチーム体制設計について解説します。
1. チャレンジングなアサインとは?
チャレンジングなアサインとは、メンバーがこれまで経験したことのない領域や、
少し高いハードルに挑戦する機会を与えることです。
これにより、メンバーは新たなスキルや知識を獲得し、成長することができます。
例
- 初めての顧客対応やプレゼンテーション
- 新規プロジェクトの立ち上げやリーダー役
- 他部署との連携業務や外部との交渉
- 業務改善や仕組みづくりなど、抽象度の高い課題への取り組み
アサインの効果
チャレンジングな経験は、個人の成長を促すだけでなく、以下のような効果をもたらします。
- 自己効力感の向上:挑戦を達成することで、自信を得ることができる。
- チーム全体のパフォーマンス向上:個々の成長がチームの価値を底上げする。
- 新しい視点や能力の獲得:未経験領域への挑戦が、新しい視点を生み出す。
チャレンジングと無理の違い
「チャレンジング」であることが「無理をさせること」とイコールではありません。
適切な配属やフォローがなければ、メンバーが過剰なストレスを抱えたり、挫折してしまうリスクがあります。
チャレンジングなアサインを成功させるためには、「成長機会」と「心理的安全性」の両方を意識することが重要です。
2. アサインを行う際の配属のポイント
チャレンジングなアサインを成功させるためには、適切な配属が重要です。
メンバーの成長と業務成果を両立させるために、以下の要点を押さえることが必要です。
①ゴール着地のイメージを持つ
配属元が「完了状態」を明確に描けていない場合、アサインは失敗しやすくなります。
着地イメージがないままの配属は“無茶振り”となり、適切な人選やフォローが困難になります。
②志向性とのマッチング
メンバーの志向性とアサイン内容が一致しているかを確認しましょう。
完全一致でなくても、チャレンジによって得られる成長やスキルを具体的に伝えることで、
納得感を高めることができます。
志向性と異なる場合は、正直に理由を説明し、合意形成を図ることが大切です。
3. アサインを行う際、管理者のフォローポイント
未経験の業務やチャレンジングなアサインでは、メンバーが安心して取り組めるようなフォロー体制が欠かせません。
心理的安全性を保ちながら成果を最大化するために、以下のポイントを意識しましょう。
①丸投げしない
未経験領域では仮説の精度が粗く、軌道修正が頻発します。
心理的安全性を保つために、定期的な相談時間(例:15分/日、1時間/週)を事前に設定しましょう。
②細かいチェックをしすぎない
細部まで過干渉してしまうと「任せられたはずでは?」という不信感につながります。
管理者はP/L(損益計算書)や稼働管理表、タスク一覧などを活用し、状況を可視化することで、報告・相談の効率を高め、メンバーに任せられるようにしましょう。
③相談の基準を明確にする
チャレンジングな業務では、相談のタイミングが分かりづらくなります。
「30分考えても糸口が見えない場合は相談する」など、時間を基準にしたトリガーを設定することで、
メンバーに心理的負担を与えずにスピード感を保ちながら前進できます。
4. チーム体制の作り方
チャレンジングなアサインを行う場合、業務量の偏りや負担が大きくなると、チーム全体のパフォーマンスが低下しかねません。
これを防ぐために、以下のポイントを意識した体制設計を行いましょう。
①常に余力を持つ
業務量に対してギリギリの人員配置は、残業の常態化や改善余力の欠如を招きます。
業務改善・自己研鑽・緊急対応のバッファを含めた余力設計が重要です。
②マネジメント工数を確保する
管理者がプレイングに偏ると、メンバーの育成や状況把握が疎かになります。
一時的な対応であっても、根本的な体制見直しの計画をステークホルダーと共有しておきましょう。
③チーム内の協力体制をつくる
効果的な協力体制を築くためには、メンバー同士が状況を共有しやすい環境を整えることが大切です。
共有された情報を活用し、チーム全体で支援し合える仕組みを作ることで、相乗効果を最大化することが可能です。
- メンバーのミッション・進捗・工数負荷・困りごとを共有する
- 状況が分かれば、自然とフォローし合える関係が生まれる
- チームは単なる労働力の総和ではなく、相乗効果を生む場である
|
|
5. まとめ
チャレンジングなアサインは、メンバーの成長とチームの価値向上に直結します。
その成功には、配属の設計、フォローの仕組み、そして無理なく支える体制づくりが不可欠です。
チーム全体で支え合いながら、挑戦を成長につなげる環境を整えていきましょう。
6. 関連資料
会員限定コンテンツで
仕事を進めやすくするヒントが見つかる!
おすすめ動画
成長を促すアサインの仕方とフォローの仕組み
チームの仕組み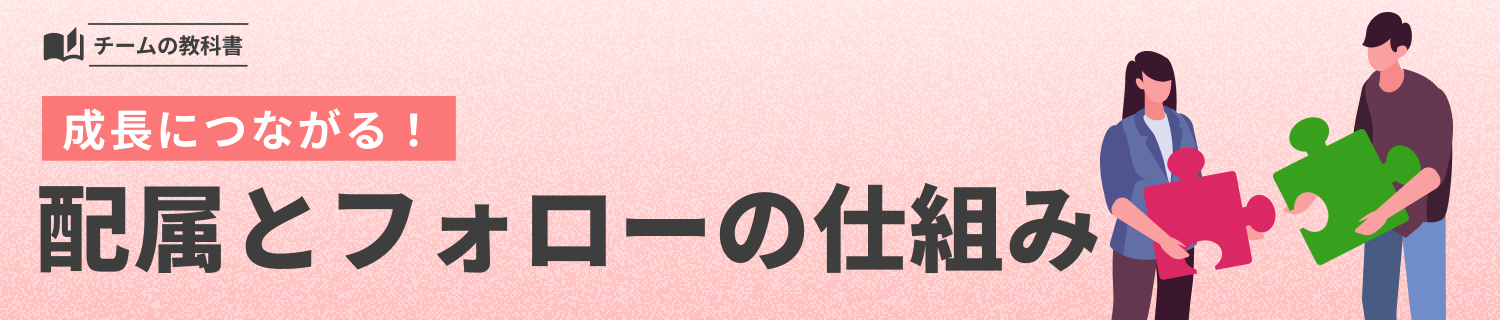
人材育成において、70%は「経験」からの学びが成長に影響すると言われています。
特に、メンバーがこれまで経験したことのない領域や、少し高いハードルに挑戦する
「チャレンジングなアサイン」は、成長を加速させる大きな機会です。
この機会を通じて、メンバーは新たなスキルや視点、自己効力感を獲得し、
その結果、チーム全体の価値向上にもつながります。
この記事では、チャレンジングなアサインの定義とその具体例を紹介した上で、
それを成功させるための「配属」と「フォロー」のポイント、さらにそれを支えるチーム体制設計について解説します。
1. チャレンジングなアサインとは?
チャレンジングなアサインとは、メンバーがこれまで経験したことのない領域や、
少し高いハードルに挑戦する機会を与えることです。
これにより、メンバーは新たなスキルや知識を獲得し、成長することができます。
例
- 初めての顧客対応やプレゼンテーション
- 新規プロジェクトの立ち上げやリーダー役
- 他部署との連携業務や外部との交渉
- 業務改善や仕組みづくりなど、抽象度の高い課題への取り組み
アサインの効果
チャレンジングな経験は、個人の成長を促すだけでなく、以下のような効果をもたらします。
- 自己効力感の向上:挑戦を達成することで、自信を得ることができる。
- チーム全体のパフォーマンス向上:個々の成長がチームの価値を底上げする。
- 新しい視点や能力の獲得:未経験領域への挑戦が、新しい視点を生み出す。
チャレンジングと無理の違い
「チャレンジング」であることが「無理をさせること」とイコールではありません。
適切な配属やフォローがなければ、メンバーが過剰なストレスを抱えたり、挫折してしまうリスクがあります。
チャレンジングなアサインを成功させるためには、「成長機会」と「心理的安全性」の両方を意識することが重要です。
2. アサインを行う際の配属のポイント
チャレンジングなアサインを成功させるためには、適切な配属が重要です。
メンバーの成長と業務成果を両立させるために、以下の要点を押さえることが必要です。
①ゴール着地のイメージを持つ
配属元が「完了状態」を明確に描けていない場合、アサインは失敗しやすくなります。
着地イメージがないままの配属は“無茶振り”となり、適切な人選やフォローが困難になります。
②志向性とのマッチング
メンバーの志向性とアサイン内容が一致しているかを確認しましょう。
完全一致でなくても、チャレンジによって得られる成長やスキルを具体的に伝えることで、
納得感を高めることができます。
志向性と異なる場合は、正直に理由を説明し、合意形成を図ることが大切です。
3. アサインを行う際、管理者のフォローポイント
未経験の業務やチャレンジングなアサインでは、メンバーが安心して取り組めるようなフォロー体制が欠かせません。
心理的安全性を保ちながら成果を最大化するために、以下のポイントを意識しましょう。
①丸投げしない
未経験領域では仮説の精度が粗く、軌道修正が頻発します。
心理的安全性を保つために、定期的な相談時間(例:15分/日、1時間/週)を事前に設定しましょう。
②細かいチェックをしすぎない
細部まで過干渉してしまうと「任せられたはずでは?」という不信感につながります。
管理者はP/L(損益計算書)や稼働管理表、タスク一覧などを活用し、状況を可視化することで、報告・相談の効率を高め、メンバーに任せられるようにしましょう。
③相談の基準を明確にする
チャレンジングな業務では、相談のタイミングが分かりづらくなります。
「30分考えても糸口が見えない場合は相談する」など、時間を基準にしたトリガーを設定することで、
メンバーに心理的負担を与えずにスピード感を保ちながら前進できます。
4. チーム体制の作り方
チャレンジングなアサインを行う場合、業務量の偏りや負担が大きくなると、チーム全体のパフォーマンスが低下しかねません。
これを防ぐために、以下のポイントを意識した体制設計を行いましょう。
①常に余力を持つ
業務量に対してギリギリの人員配置は、残業の常態化や改善余力の欠如を招きます。
業務改善・自己研鑽・緊急対応のバッファを含めた余力設計が重要です。
②マネジメント工数を確保する
管理者がプレイングに偏ると、メンバーの育成や状況把握が疎かになります。
一時的な対応であっても、根本的な体制見直しの計画をステークホルダーと共有しておきましょう。
③チーム内の協力体制をつくる
効果的な協力体制を築くためには、メンバー同士が状況を共有しやすい環境を整えることが大切です。
共有された情報を活用し、チーム全体で支援し合える仕組みを作ることで、相乗効果を最大化することが可能です。
- メンバーのミッション・進捗・工数負荷・困りごとを共有する
- 状況が分かれば、自然とフォローし合える関係が生まれる
- チームは単なる労働力の総和ではなく、相乗効果を生む場である
|
|
5. まとめ
チャレンジングなアサインは、メンバーの成長とチームの価値向上に直結します。
その成功には、配属の設計、フォローの仕組み、そして無理なく支える体制づくりが不可欠です。
チーム全体で支え合いながら、挑戦を成長につなげる環境を整えていきましょう。
6. 関連資料
会員限定コンテンツで
仕事を進めやすくするヒントが見つかる!