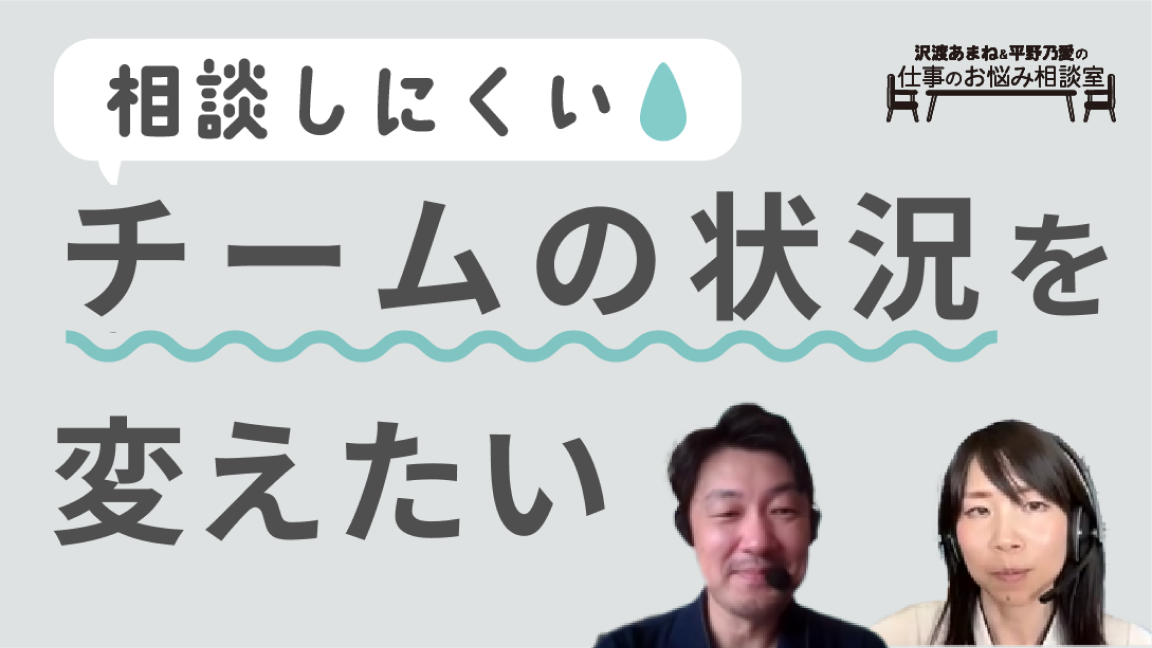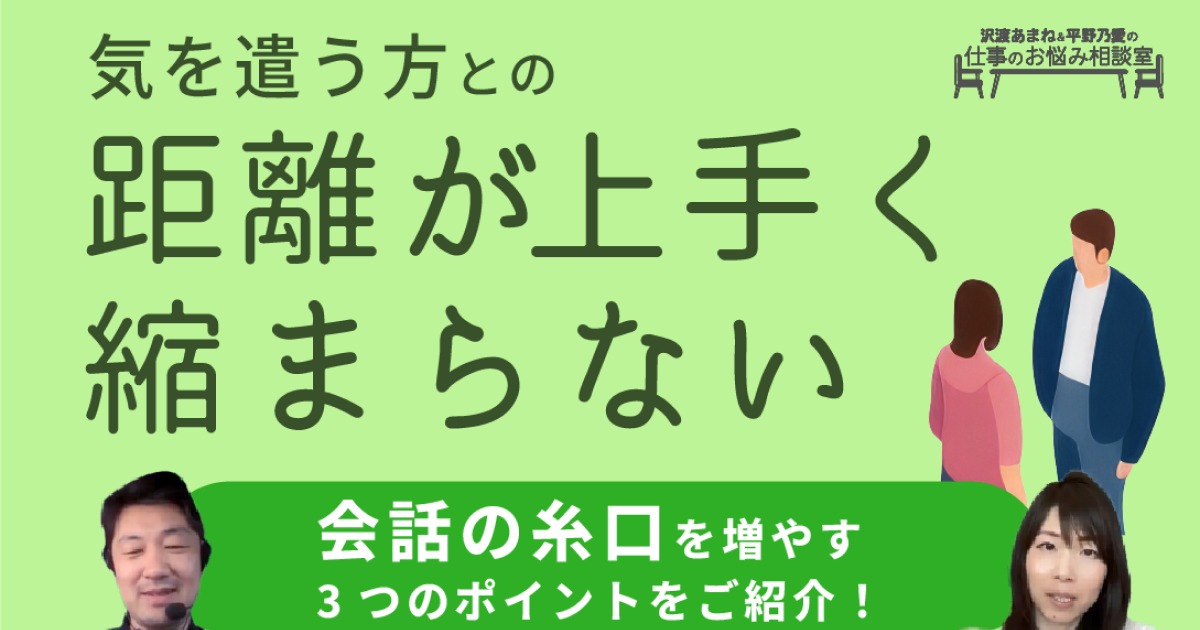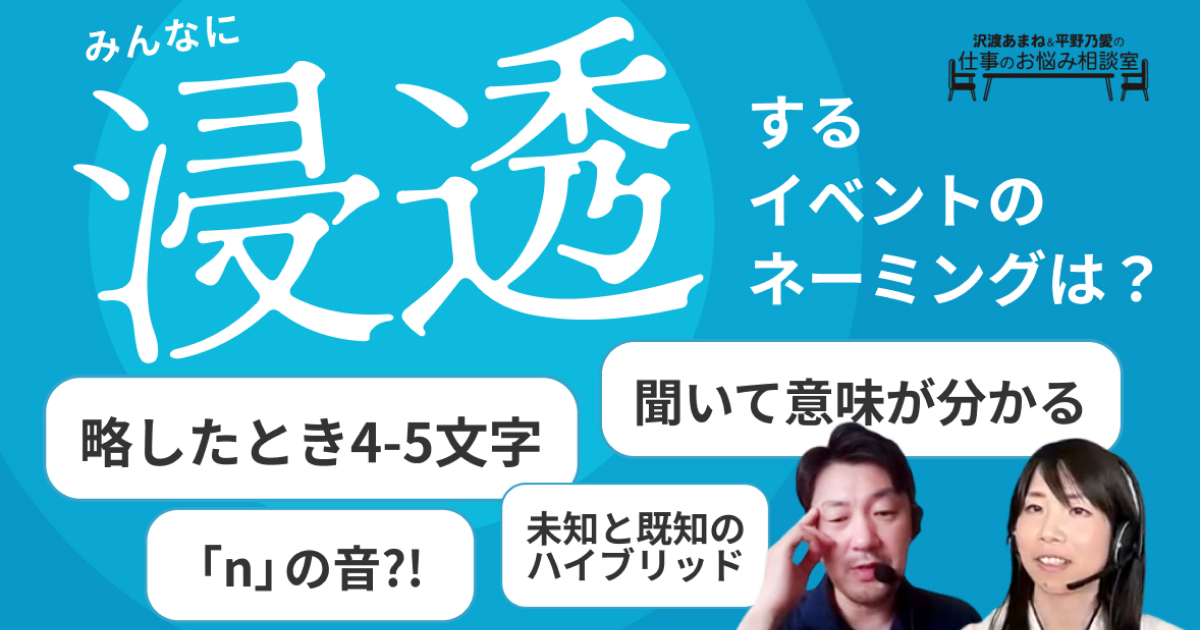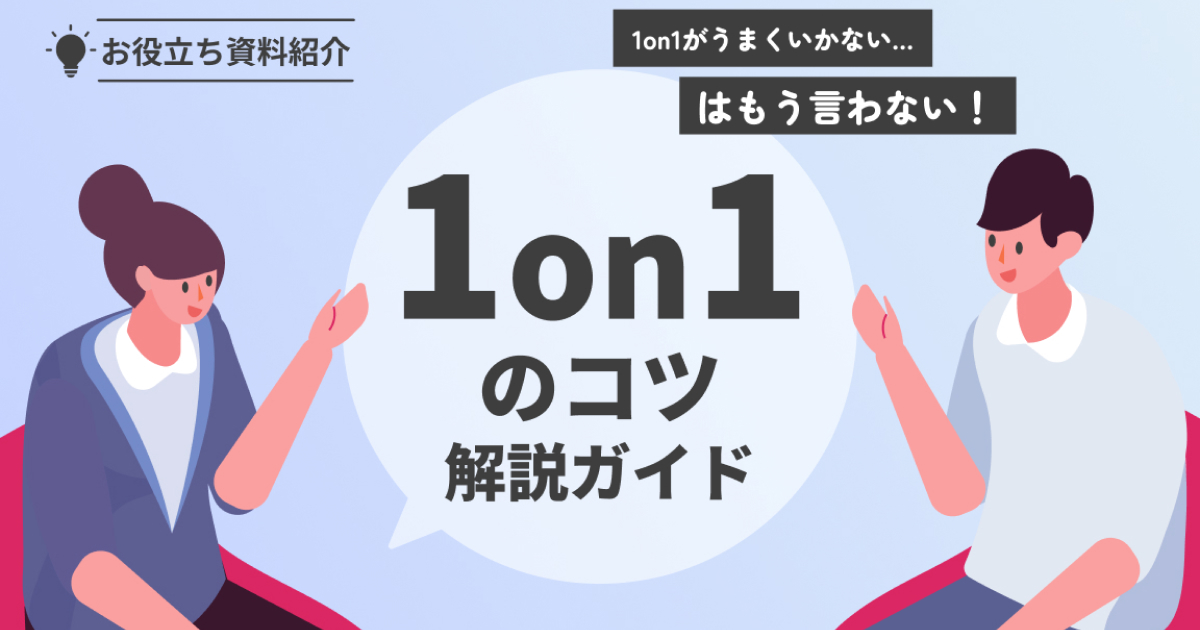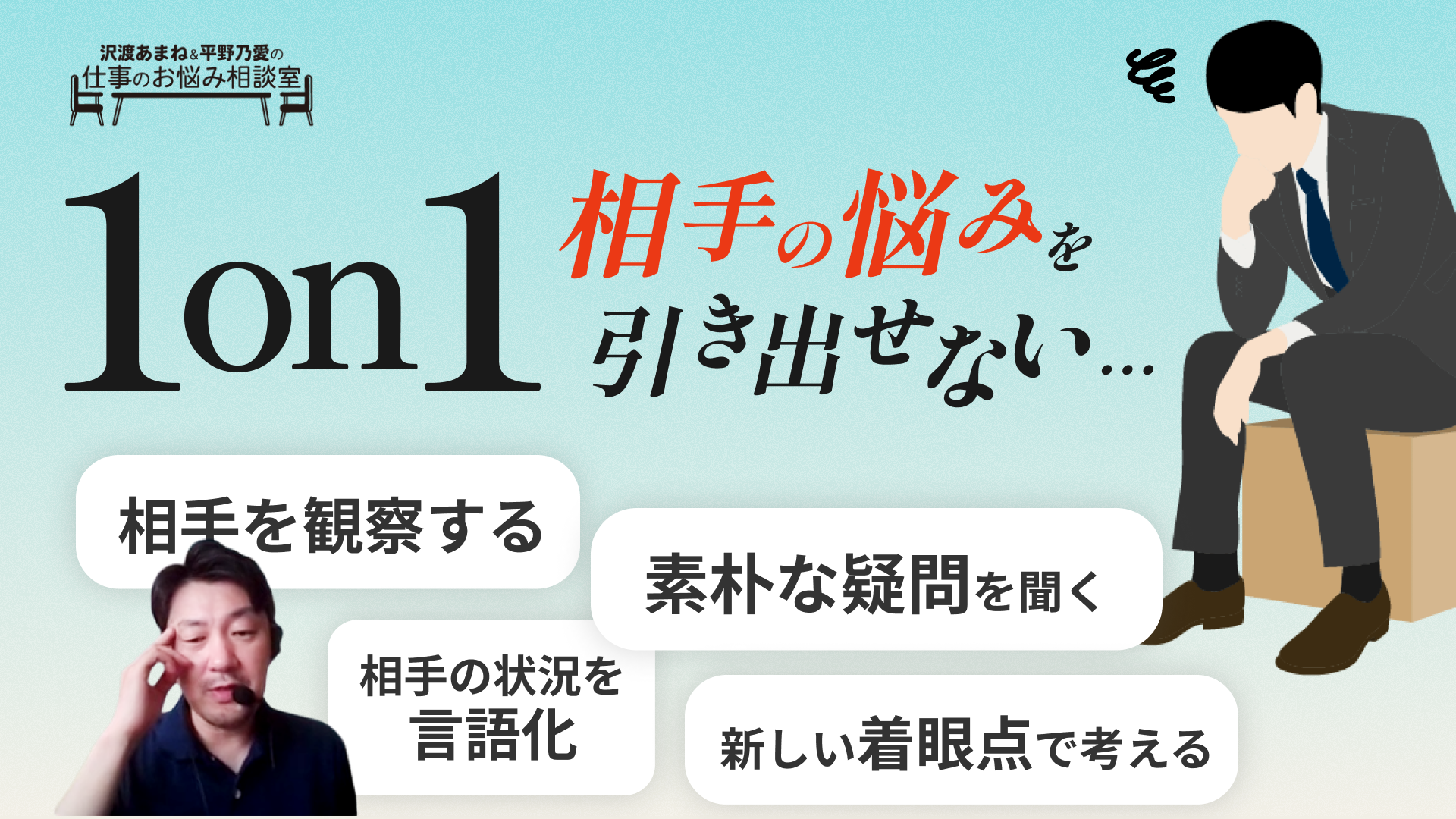関係者と認識ズレを防ぐ方法
コミュニケーション
1. 認識ズレが起きる理由
仕事をする中で、様々な方と関わると認識ズレが発生してしまうことは日常茶飯事かと思います。
みなさんご存じのことかと思いますが、関係者間での認識ズレを防ぐことで仕事は進めやすくなります。
ここでは、どんなことを意識すると認識ズレが起きないのか考えてみましょう。
以下の3点を前提に考えておくと、認識ズレを防ぎやすくなります。
職位階層によって視点は異なる
立場の違いにより視点は異なるため、同じ事象を対応していても重要だと思うポイントが異なります。
そのため、普段やりとりしている関係者と、意思決定する関係者とが異なる場合は、
意思決定する関係者の意向や考えを押さえに行く必要があります。
しかし、やりとりしている方が担当者であるのに、急に部長に連絡を取るなどの階層を飛ばしたコミュニケーションは相手の方にとって心象が良くないことが多くあるため、
意思決定する関係者と連携を取る場合は、意識的に注意して接点を持つようにしましょう。
相手が必ずしも本音を言っているとは限らない
様々な理由から、会議などの場で全員が本音を言っているわけではないかもしれません。
また、会議で発言をしていないから(反対意見を言わなかったから)といって、意見に賛成しているとは限りません。
そのため、会議などオフィシャルな場での発言内容だけでなく、必要であれば別の場で「実際のところ…」と確認をすることや、会議の場でもあえて「◎◎さん、いかがですか」と振ってみるなど、考えを引き出す工夫をしましょう。
みんなが同じ考えとは思わない、一人の意見を鵜呑みにしない
ミーティングなどでは発言者の視点や利害に基づいて意見を言う場合も多いため、会議で発言されることだけが正しいとは限りません。
できるだけ耳にした一次情報について、他の人などにも確認するようにしましょう。
全ての一次情報を確認することは現実的に不可能だとしても、「もしかしたら違うかも…」という視点を持っておくことが大切です。
また、外から見ると部門内で認識が統一されているものと思い込みがちですが、
実際には、部門内は必ずしも一枚岩とは限らないもので、部内でも情報が共有されていないことが多々あります。
誰か特定の人物が発言したことが、その部門全体の共通見解とは思わないように、できるだけ関係者全体の意見を把握を意識しましょう。
2. 認識ズレを防ぐには
ここからはどんなことを意識すると認識ズレが起きにくいのかをお伝えします。
小さな変化を察知し、背景を理解する
関係者の変化の背景にはニーズの変化など重要な事柄が含まれる可能性があるため、
より早くキャッチアップすることでチームの仕事をより良い方向に軌道修正することができます。
ニーズの変化を察知するポイントは
以下のような違和感を察知した場合、ニーズに変化が出ている可能性があります
- 定例会の参加率が減ったり、メールの返信がなかなか来なくなるなど、忙しそうな様子
- 急に具体的な指示が出るようになった、発言の内容が以前と変わるなど
相手の違和感を察知した場合は、いきなりずけずけと聞かず、
定期的なコミュニケーションの中で「自分はこう感じているが、合っているか?」と確認し、
合っていればその理由を確認しましょう。
信頼関係を築く
認識ズレを防ぐコミュニケーションの第一歩は能動的に相手に投げかけることです。
例え少しずつであっても相手の期待していること以上の成果を出し、スピーディーに応えることを続けると
徐々にこちらを信頼してもらえ、より重要な依頼や本音を開示してくれるようになります。
3. 関連資料
【📝記事】関係者の洗い出しとキーパーソン特定のコツ はこちら
会員限定コンテンツで
仕事を進めやすくするヒントが見つかる!
おすすめ動画
関係者と認識ズレを防ぐ方法
コミュニケーション
1. 認識ズレが起きる理由
仕事をする中で、様々な方と関わると認識ズレが発生してしまうことは日常茶飯事かと思います。
みなさんご存じのことかと思いますが、関係者間での認識ズレを防ぐことで仕事は進めやすくなります。
ここでは、どんなことを意識すると認識ズレが起きないのか考えてみましょう。
以下の3点を前提に考えておくと、認識ズレを防ぎやすくなります。
職位階層によって視点は異なる
立場の違いにより視点は異なるため、同じ事象を対応していても重要だと思うポイントが異なります。
そのため、普段やりとりしている関係者と、意思決定する関係者とが異なる場合は、
意思決定する関係者の意向や考えを押さえに行く必要があります。
しかし、やりとりしている方が担当者であるのに、急に部長に連絡を取るなどの階層を飛ばしたコミュニケーションは相手の方にとって心象が良くないことが多くあるため、
意思決定する関係者と連携を取る場合は、意識的に注意して接点を持つようにしましょう。
相手が必ずしも本音を言っているとは限らない
様々な理由から、会議などの場で全員が本音を言っているわけではないかもしれません。
また、会議で発言をしていないから(反対意見を言わなかったから)といって、意見に賛成しているとは限りません。
そのため、会議などオフィシャルな場での発言内容だけでなく、必要であれば別の場で「実際のところ…」と確認をすることや、会議の場でもあえて「◎◎さん、いかがですか」と振ってみるなど、考えを引き出す工夫をしましょう。
みんなが同じ考えとは思わない、一人の意見を鵜呑みにしない
ミーティングなどでは発言者の視点や利害に基づいて意見を言う場合も多いため、会議で発言されることだけが正しいとは限りません。
できるだけ耳にした一次情報について、他の人などにも確認するようにしましょう。
全ての一次情報を確認することは現実的に不可能だとしても、「もしかしたら違うかも…」という視点を持っておくことが大切です。
また、外から見ると部門内で認識が統一されているものと思い込みがちですが、
実際には、部門内は必ずしも一枚岩とは限らないもので、部内でも情報が共有されていないことが多々あります。
誰か特定の人物が発言したことが、その部門全体の共通見解とは思わないように、できるだけ関係者全体の意見を把握を意識しましょう。
2. 認識ズレを防ぐには
ここからはどんなことを意識すると認識ズレが起きにくいのかをお伝えします。
小さな変化を察知し、背景を理解する
関係者の変化の背景にはニーズの変化など重要な事柄が含まれる可能性があるため、
より早くキャッチアップすることでチームの仕事をより良い方向に軌道修正することができます。
ニーズの変化を察知するポイントは
以下のような違和感を察知した場合、ニーズに変化が出ている可能性があります
- 定例会の参加率が減ったり、メールの返信がなかなか来なくなるなど、忙しそうな様子
- 急に具体的な指示が出るようになった、発言の内容が以前と変わるなど
相手の違和感を察知した場合は、いきなりずけずけと聞かず、
定期的なコミュニケーションの中で「自分はこう感じているが、合っているか?」と確認し、
合っていればその理由を確認しましょう。
信頼関係を築く
認識ズレを防ぐコミュニケーションの第一歩は能動的に相手に投げかけることです。
例え少しずつであっても相手の期待していること以上の成果を出し、スピーディーに応えることを続けると
徐々にこちらを信頼してもらえ、より重要な依頼や本音を開示してくれるようになります。
3. 関連資料
【📝記事】関係者の洗い出しとキーパーソン特定のコツ はこちら
会員限定コンテンツで
仕事を進めやすくするヒントが見つかる!


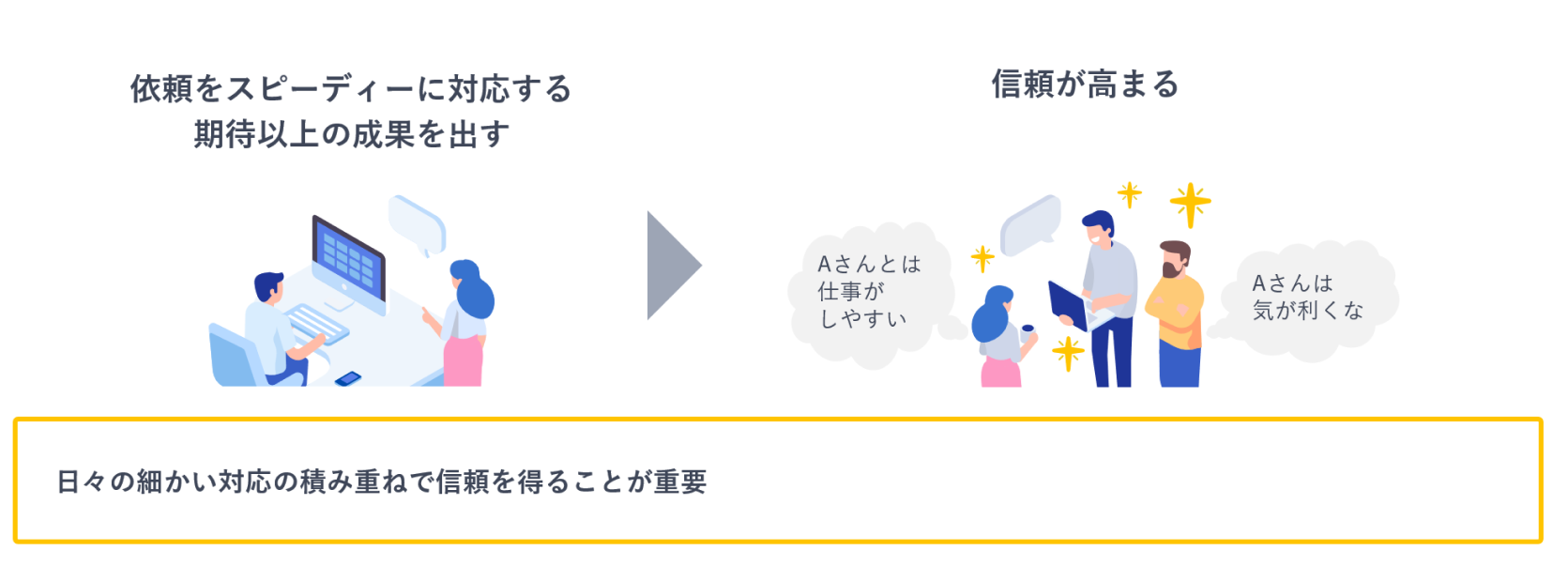


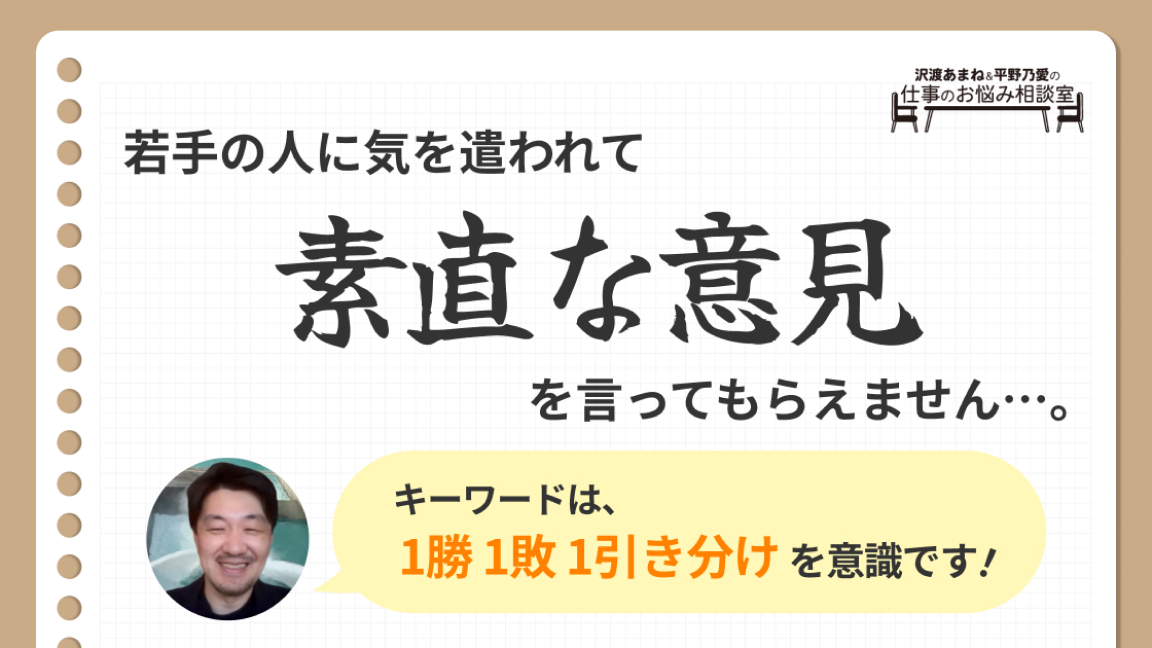
.jpg)
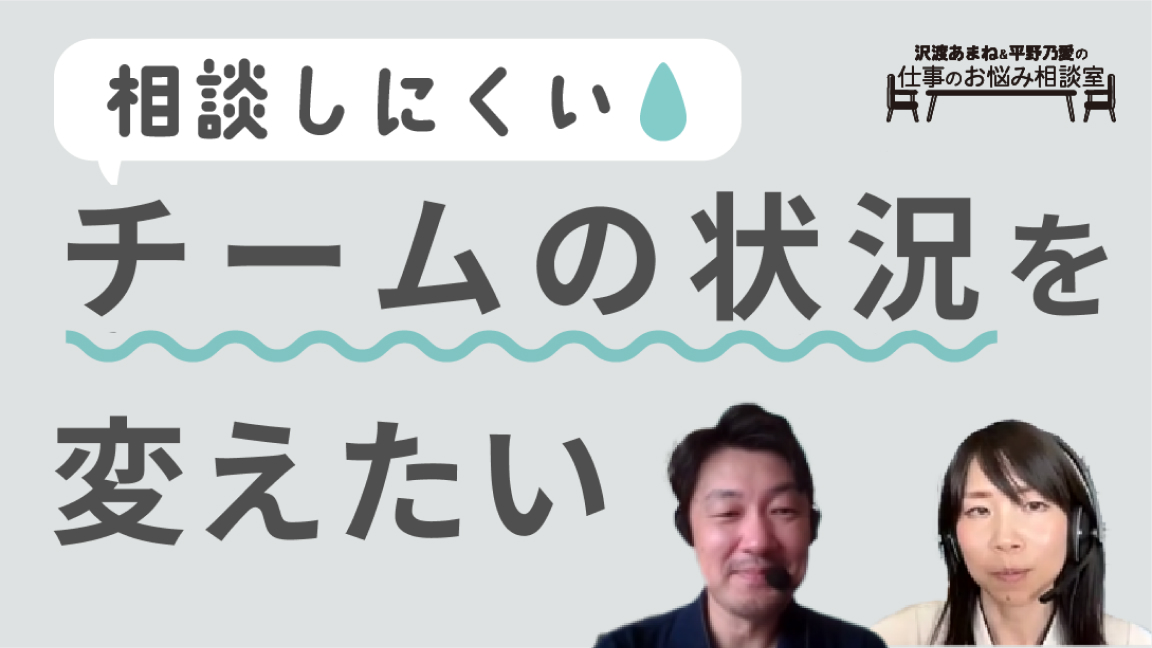
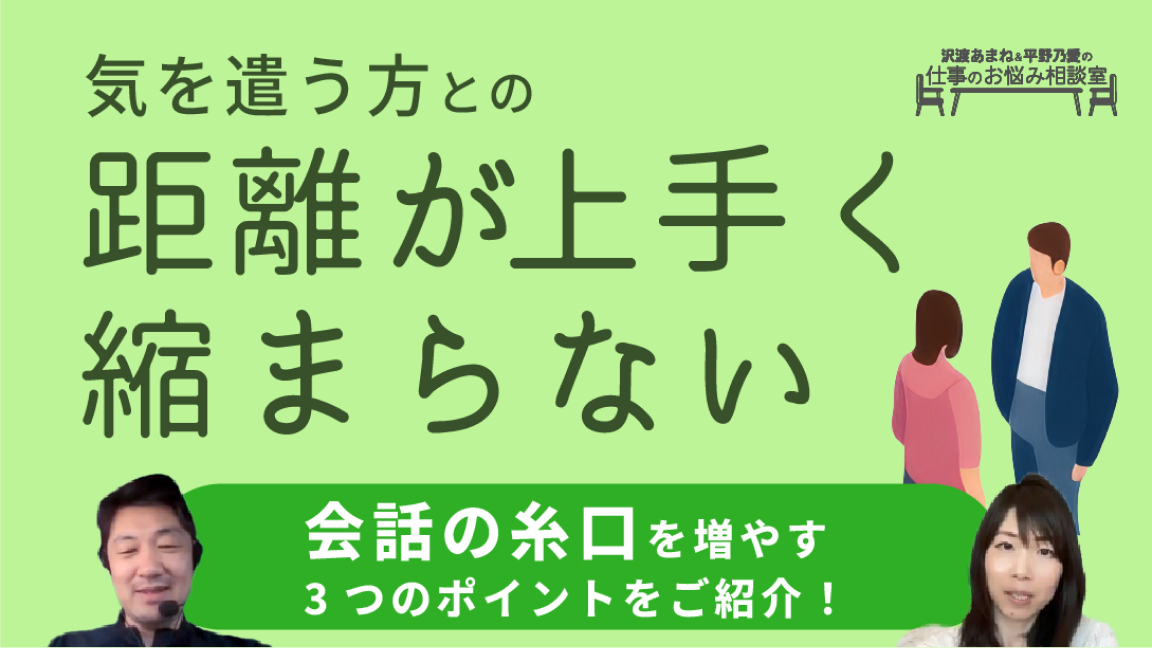
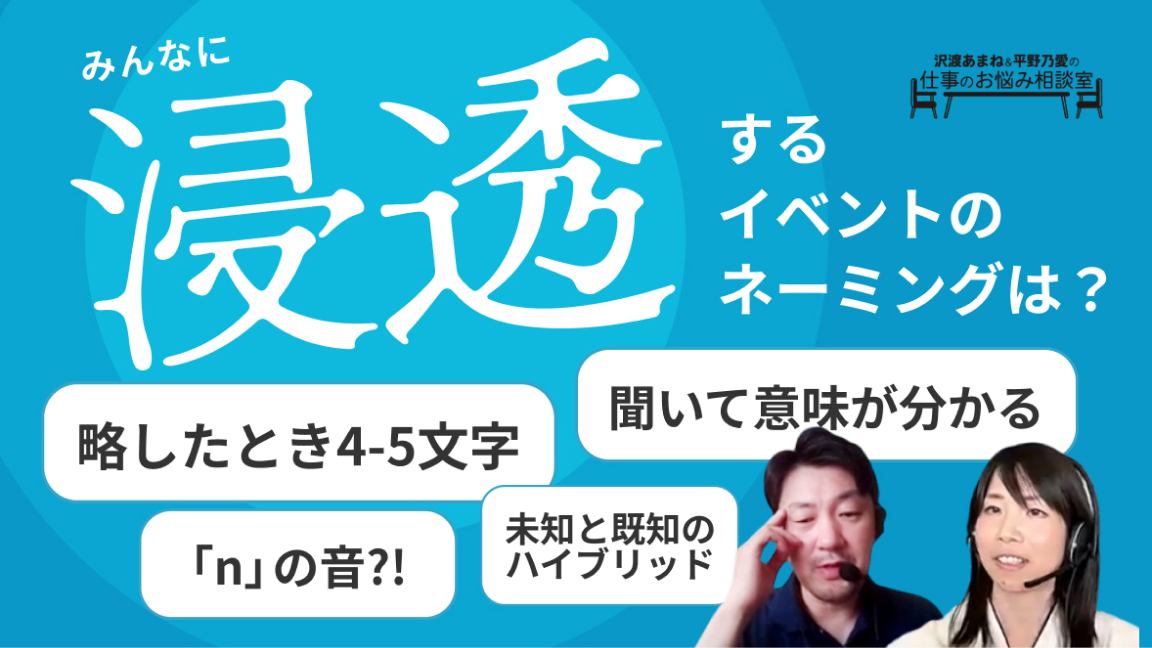
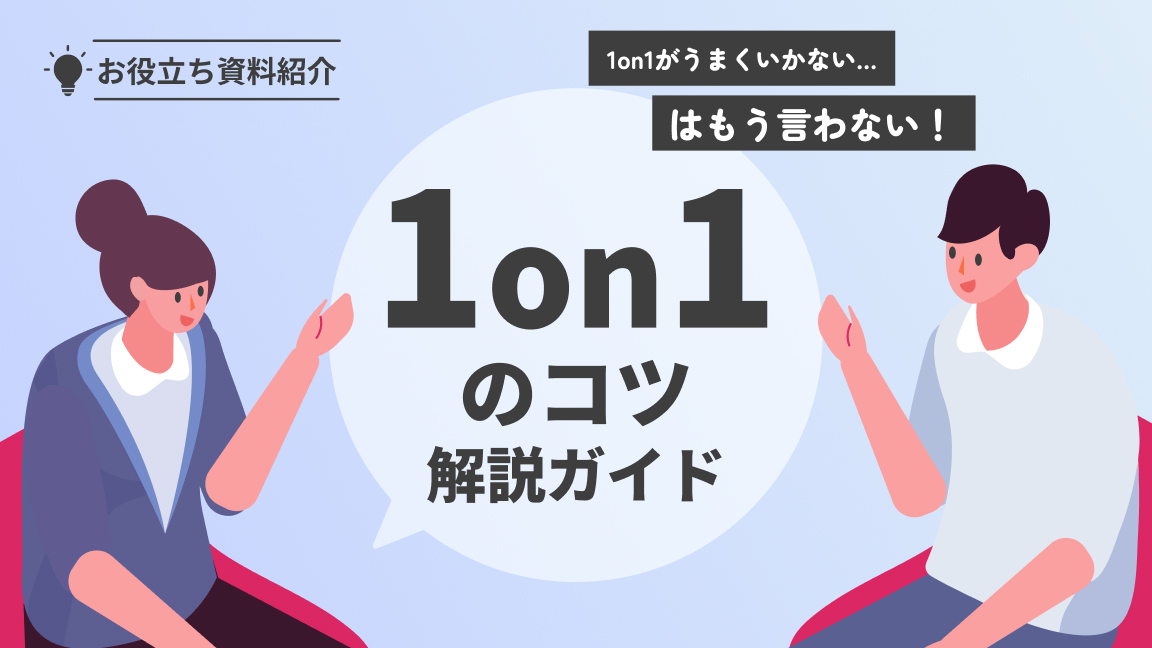
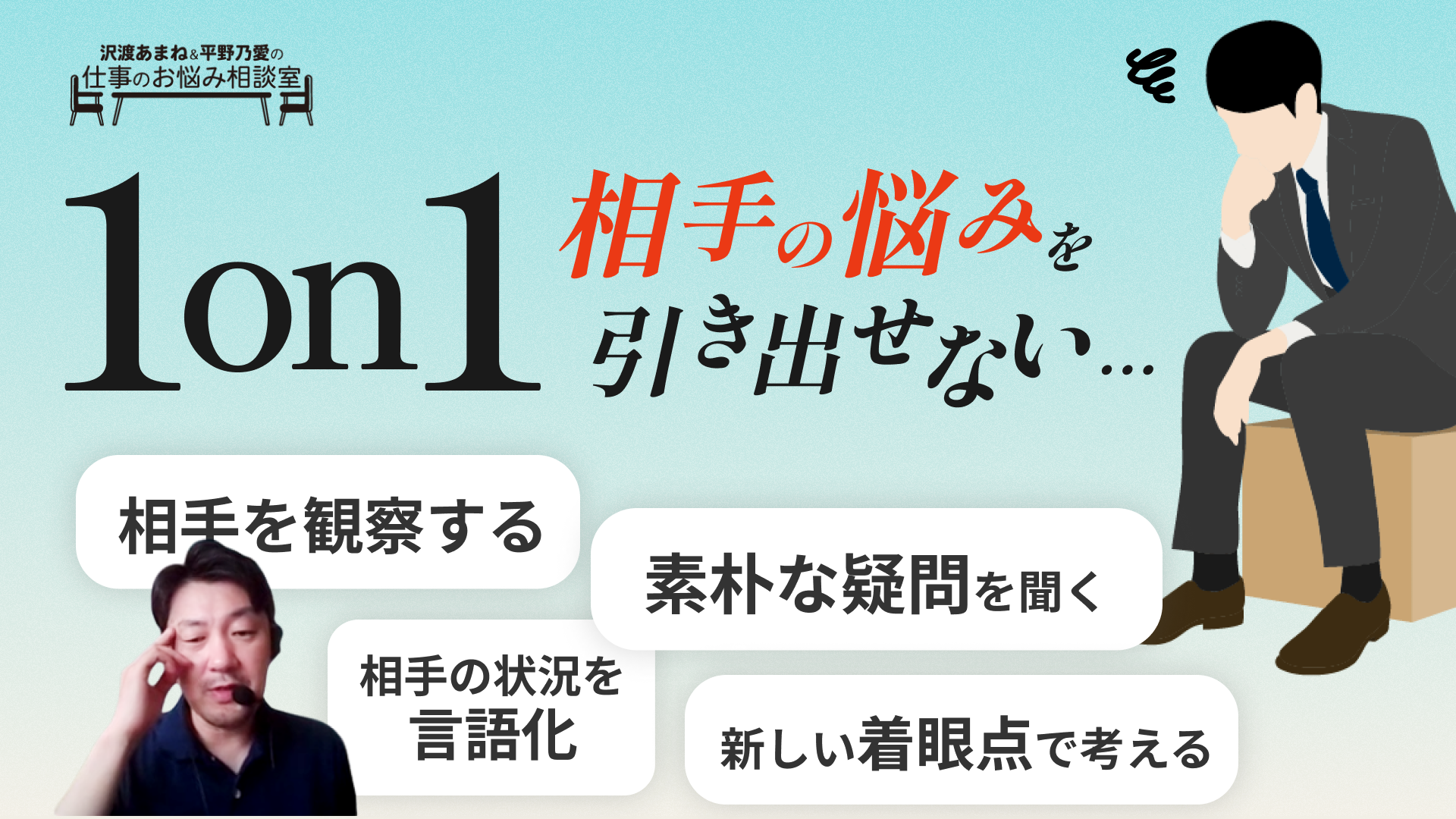
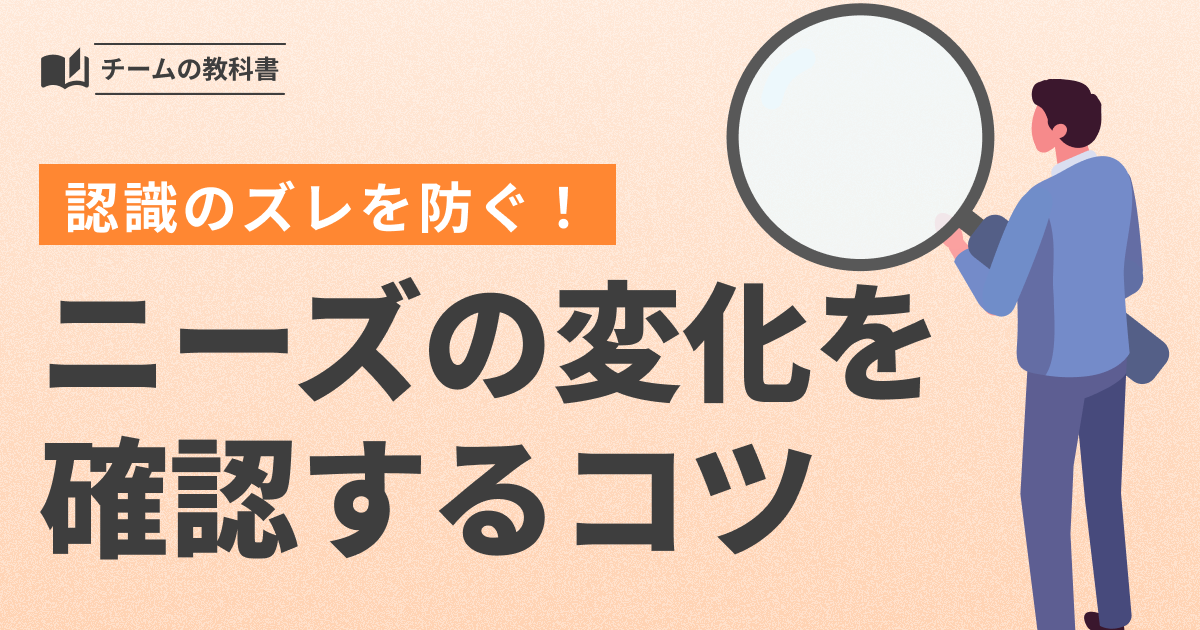
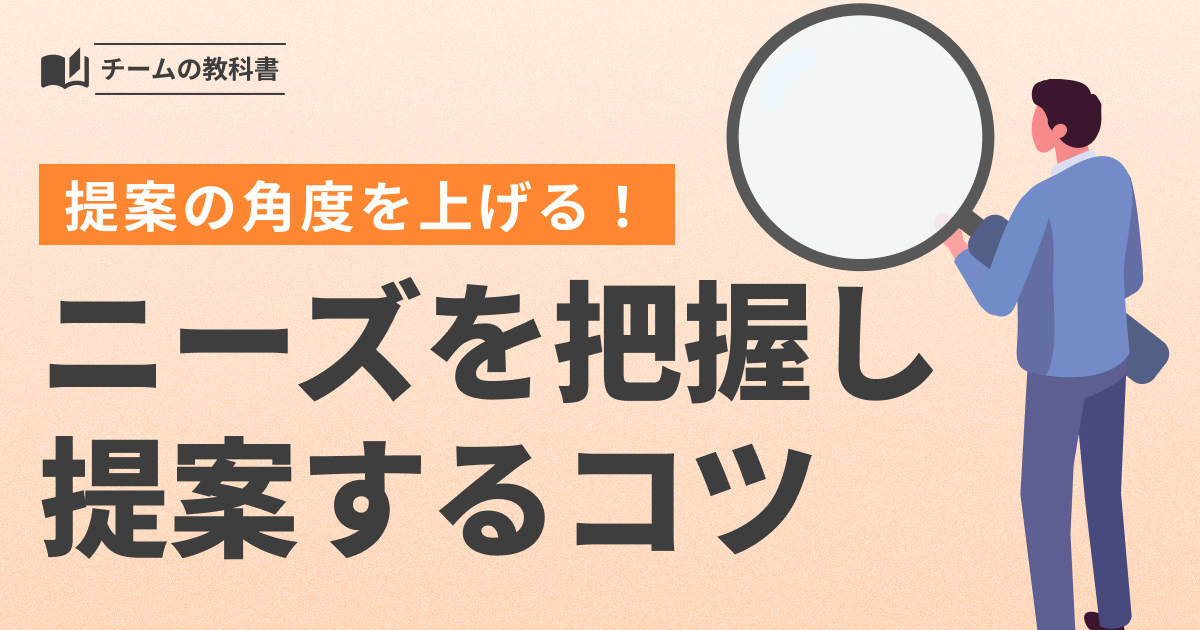

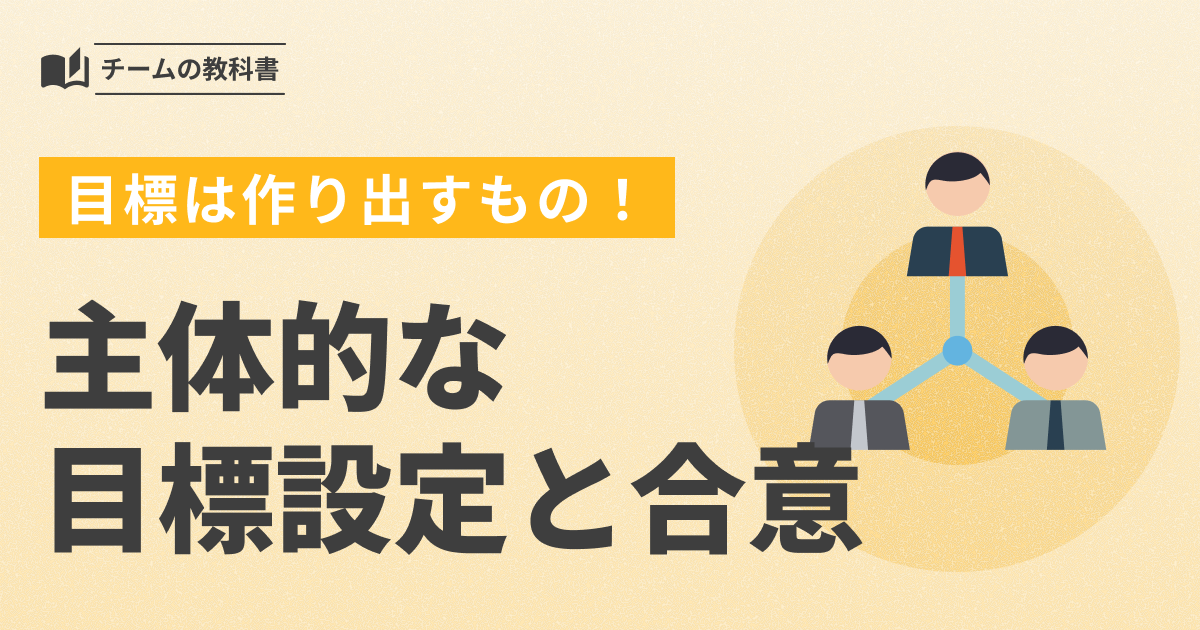
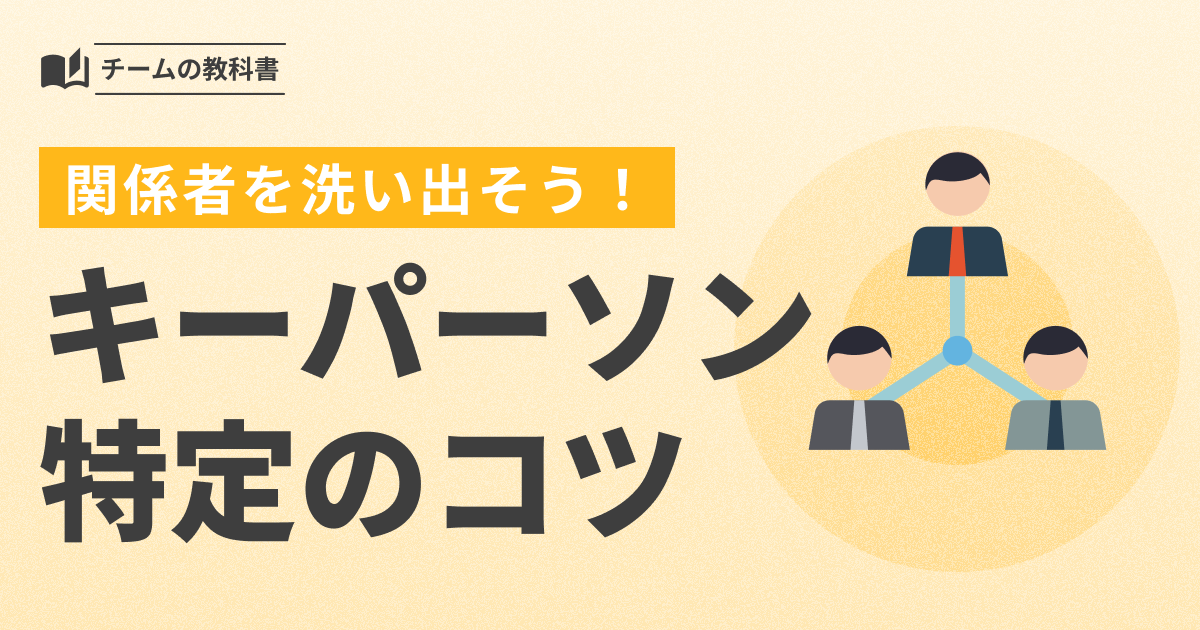
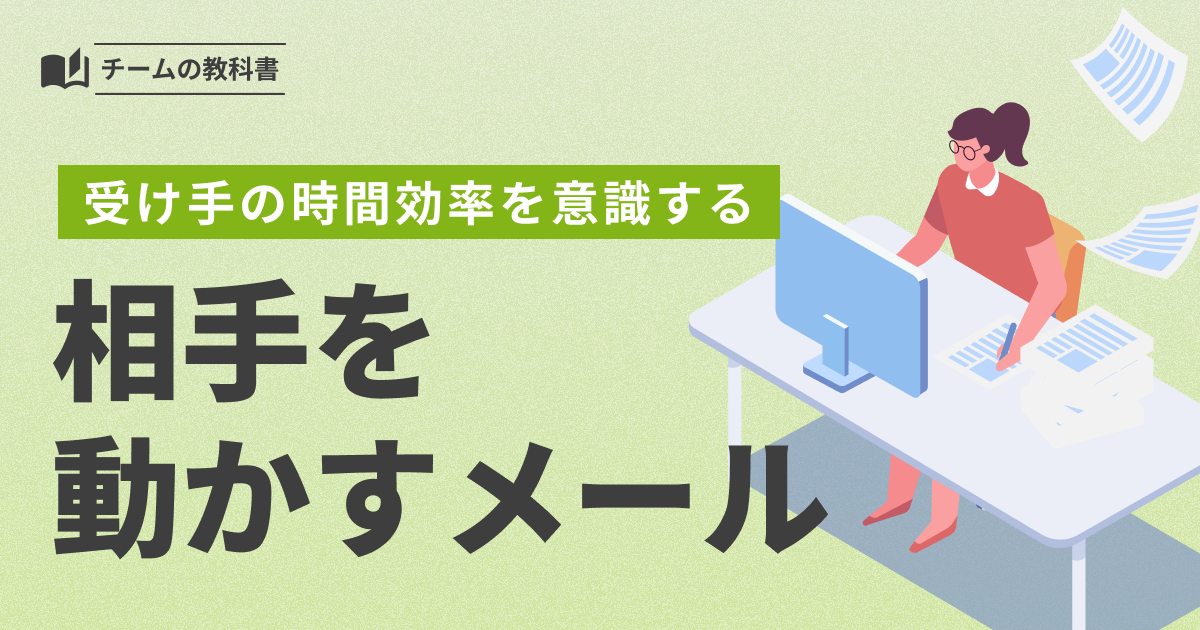




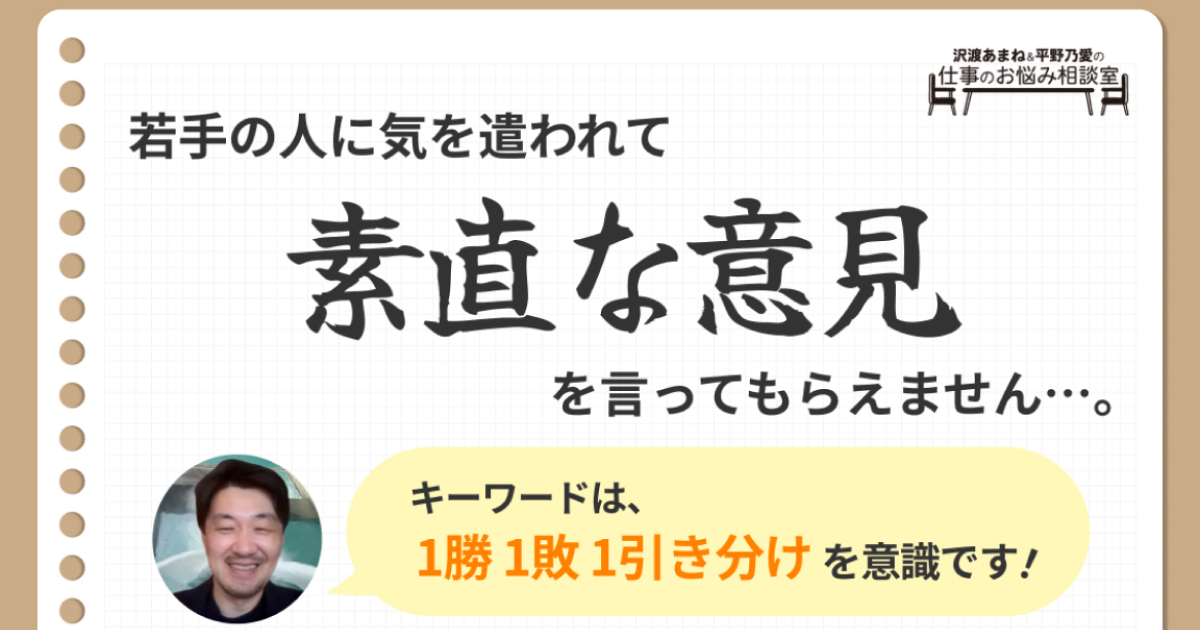
.jpg)