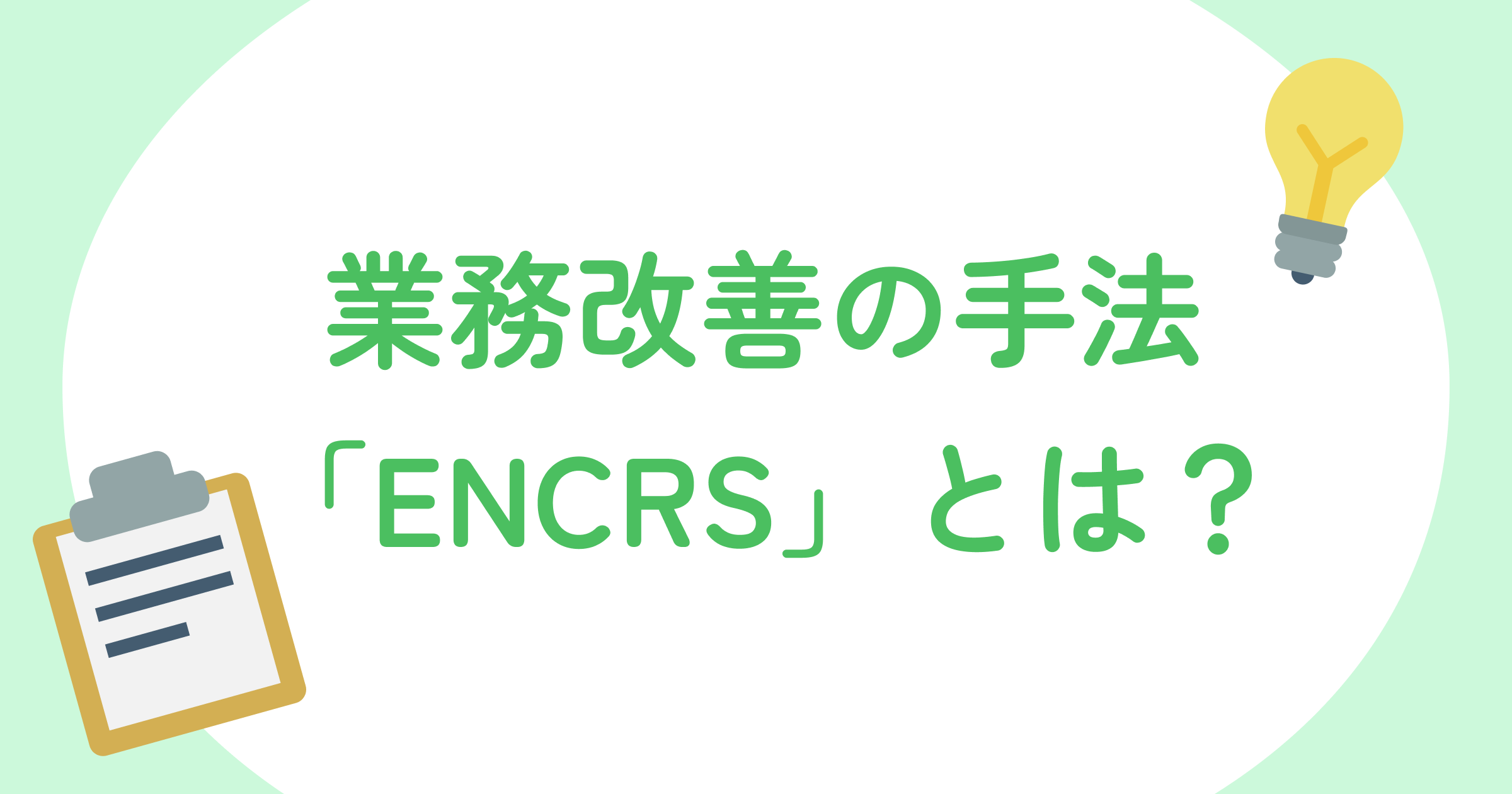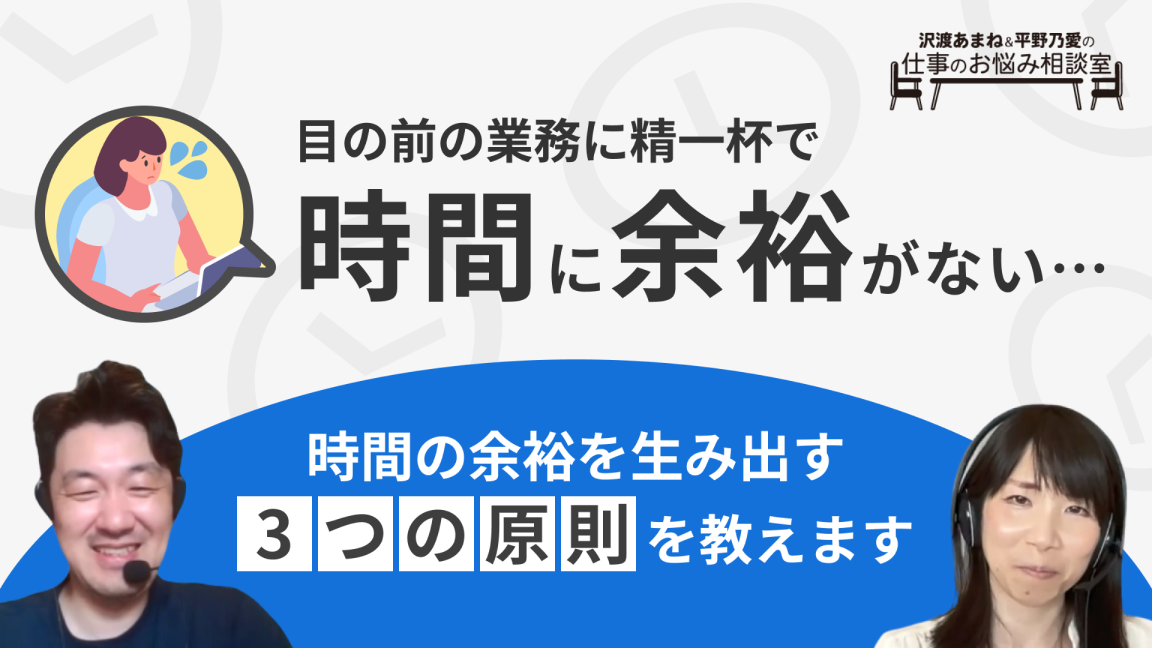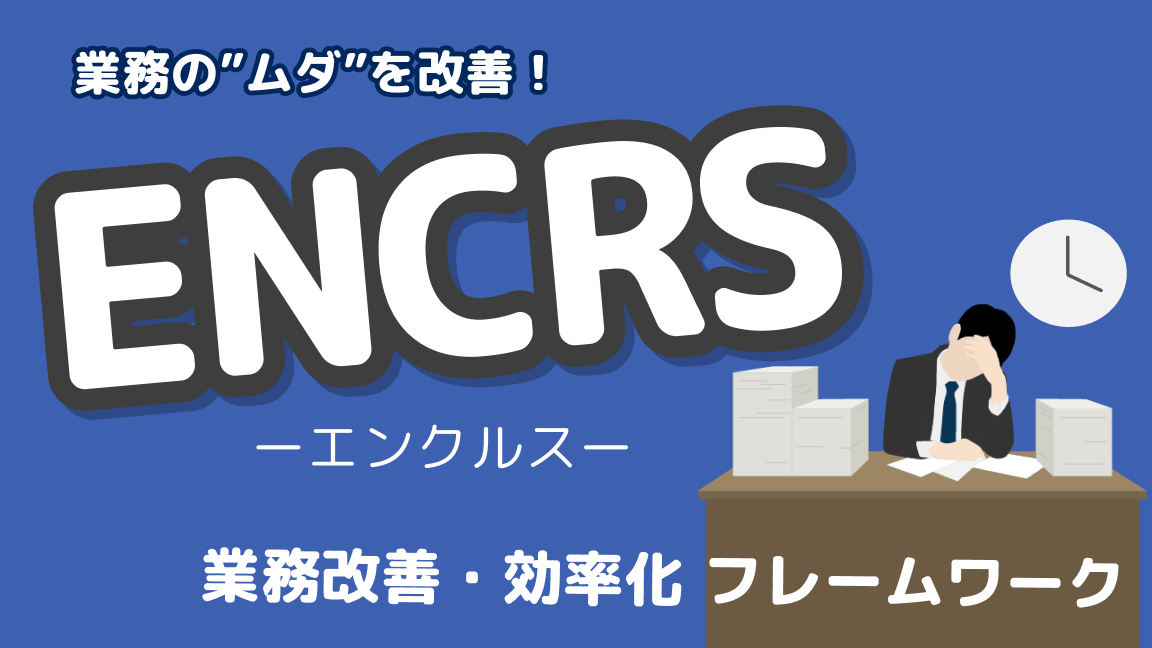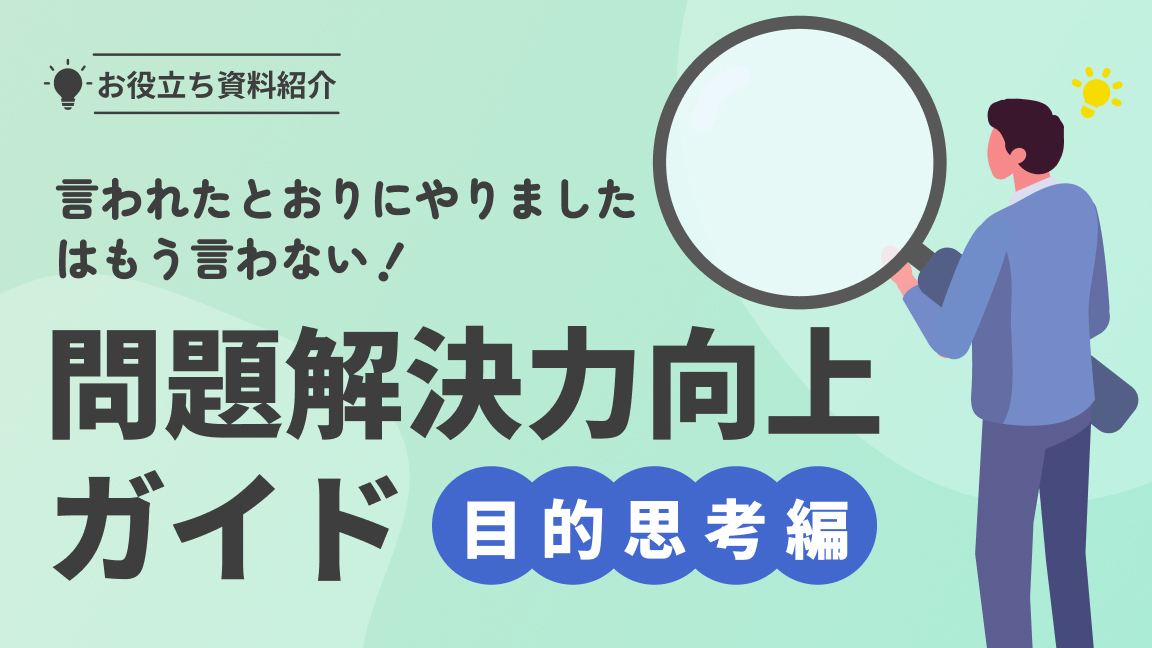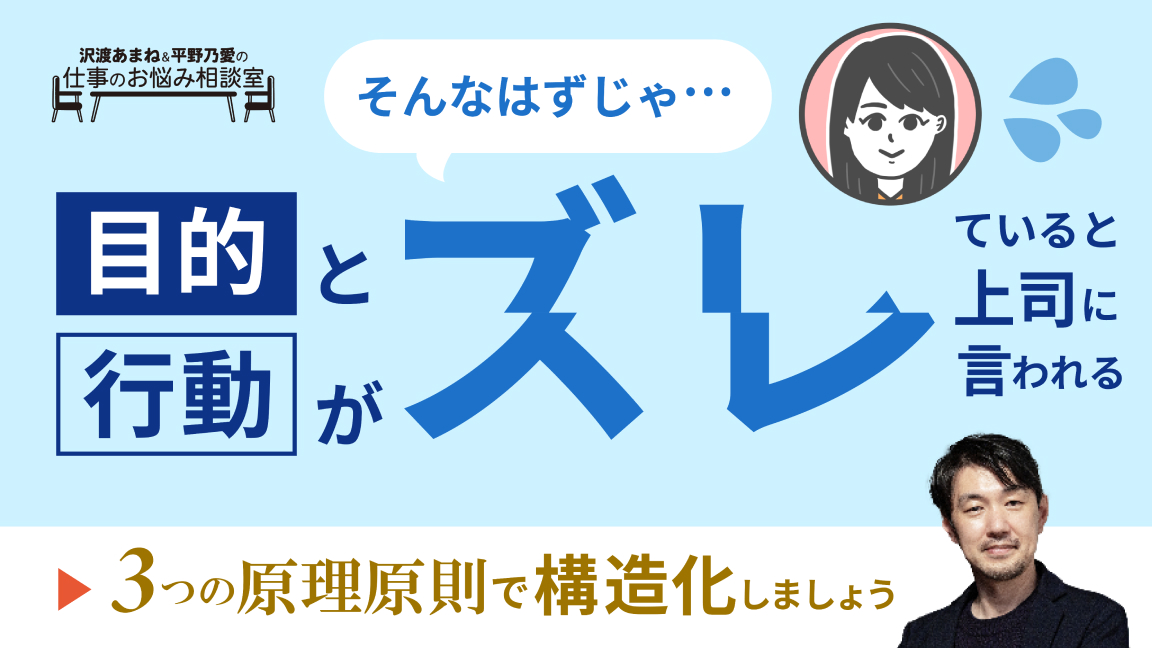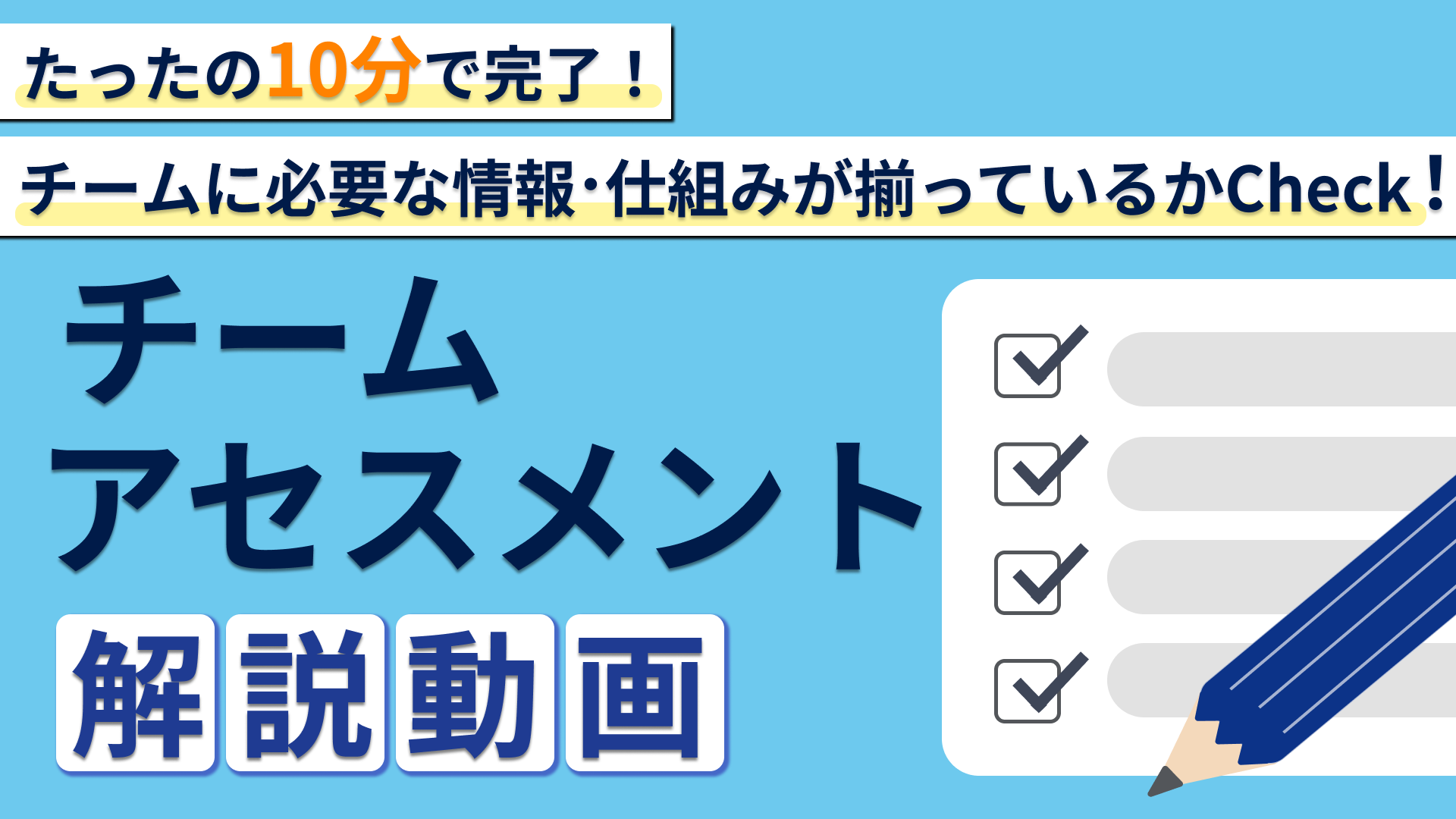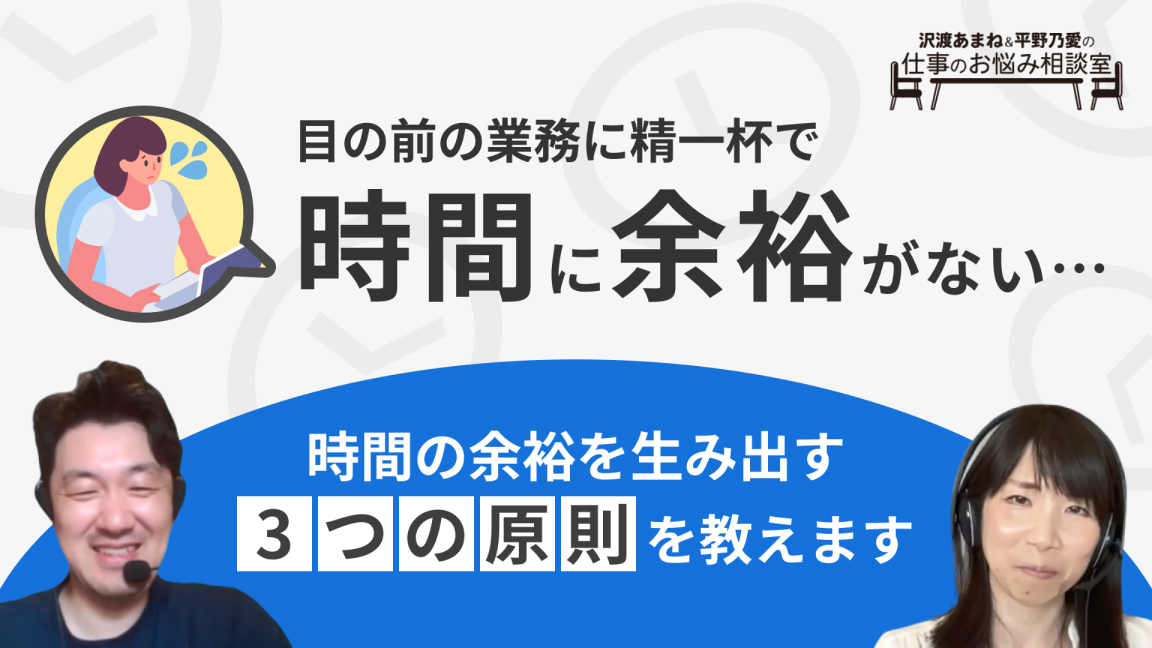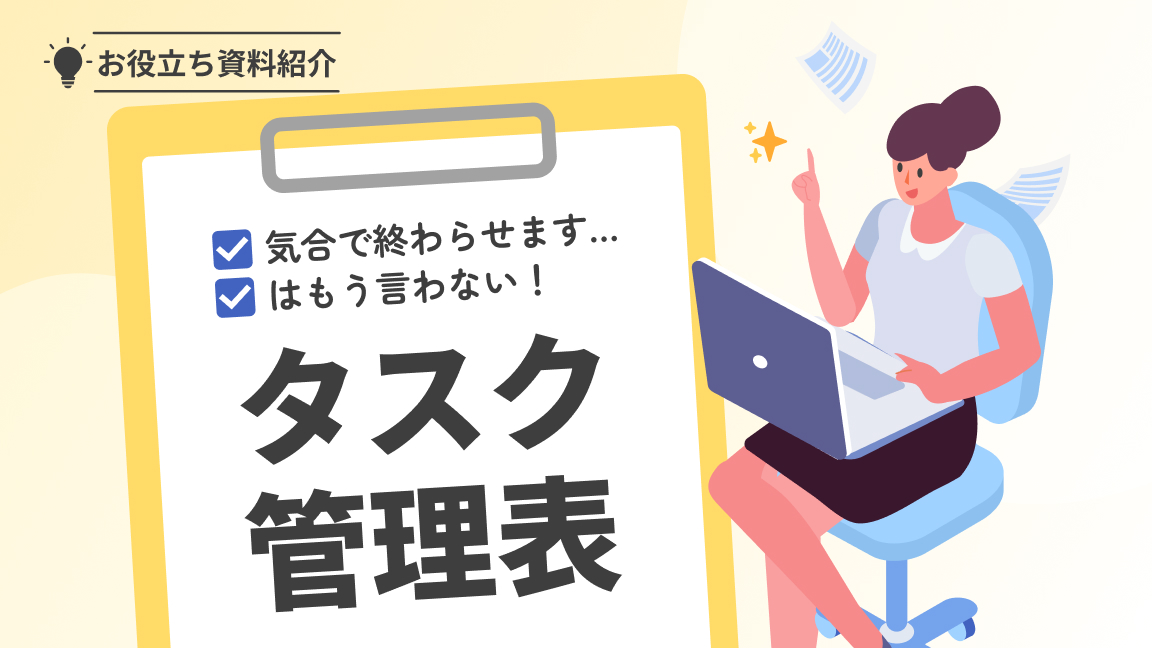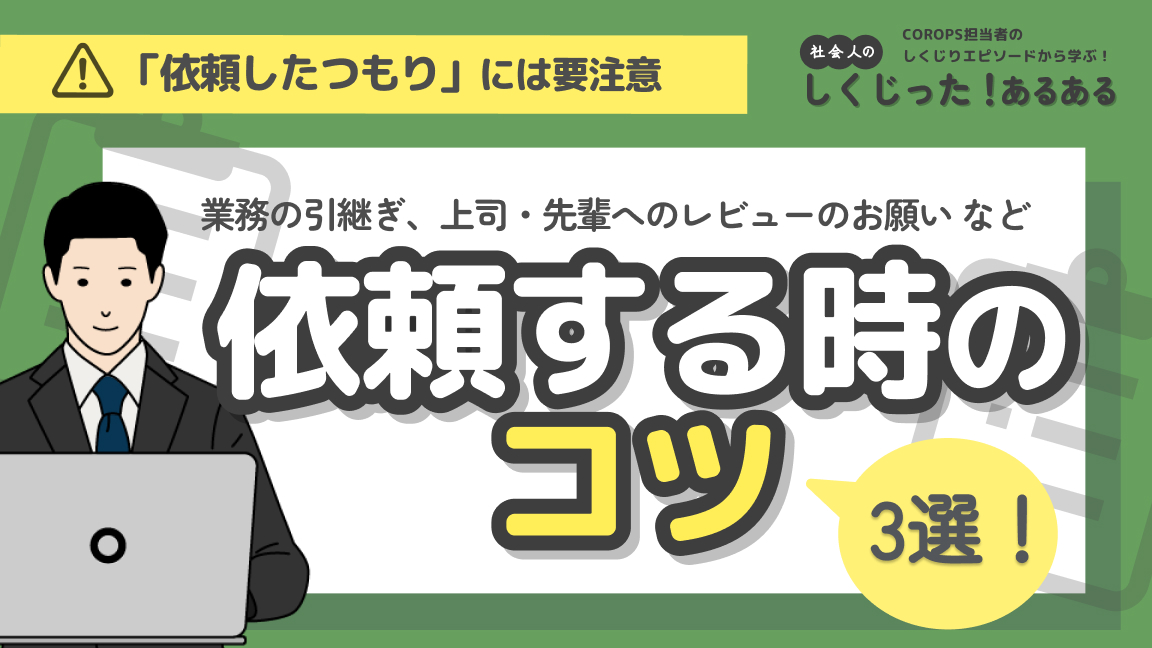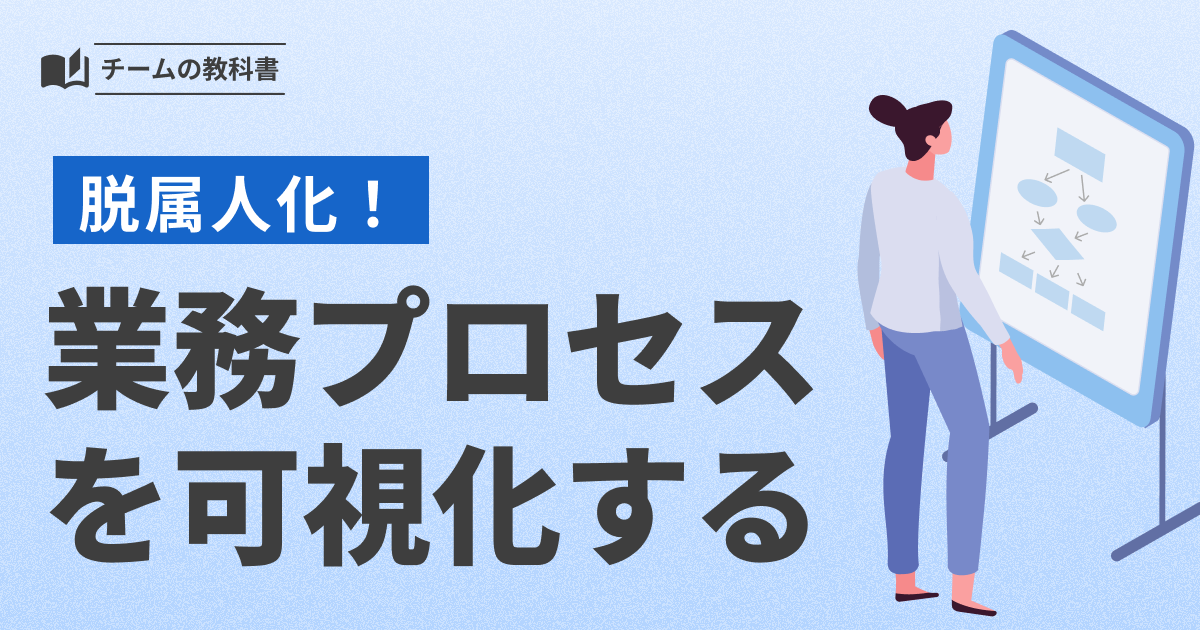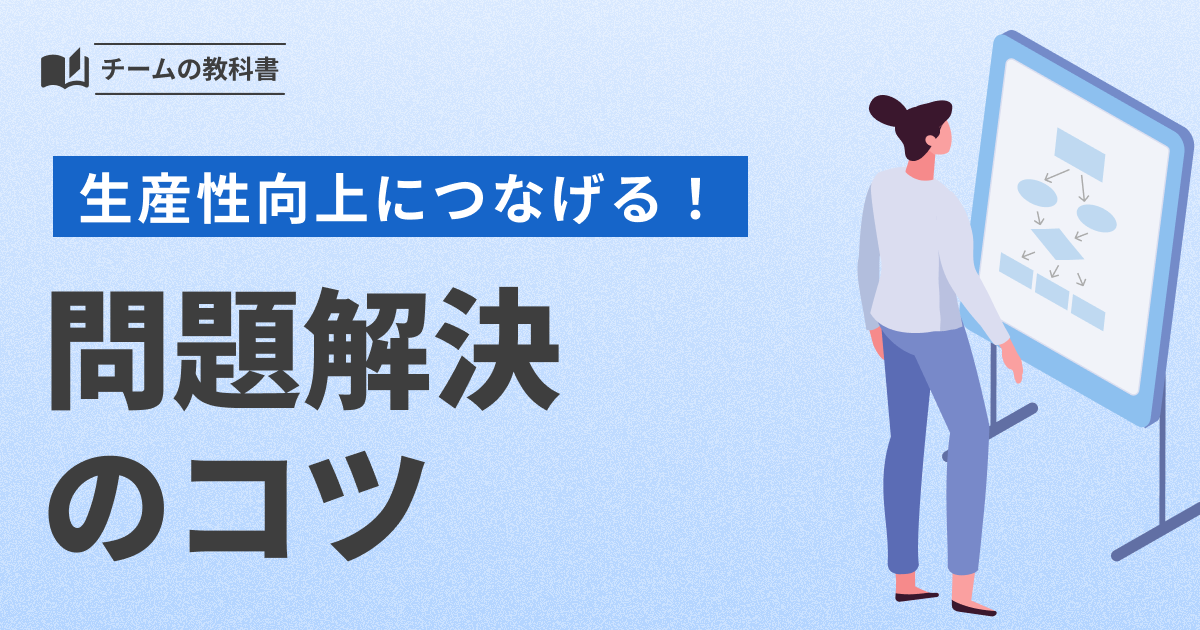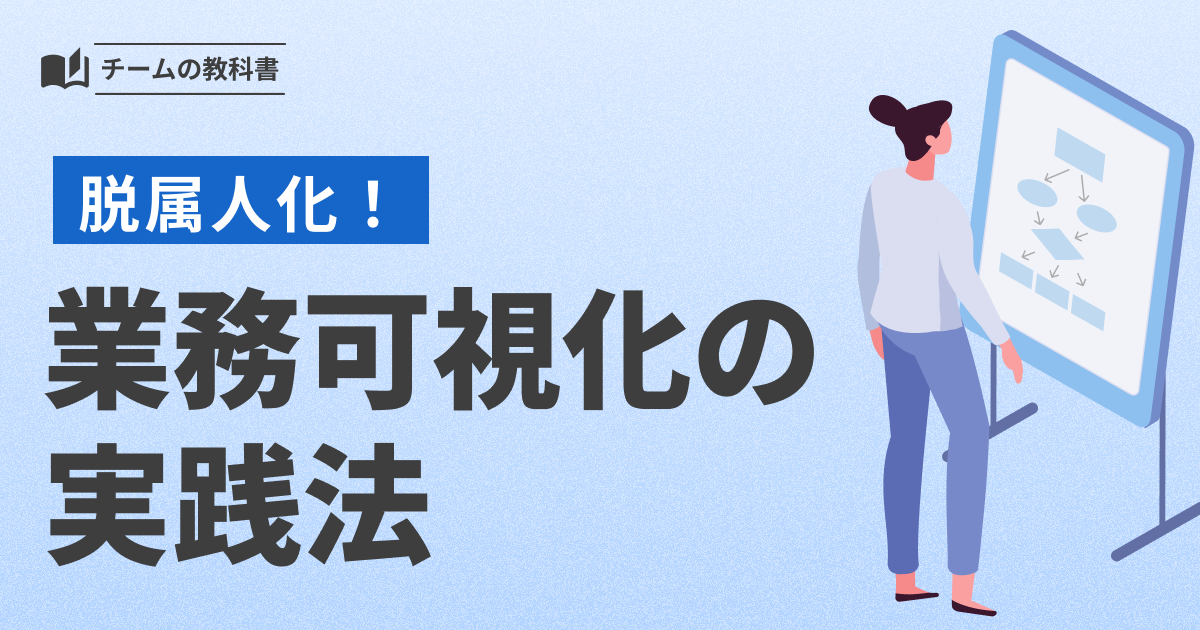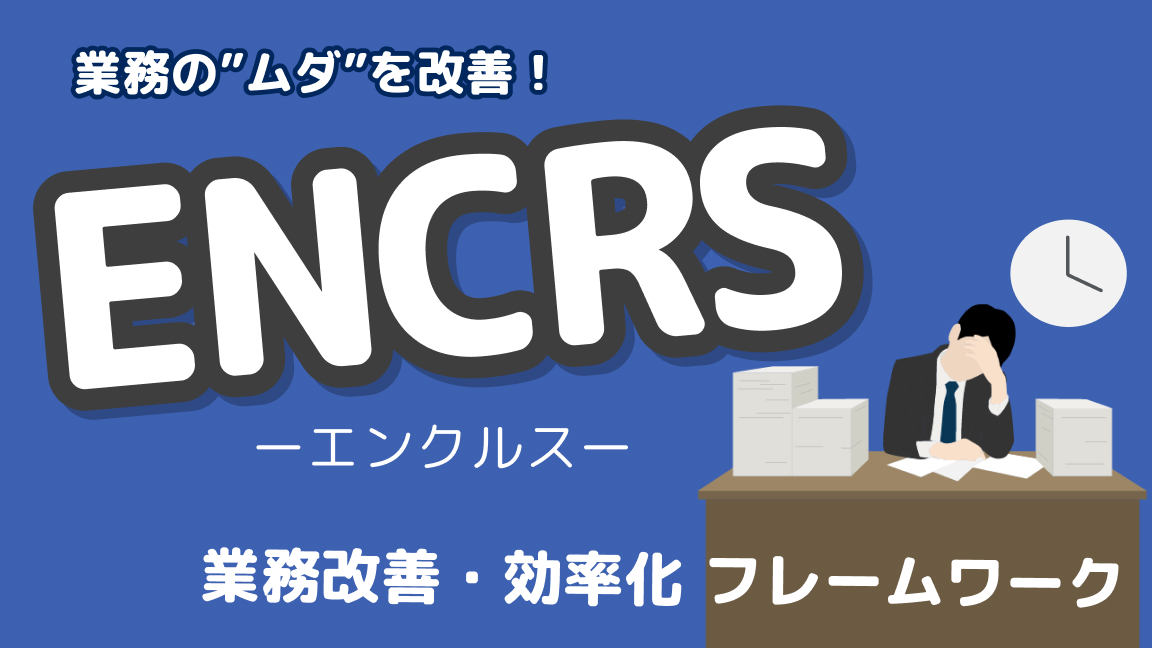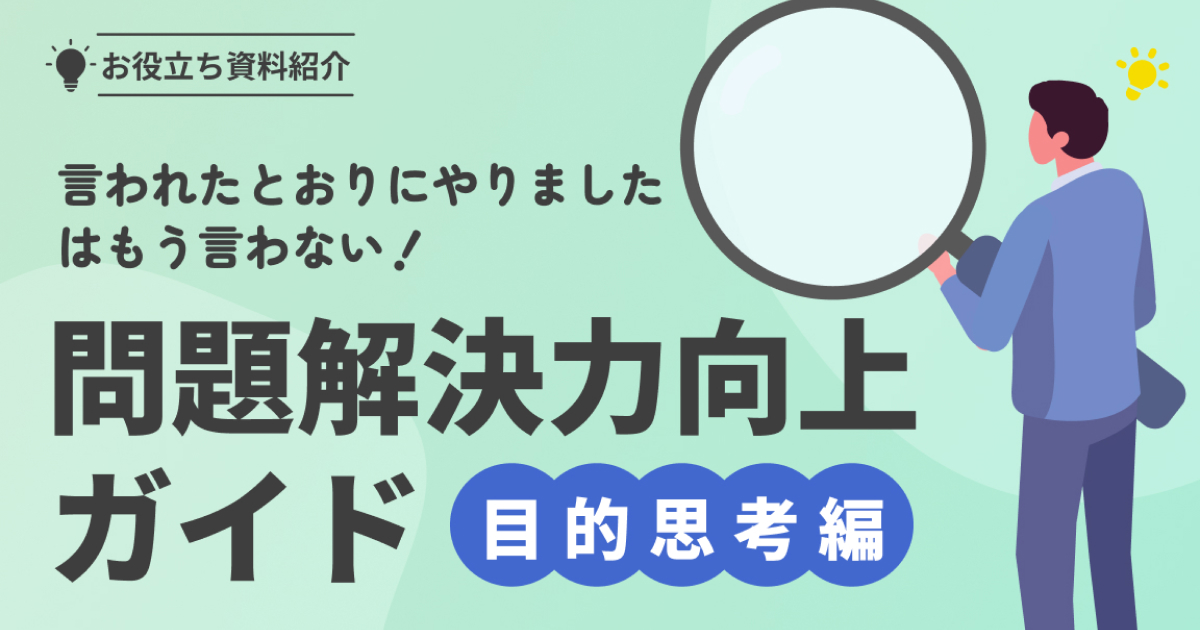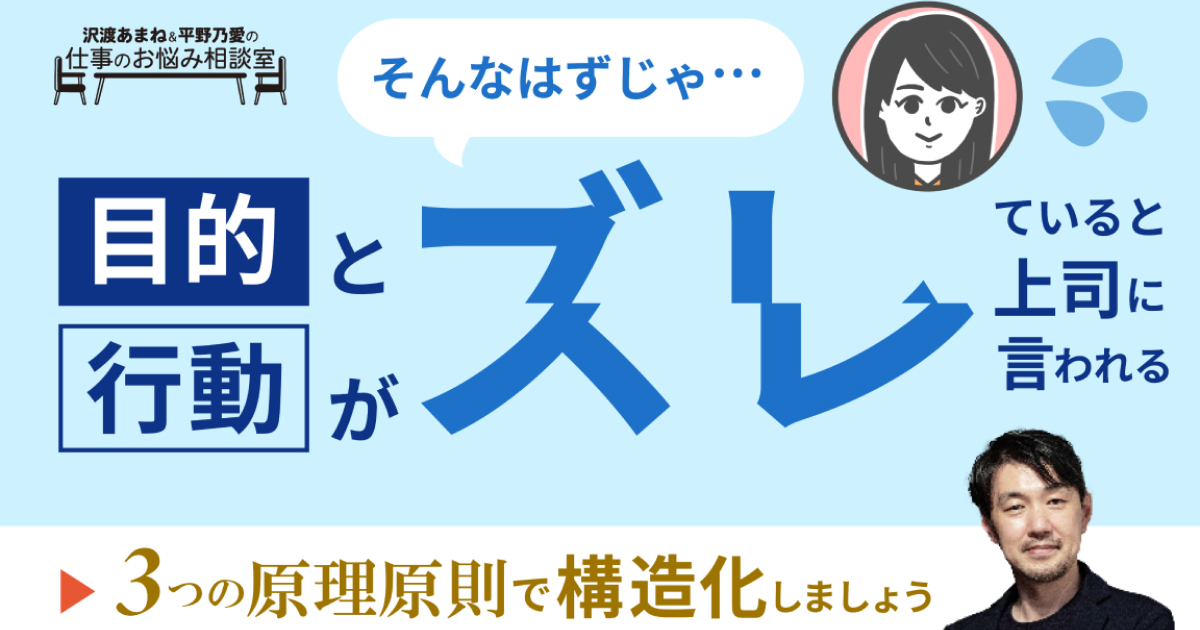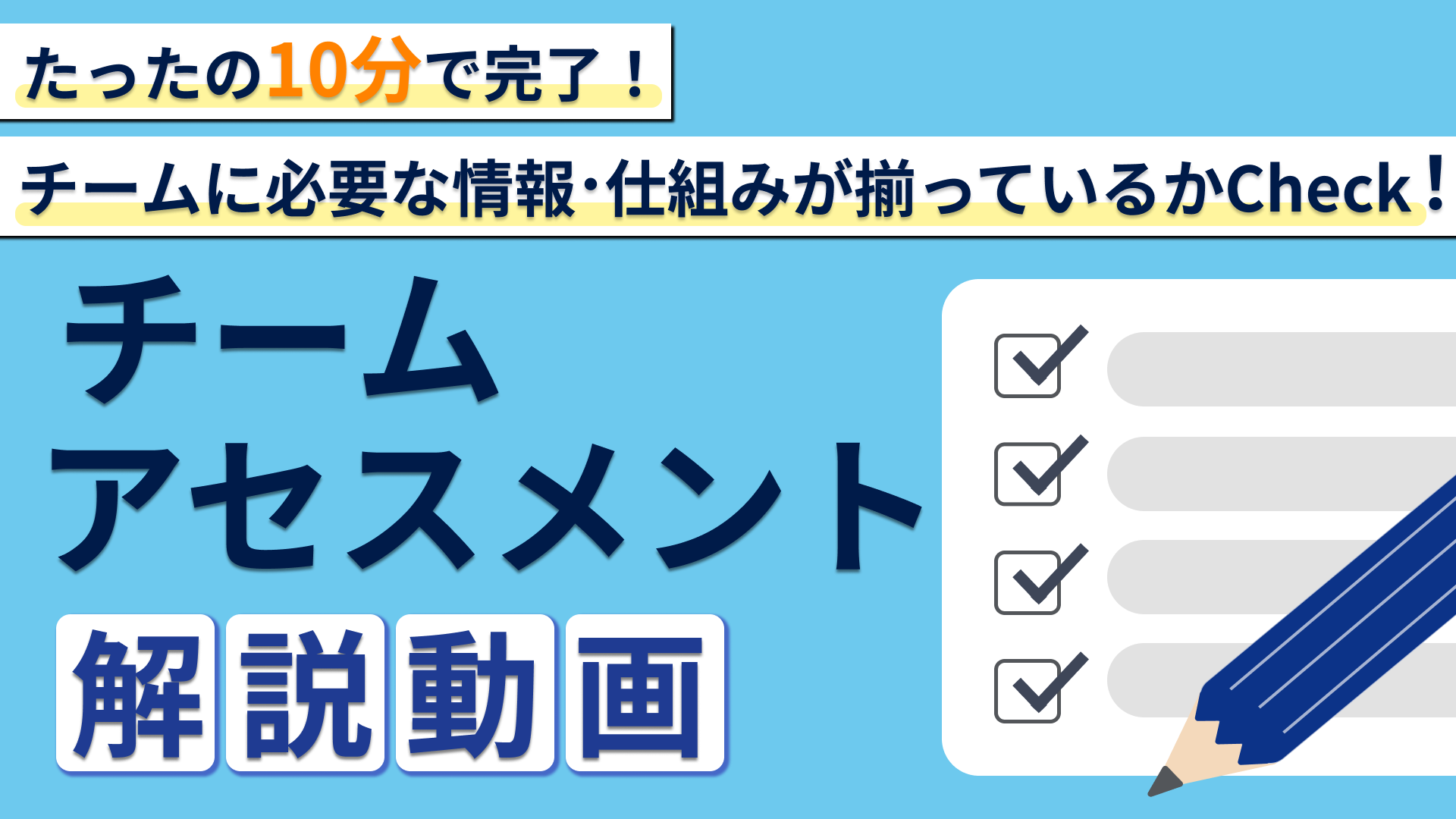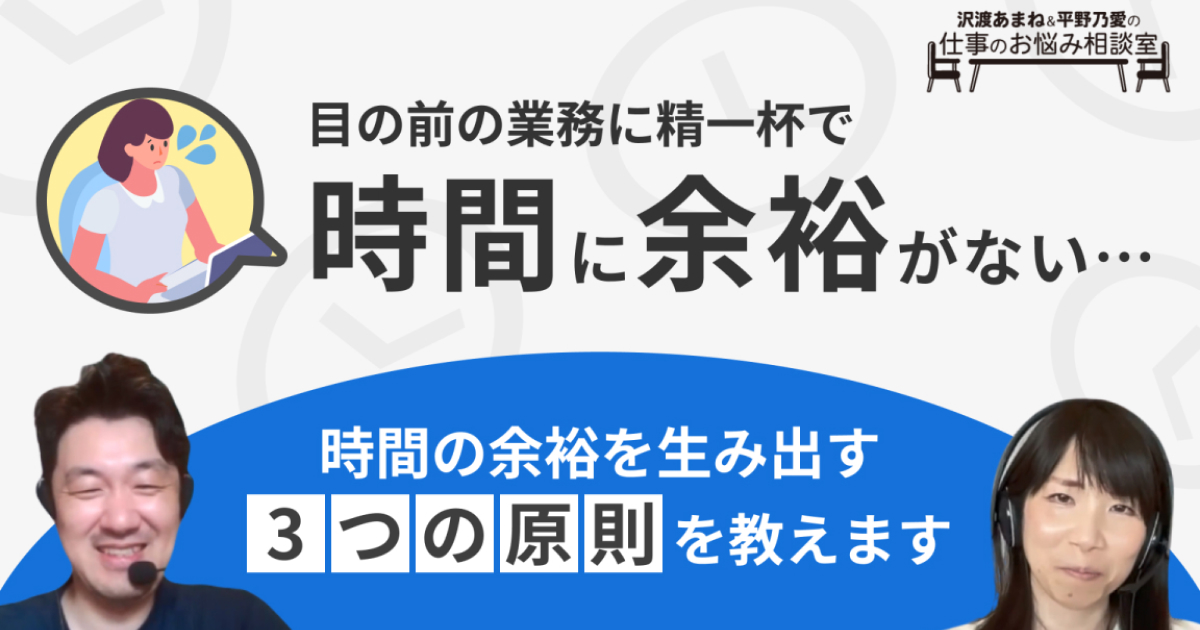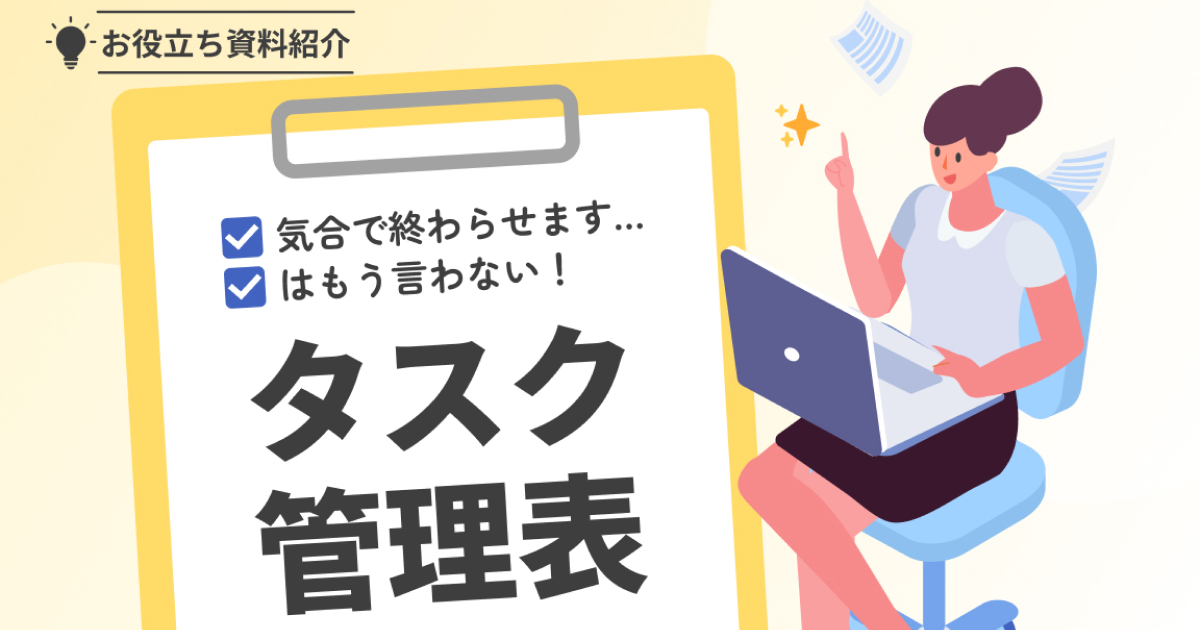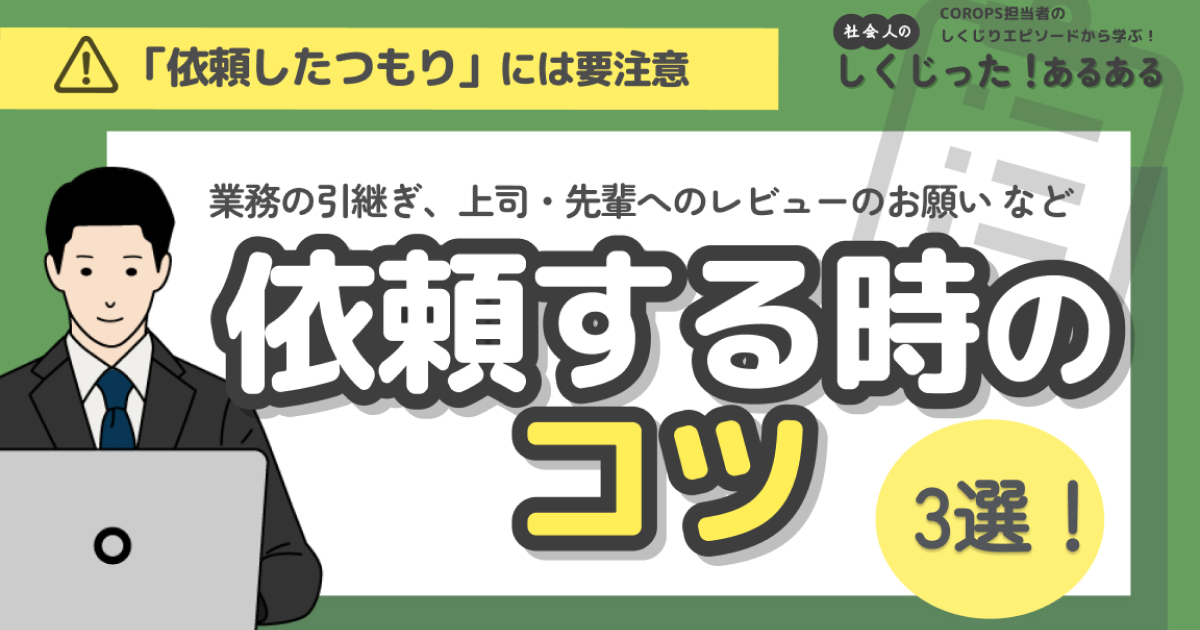稼働不足を解消して改善を進める方法
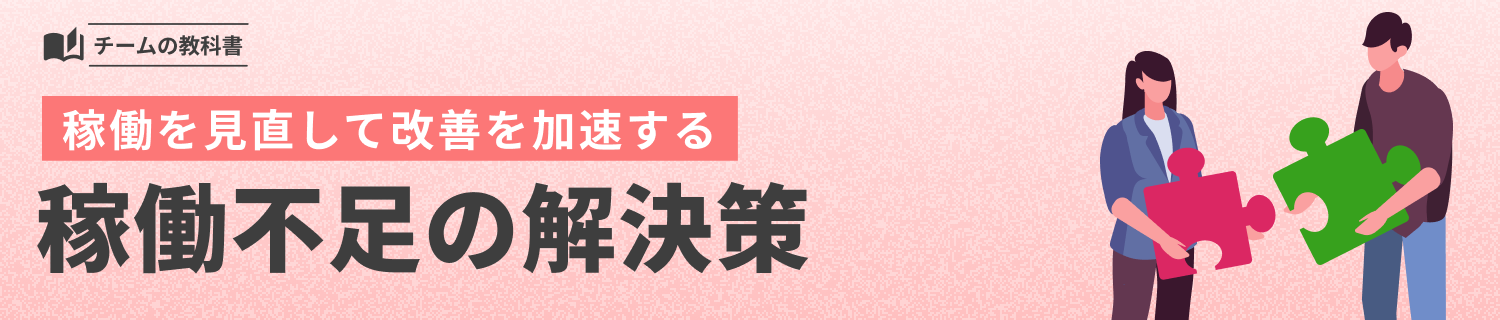
業務改善に向けた課題が整理され、打ち手も明確になっているにも関わらず、
「実行に移す稼働がない」という壁に直面するケースは少なくありません。
これは多くの現場で頻発する課題であり、放置すれば改善の機会を逃すだけでなく、
チームの成長も停滞しかねません。
この“稼働問題”に対する解決策は、実はシンプルです。大きく分けて、以下の2つのアプローチが有効です。
1.スキマ時間を活用し、改善を“細切れ”で進める
日々の業務が忙しく、まとまった時間を確保するのが難しい場合は、
15分・30分といった短時間で作業を進める工夫が必要です。
改善活動を「細切れ」にすることで、日常業務の合間にも着手できるようになります。
この方法を成功させる鍵は、作業の洗い出しです。
どの作業をどの単位で進めるかを明確にすることで、短時間でも着実に前進できます。
未来のために1%の時間を使うだけでも、1年後には37倍の成果につながる
──これは複利的な成長の考え方です。
2.一定期間、稼働調整を行い、改善のための時間を“確保”する
改善活動は、そもそも時間的余裕がないからこそ必要とされるものです。
そのため、「空いた時間でやる」ではなく、「時間を作る」ことが求められます。
この場合、管理者がチーム全体の労務状況を見ながら、期間を定めて残業時間や業務調整を行い、改善活動に充てる時間を確保する必要があります。
チーム内での“コミットメント”
- 何時間を確保するのか
- どの期間で進めるのか
- どの打ち手を優先するのか
これらを明示し、メンバーに説明した上で進めることで、
改善活動が「やれること」から「やること」へと変わります。
稼働は待っていても、絶対に確保できません。意図的に作り出すことが、改善の第一歩です。
改善は“稼働の確保”から始まります。
改善の打ち手が見えていても、実行に移す稼働がなければ成果は生まれません。
スキマ時間の活用と稼働調整という2つのアプローチを組み合わせることで、初期稼働を創出し、改善活動を持続可能なものにすることができます。
関連資料
おすすめ動画
稼働不足を解消して改善を進める方法
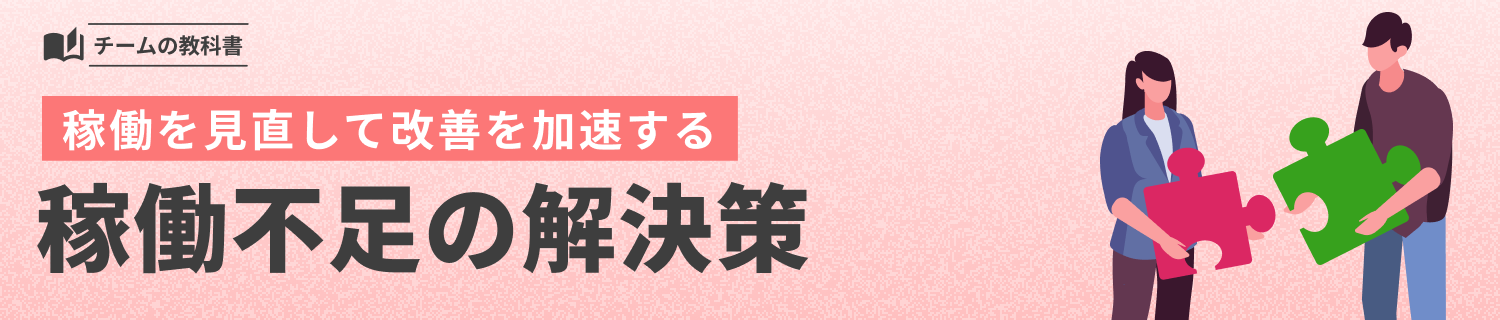
業務改善に向けた課題が整理され、打ち手も明確になっているにも関わらず、
「実行に移す稼働がない」という壁に直面するケースは少なくありません。
これは多くの現場で頻発する課題であり、放置すれば改善の機会を逃すだけでなく、
チームの成長も停滞しかねません。
この“稼働問題”に対する解決策は、実はシンプルです。大きく分けて、以下の2つのアプローチが有効です。
1.スキマ時間を活用し、改善を“細切れ”で進める
日々の業務が忙しく、まとまった時間を確保するのが難しい場合は、
15分・30分といった短時間で作業を進める工夫が必要です。
改善活動を「細切れ」にすることで、日常業務の合間にも着手できるようになります。
この方法を成功させる鍵は、作業の洗い出しです。
どの作業をどの単位で進めるかを明確にすることで、短時間でも着実に前進できます。
未来のために1%の時間を使うだけでも、1年後には37倍の成果につながる
──これは複利的な成長の考え方です。
2.一定期間、稼働調整を行い、改善のための時間を“確保”する
改善活動は、そもそも時間的余裕がないからこそ必要とされるものです。
そのため、「空いた時間でやる」ではなく、「時間を作る」ことが求められます。
この場合、管理者がチーム全体の労務状況を見ながら、期間を定めて残業時間や業務調整を行い、改善活動に充てる時間を確保する必要があります。
チーム内での“コミットメント”
- 何時間を確保するのか
- どの期間で進めるのか
- どの打ち手を優先するのか
これらを明示し、メンバーに説明した上で進めることで、
改善活動が「やれること」から「やること」へと変わります。
稼働は待っていても、絶対に確保できません。意図的に作り出すことが、改善の第一歩です。
改善は“稼働の確保”から始まります。
改善の打ち手が見えていても、実行に移す稼働がなければ成果は生まれません。
スキマ時間の活用と稼働調整という2つのアプローチを組み合わせることで、初期稼働を創出し、改善活動を持続可能なものにすることができます。
関連資料