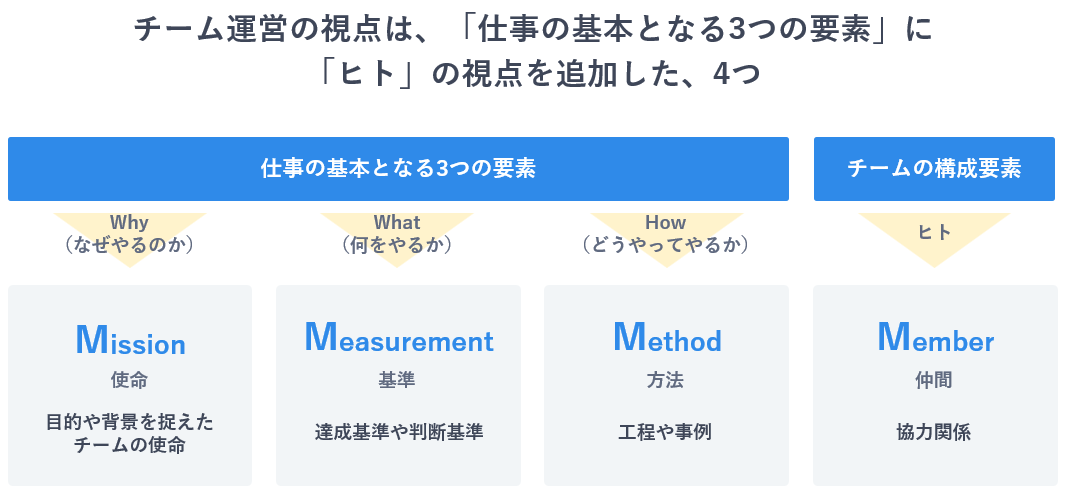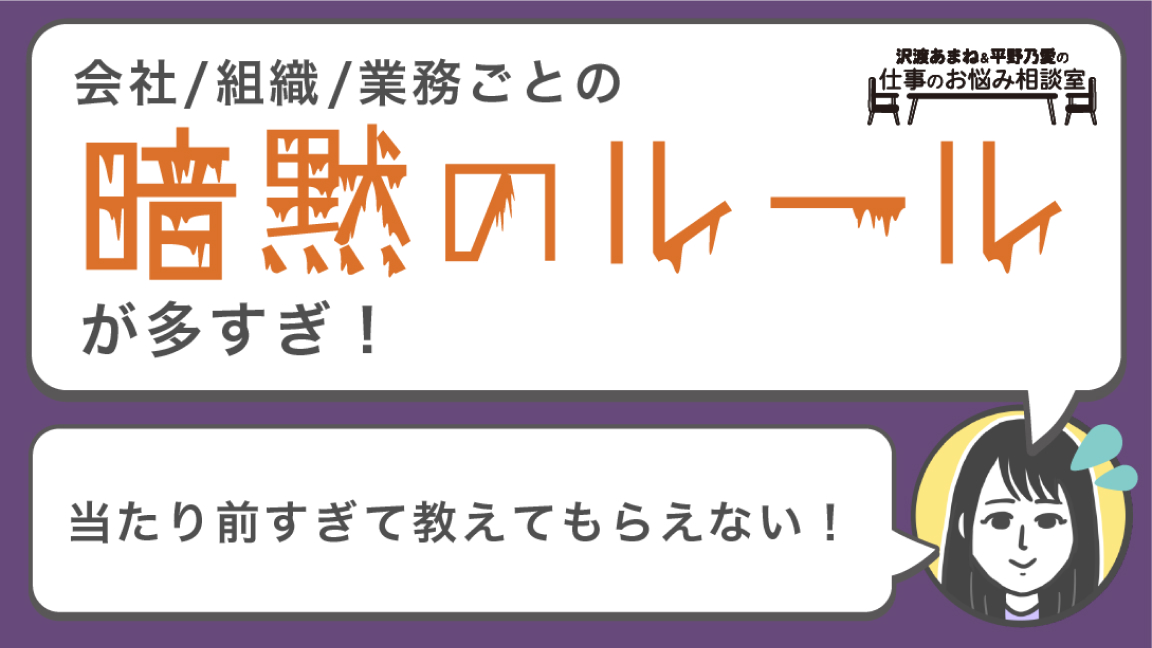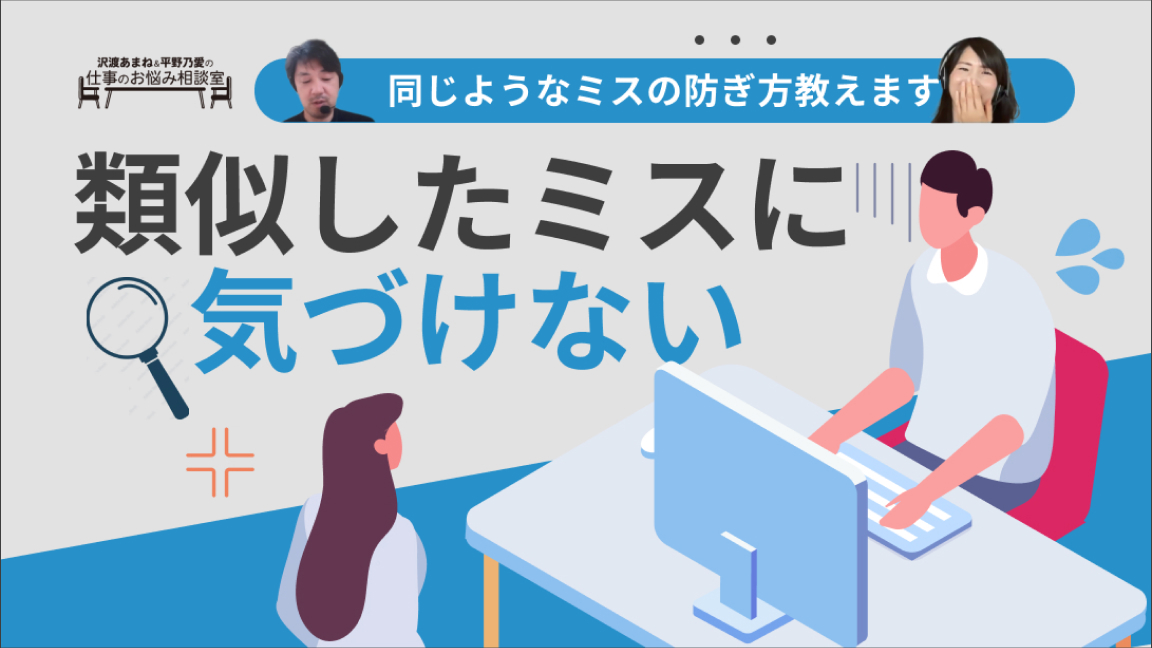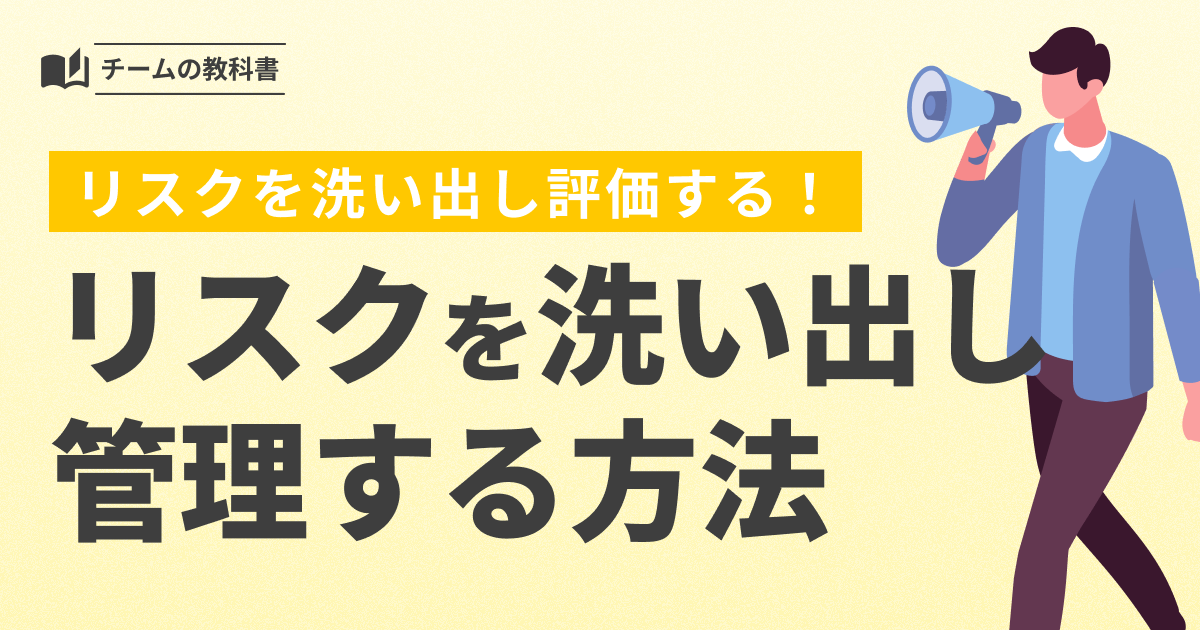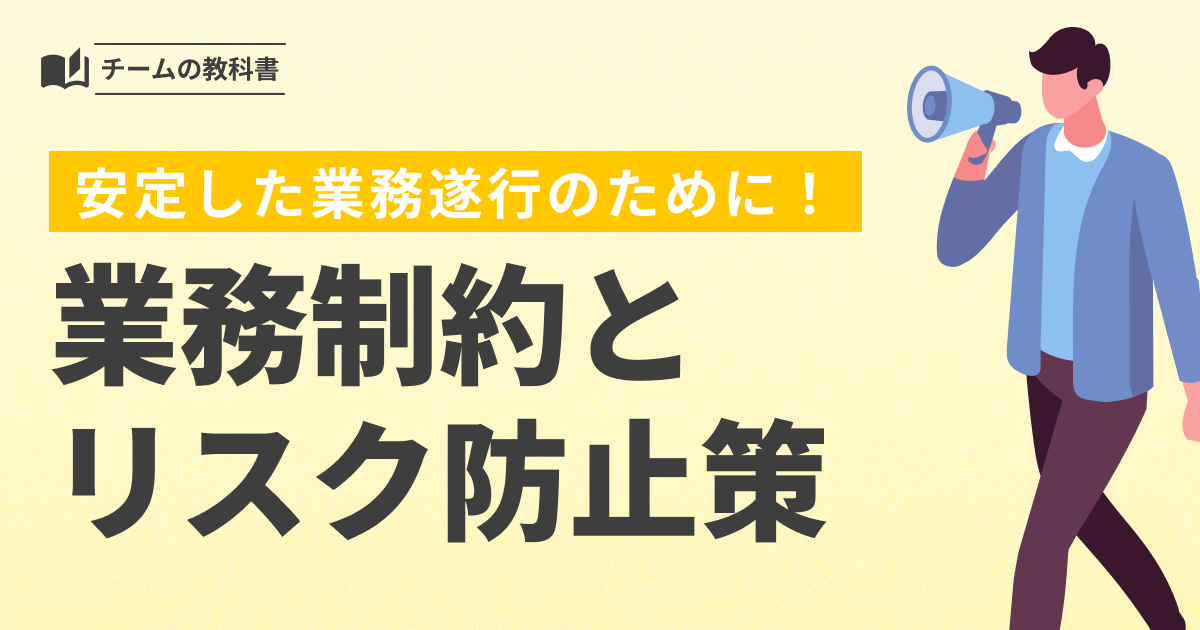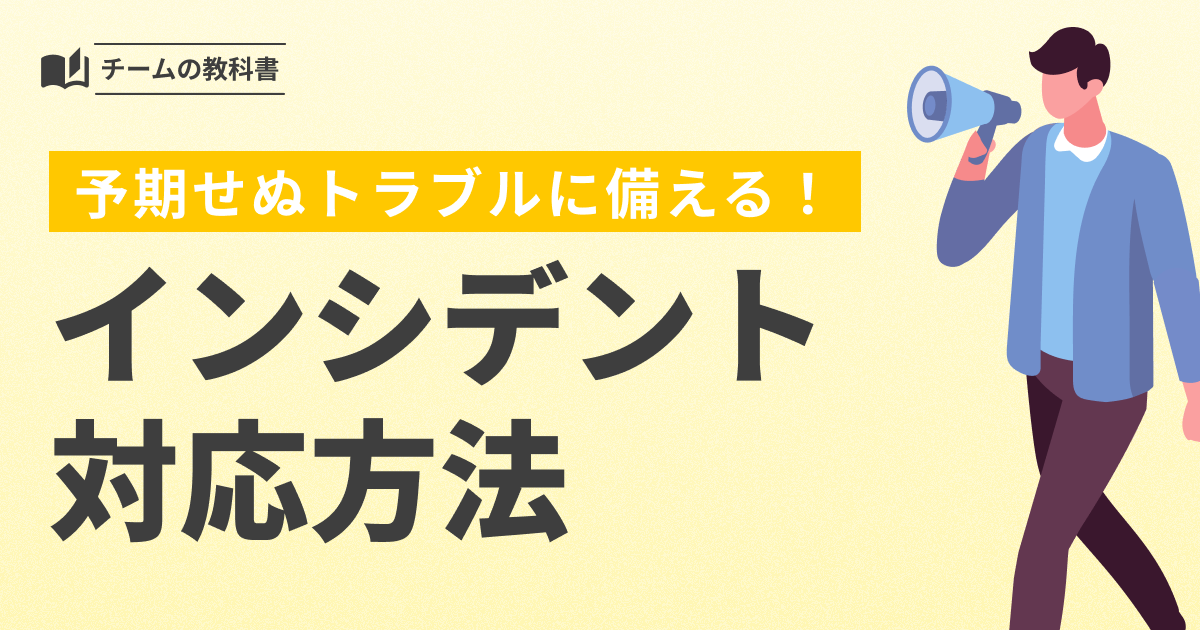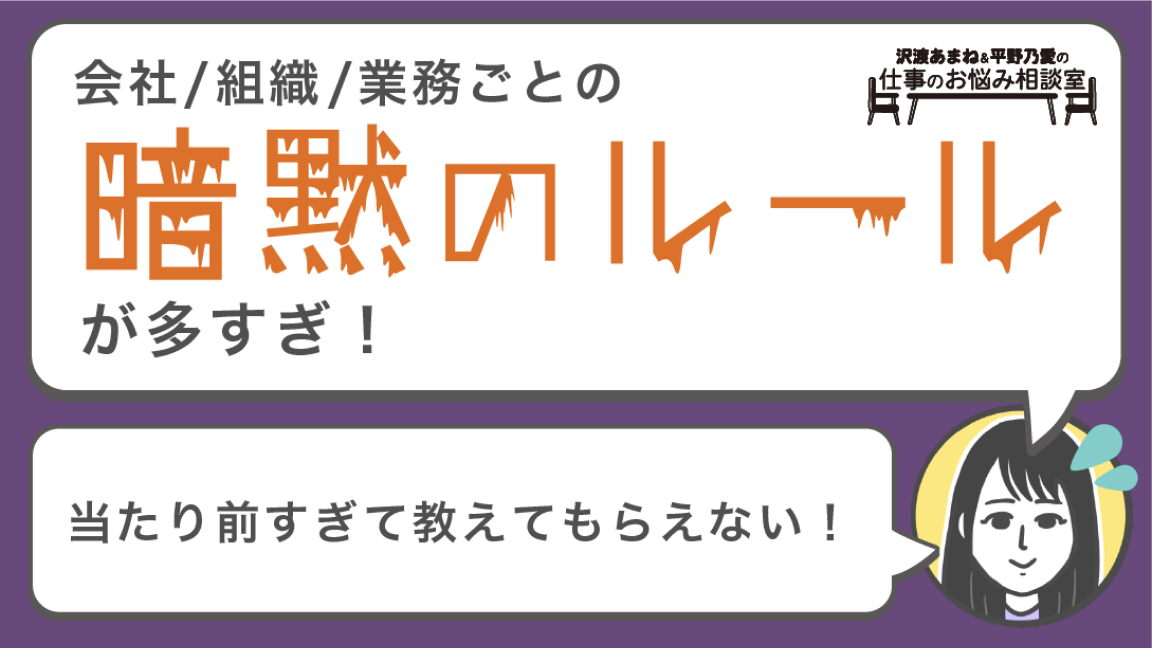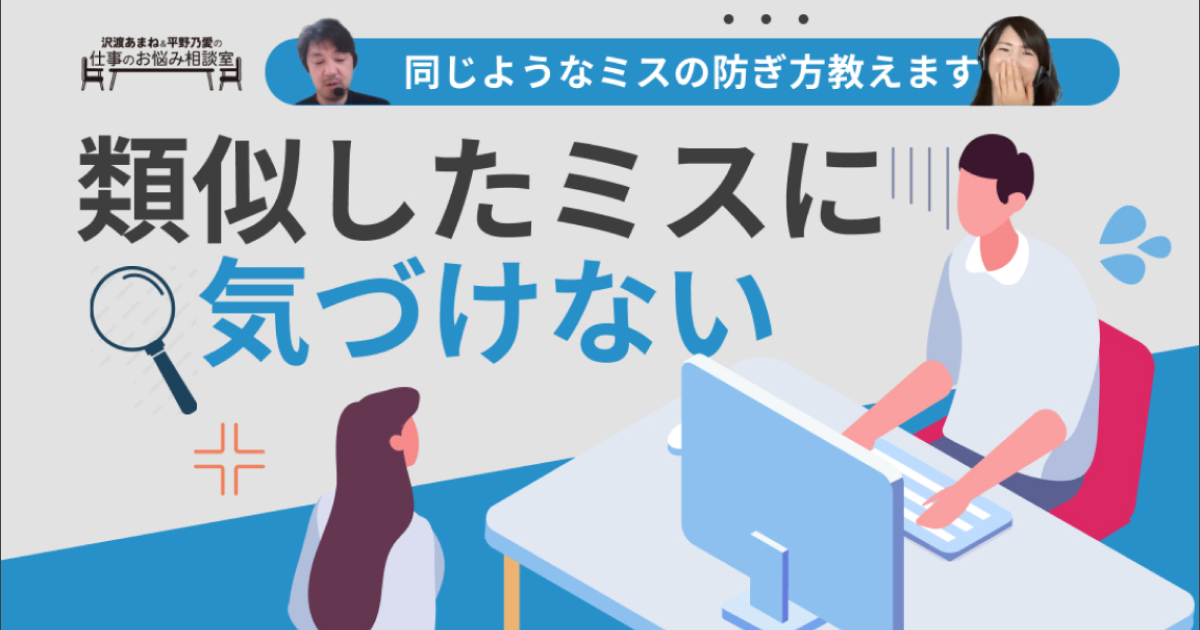課題解決を加速するIssueリストの使い方
ミス・トラブル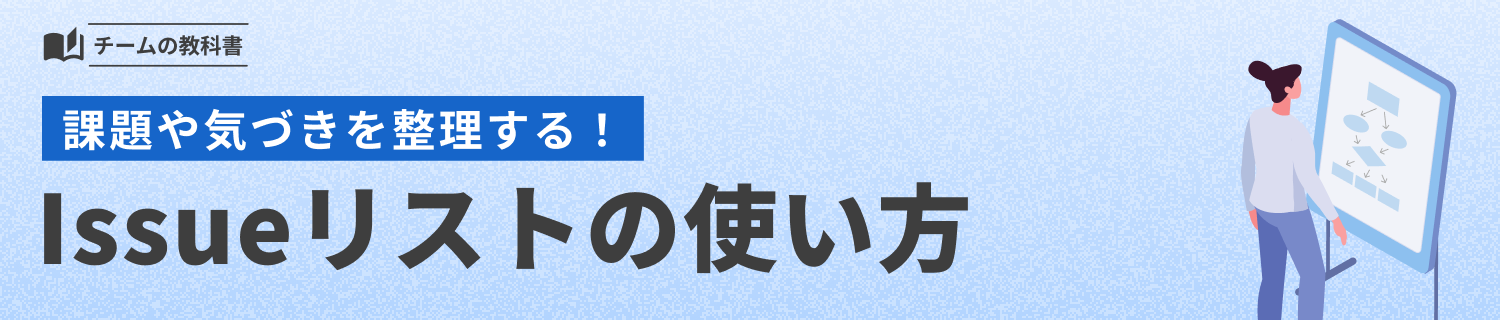
チームが目標に向かって進む際、計画時には見えなかった課題や、実行して初めて気づく改善点は必ず出てきます。
これらの課題を放置せず、体系的に収集・整理し、具体的なアクションにつなげる仕組みが「Issueリスト」です。
Issueリストは、課題や気づきを「見える化」し、チーム全体で共有・活用できる便利なツールです。
これを活用することで、課題を解決しながらチームの成長と成果の最大化が可能になります。
この記事では、Issueリストの基本的な役割を解説した上で、
その活用方法を「収集」「アクション化」「実行」の3ステップで紹介します。
※Issueリストと課題管理表の違い
Issueリストが課題の「何が問題か」を明確にするためのリストであるのに対し、
課題管理表は「どう解決するか」を課題、タスク、担当者、期日、進捗などを具体的に管理する表です。
課題管理表の元となるリストとして活用しましょう。
1. Issueリストとは?
Issue(イシュー)リストとは、チームの中で発生している課題や気づき、
改善のヒントを記録・整理するためのリストです。
日々の業務の中で「やりづらい」「気になる」「もっとこうした方が良いのでは?」と感じたことを可視化し、チーム全体で共有・活用することで、継続的な改善を促進します。
Issueリストがあることで得られるメリット
- 課題の見える化:個人の気づきをチーム全体で共有できる
- 改善のスピード向上:気づいたことをすぐにアクションにつなげられる
- チームの成長促進:現場の声をもとに、業務や仕組みを進化させられる
- 心理的安全性の向上:意見を出しやすい環境が整い、チーム内の対話が活性化する
Issueリストがない場合に生じるリスク
- 課題が埋もれる:現場で感じた違和感や改善点が放置される
- 同じ失敗の繰り返し:過去の問題が記録されず、再発防止ができない
- 改善の機会損失:メンバーの気づきが活かされず、チームの成長が停滞する
- 属人化の加速:個人の経験が共有されず、ノウハウが個人に閉じてしまう
-
Issueリストは、チームの「気づき」を「改善」につなげるための出発点である
-
記録すること自体が目的ではなく、アクションに結びつけることでチームの生産性と柔軟性が向上する
2. Issueリストの活用方法
- Issueリストで改善意見を収集する
- 収集した意見をアクション化する
- アクションを実行する
Step1:Issueリストで改善意見を収集する
課題や改善点の発見は、チームの成長に欠かせません。
まずは、チーム内の意見を幅広く収集する仕組みを整え、課題や気づきを見える化しましょう。
①収集の仕組みを整える
- 共有ファイルやチャット部屋を用意:チーム全員が編集できるExcelやスプレッドシートがおすすめ
- 記載ルールを明確に:不安・気づき・アイデア・改善点など、記載内容を事前にすり合わせておく
- 記入頻度を決める:週1回など定期的な記入を促すことで、日常業務の中でアンテナを張る習慣が生まれる
②補完手段としてインタビューを活用
- 業務が忙しく記入が進まない場合は、インタビューで意見を引き出す
- 事前に業務内容や4M(Mission, Measurement, Method, Member)の視点で仮説を立てておくと、スムーズに進行できる
|
|
Step2:収集した意見をアクション化する
収集した意見をそのままにしておいては意味がありません。
次に、それらを具体的な行動につなげるために整理し、チーム全体で共有・議論しながら解決策を明確化しましょう。
①4Mでカテゴリ分類する
- Mission:顧客ニーズ、期待値、事故・ヒヤリハットなど
- Measurement:目標、指標、進捗に対する違和感
- Method:業務フロー、ナレッジ、標準化の余地
- Member:稼働状況、育成、ローカルルールなど
分類することで、意見の偏りや見落としを可視化できます。
意見が少ないカテゴリは、視点が向いていない可能性があるため、追加の収集が必要です。
②チームで意見交換する
- 事象と原因のすり合わせ:何が起きているのかを共有し、認識を揃える
- 解決状態の定義:「どうなれば解決か」を明確にし、未知の課題に対してはミッションやゴールを再確認してヒントを探ることが重要
- アクションの具体化:誰が何をいつまでにやるかを明確にし、進行に応じて柔軟に詳細化していくことが重要(理想はWBS化だが、箇条書きでもOK)
Step3:アクションを実行する
整理したアクションを実行することで、チームは実際の改善を進められます。
優先順位を決め、効果的に割り振ることで、着実な進捗と成果につなげていきましょう。
①優先順位を決める
- 効果の大きさ、工数、放置による影響度を基準に、着手順を決定
②割り振りを工夫する
- 得意な人に任せる:スピードと精度が向上
- 志向性に合わせる:モチベーションが高まり、主体的な取り組みにつながる
- チャレンジ枠を設ける:未経験者にも挑戦の機会を提供し、フォロー体制を整えて支援する
③コミュニケーションプランを設計する
- 定期MTGに進捗共有のアジェンダを追加するなど、進捗を確認する場を必ず設ける
- 進捗が停滞する原因は「工数不足」だけでなく「イメージできないこと」も多い
相談や対話を通じて、行動のイメージを明確にすることが重要
まとめ
Issueリストは、チームの課題や改善のヒントが詰まった「宝の山」です。
収集→整理→実行のサイクルを回すことで、チームの改善力と成果が着実に高まります。
日常業務に組み込み、継続的に活用することで、チームの成長を加速させましょう。
関連資料
会員限定コンテンツで
仕事を進めやすくするヒントが見つかる!
おすすめ動画
課題解決を加速するIssueリストの使い方
ミス・トラブル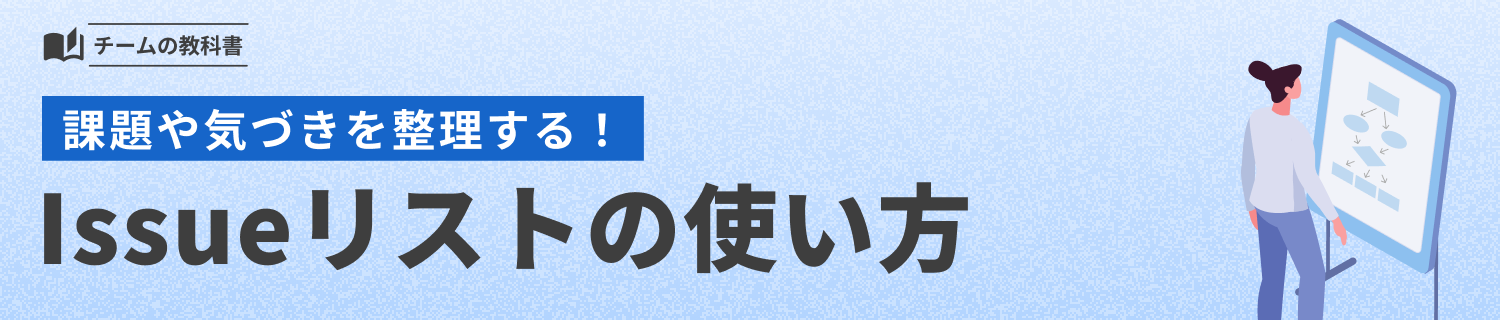
チームが目標に向かって進む際、計画時には見えなかった課題や、実行して初めて気づく改善点は必ず出てきます。
これらの課題を放置せず、体系的に収集・整理し、具体的なアクションにつなげる仕組みが「Issueリスト」です。
Issueリストは、課題や気づきを「見える化」し、チーム全体で共有・活用できる便利なツールです。
これを活用することで、課題を解決しながらチームの成長と成果の最大化が可能になります。
この記事では、Issueリストの基本的な役割を解説した上で、
その活用方法を「収集」「アクション化」「実行」の3ステップで紹介します。
※Issueリストと課題管理表の違い
Issueリストが課題の「何が問題か」を明確にするためのリストであるのに対し、
課題管理表は「どう解決するか」を課題、タスク、担当者、期日、進捗などを具体的に管理する表です。
課題管理表の元となるリストとして活用しましょう。
1. Issueリストとは?
Issue(イシュー)リストとは、チームの中で発生している課題や気づき、
改善のヒントを記録・整理するためのリストです。
日々の業務の中で「やりづらい」「気になる」「もっとこうした方が良いのでは?」と感じたことを可視化し、チーム全体で共有・活用することで、継続的な改善を促進します。
Issueリストがあることで得られるメリット
- 課題の見える化:個人の気づきをチーム全体で共有できる
- 改善のスピード向上:気づいたことをすぐにアクションにつなげられる
- チームの成長促進:現場の声をもとに、業務や仕組みを進化させられる
- 心理的安全性の向上:意見を出しやすい環境が整い、チーム内の対話が活性化する
Issueリストがない場合に生じるリスク
- 課題が埋もれる:現場で感じた違和感や改善点が放置される
- 同じ失敗の繰り返し:過去の問題が記録されず、再発防止ができない
- 改善の機会損失:メンバーの気づきが活かされず、チームの成長が停滞する
- 属人化の加速:個人の経験が共有されず、ノウハウが個人に閉じてしまう
-
Issueリストは、チームの「気づき」を「改善」につなげるための出発点である
-
記録すること自体が目的ではなく、アクションに結びつけることでチームの生産性と柔軟性が向上する
2. Issueリストの活用方法
- Issueリストで改善意見を収集する
- 収集した意見をアクション化する
- アクションを実行する
Step1:Issueリストで改善意見を収集する
課題や改善点の発見は、チームの成長に欠かせません。
まずは、チーム内の意見を幅広く収集する仕組みを整え、課題や気づきを見える化しましょう。
①収集の仕組みを整える
- 共有ファイルやチャット部屋を用意:チーム全員が編集できるExcelやスプレッドシートがおすすめ
- 記載ルールを明確に:不安・気づき・アイデア・改善点など、記載内容を事前にすり合わせておく
- 記入頻度を決める:週1回など定期的な記入を促すことで、日常業務の中でアンテナを張る習慣が生まれる
②補完手段としてインタビューを活用
- 業務が忙しく記入が進まない場合は、インタビューで意見を引き出す
- 事前に業務内容や4M(Mission, Measurement, Method, Member)の視点で仮説を立てておくと、スムーズに進行できる
|
|
Step2:収集した意見をアクション化する
収集した意見をそのままにしておいては意味がありません。
次に、それらを具体的な行動につなげるために整理し、チーム全体で共有・議論しながら解決策を明確化しましょう。
①4Mでカテゴリ分類する
- Mission:顧客ニーズ、期待値、事故・ヒヤリハットなど
- Measurement:目標、指標、進捗に対する違和感
- Method:業務フロー、ナレッジ、標準化の余地
- Member:稼働状況、育成、ローカルルールなど
分類することで、意見の偏りや見落としを可視化できます。
意見が少ないカテゴリは、視点が向いていない可能性があるため、追加の収集が必要です。
②チームで意見交換する
- 事象と原因のすり合わせ:何が起きているのかを共有し、認識を揃える
- 解決状態の定義:「どうなれば解決か」を明確にし、未知の課題に対してはミッションやゴールを再確認してヒントを探ることが重要
- アクションの具体化:誰が何をいつまでにやるかを明確にし、進行に応じて柔軟に詳細化していくことが重要(理想はWBS化だが、箇条書きでもOK)
Step3:アクションを実行する
整理したアクションを実行することで、チームは実際の改善を進められます。
優先順位を決め、効果的に割り振ることで、着実な進捗と成果につなげていきましょう。
①優先順位を決める
- 効果の大きさ、工数、放置による影響度を基準に、着手順を決定
②割り振りを工夫する
- 得意な人に任せる:スピードと精度が向上
- 志向性に合わせる:モチベーションが高まり、主体的な取り組みにつながる
- チャレンジ枠を設ける:未経験者にも挑戦の機会を提供し、フォロー体制を整えて支援する
③コミュニケーションプランを設計する
- 定期MTGに進捗共有のアジェンダを追加するなど、進捗を確認する場を必ず設ける
- 進捗が停滞する原因は「工数不足」だけでなく「イメージできないこと」も多い
相談や対話を通じて、行動のイメージを明確にすることが重要
まとめ
Issueリストは、チームの課題や改善のヒントが詰まった「宝の山」です。
収集→整理→実行のサイクルを回すことで、チームの改善力と成果が着実に高まります。
日常業務に組み込み、継続的に活用することで、チームの成長を加速させましょう。
関連資料
会員限定コンテンツで
仕事を進めやすくするヒントが見つかる!