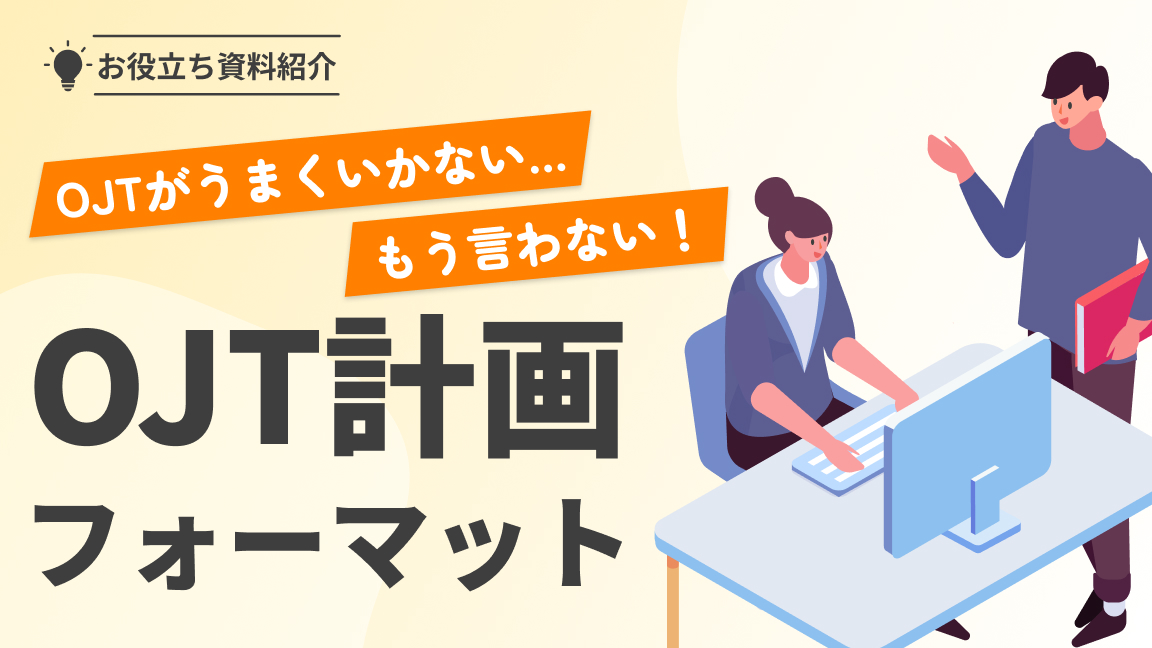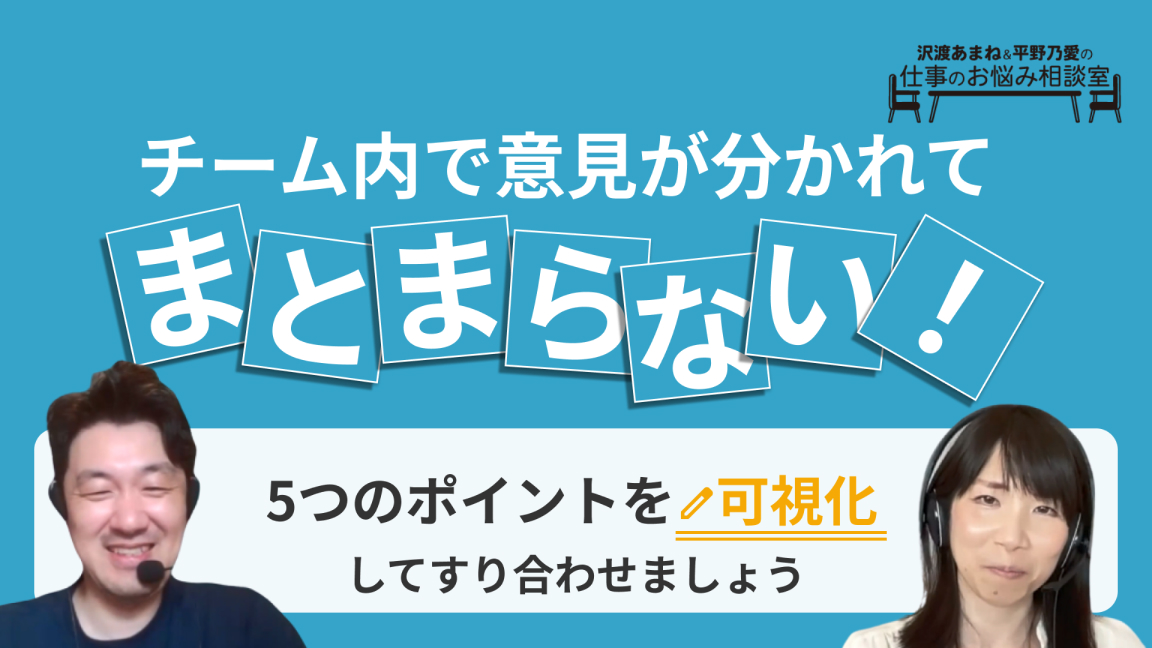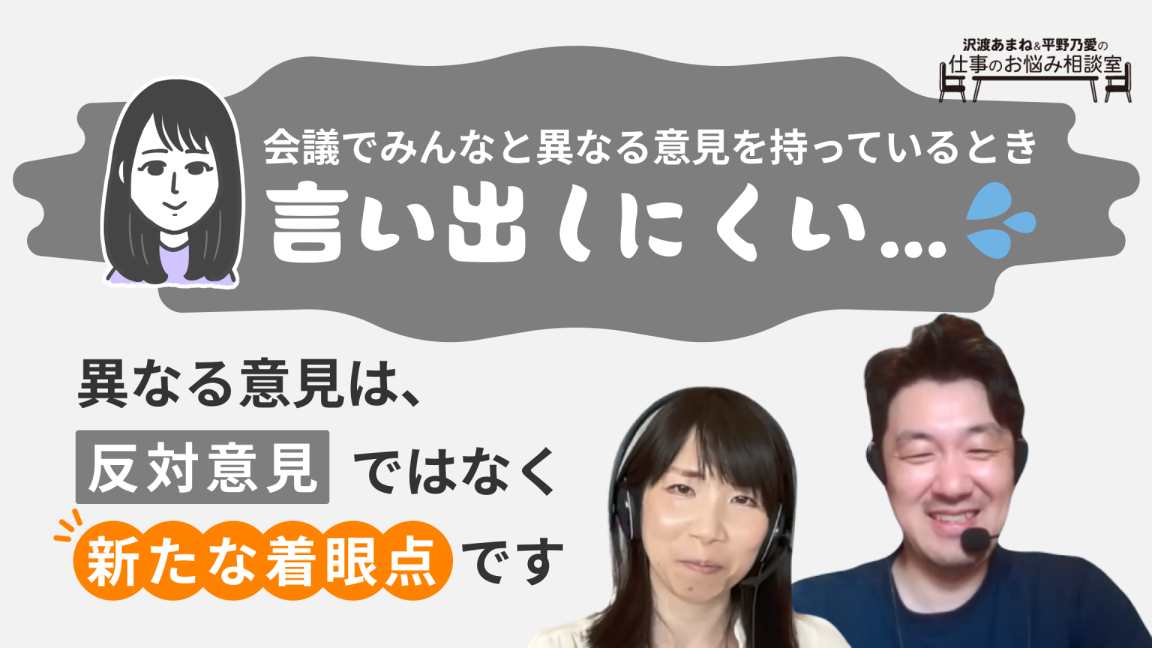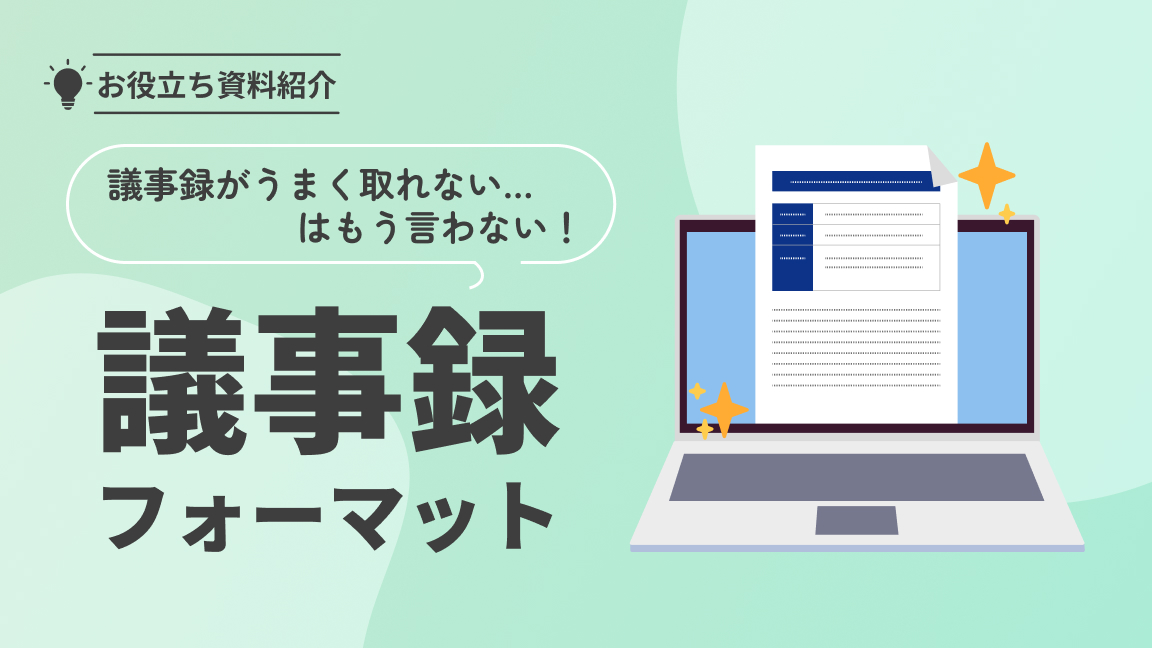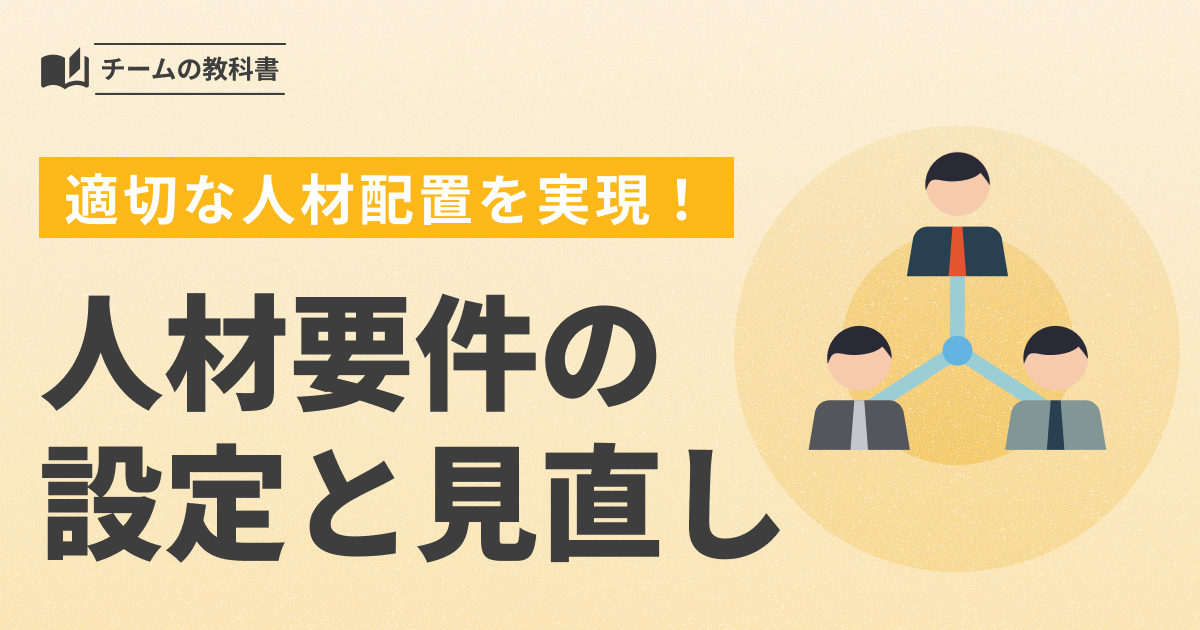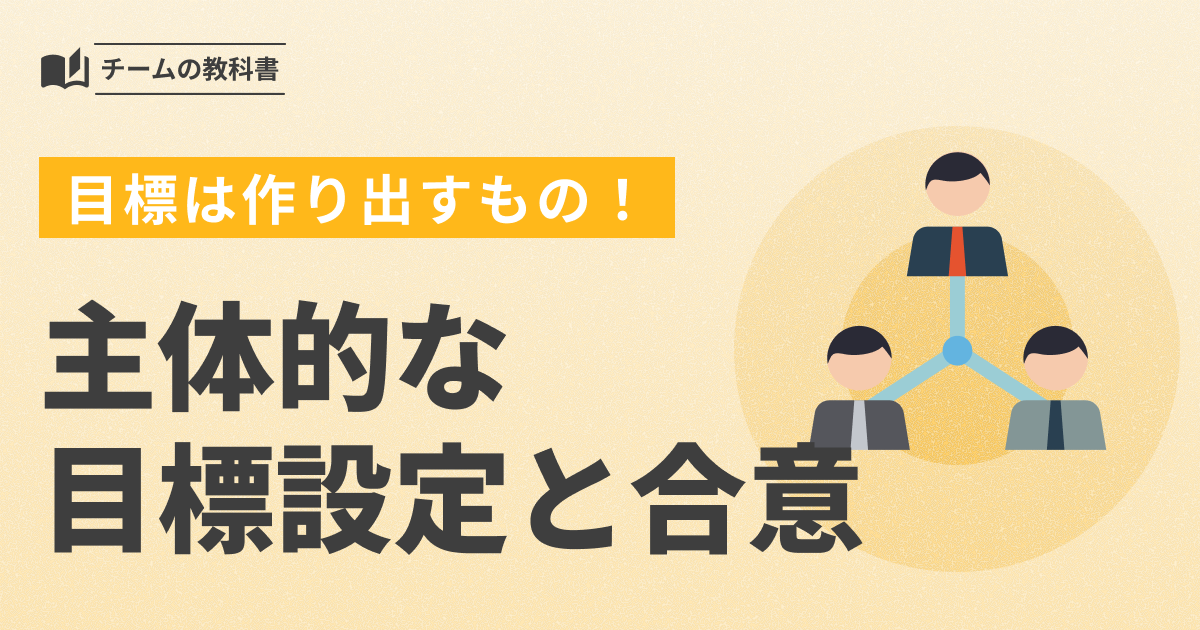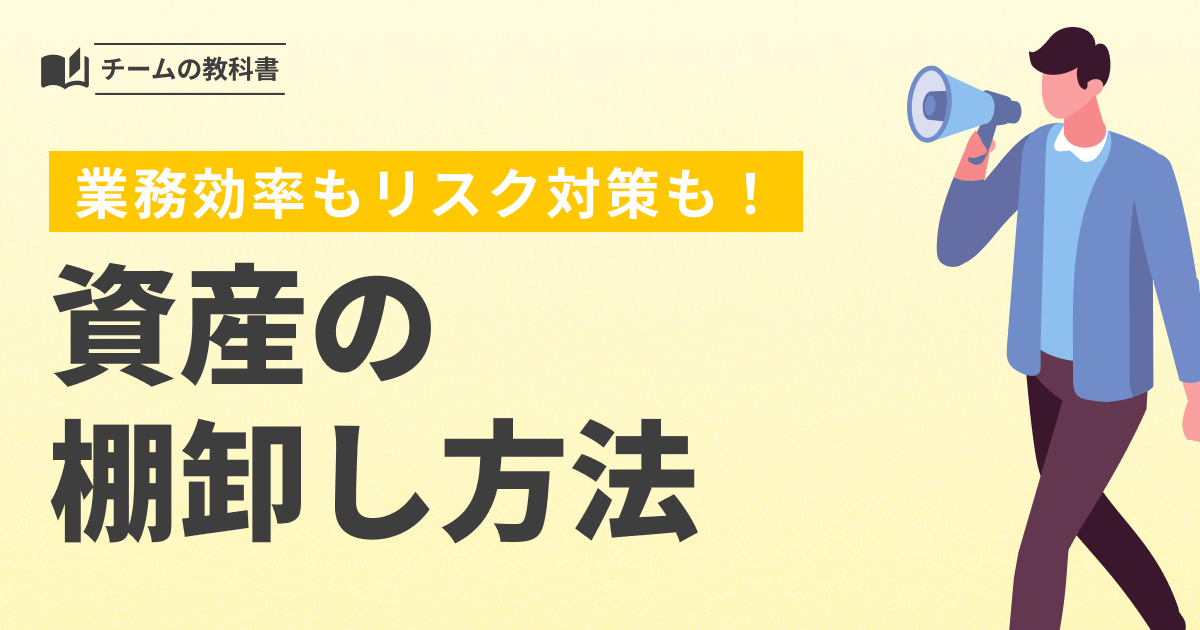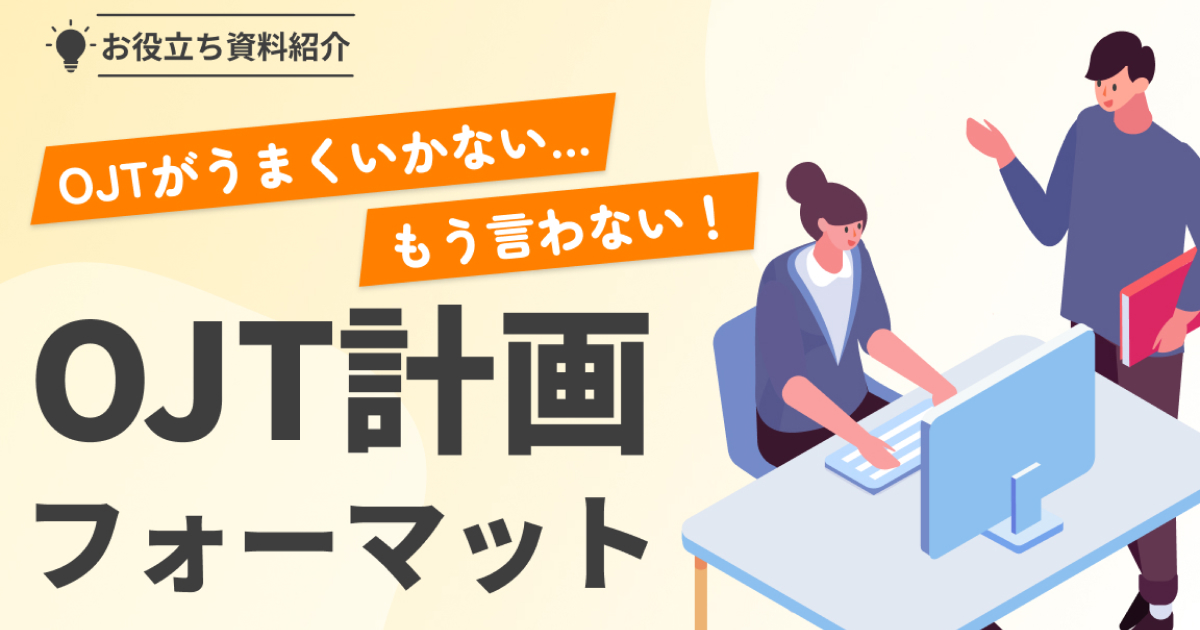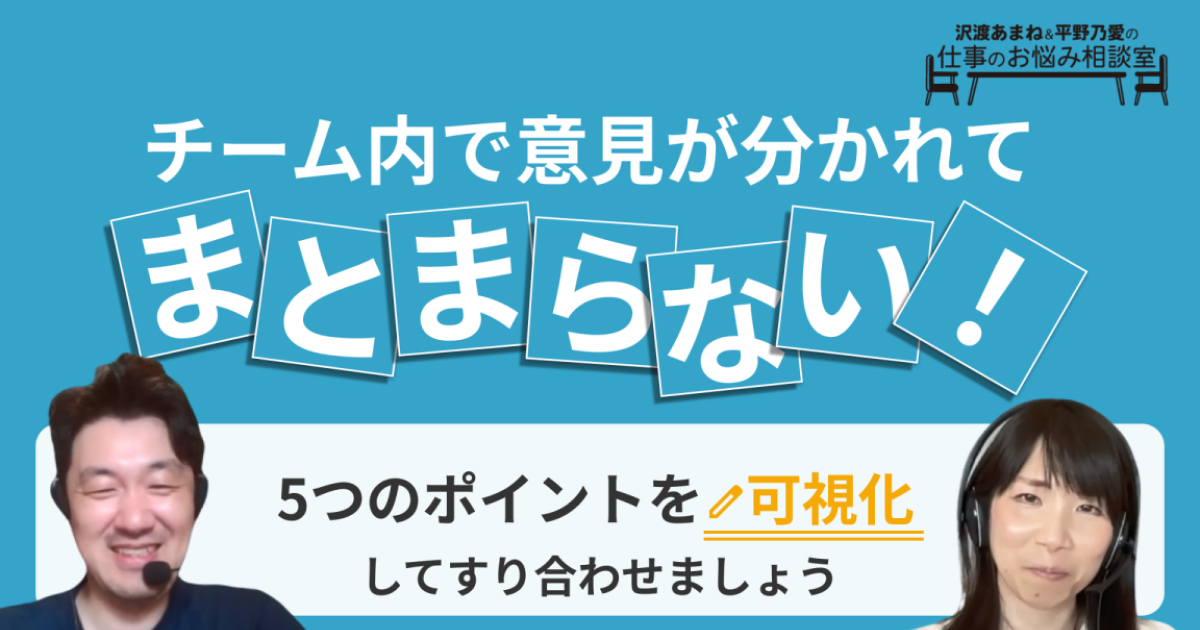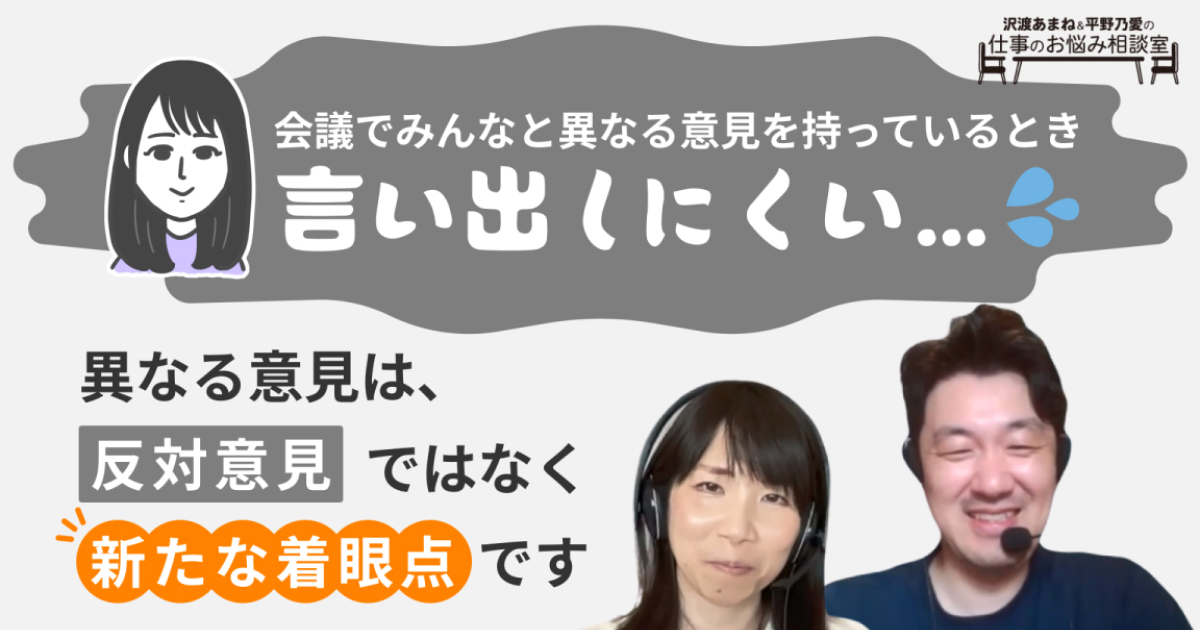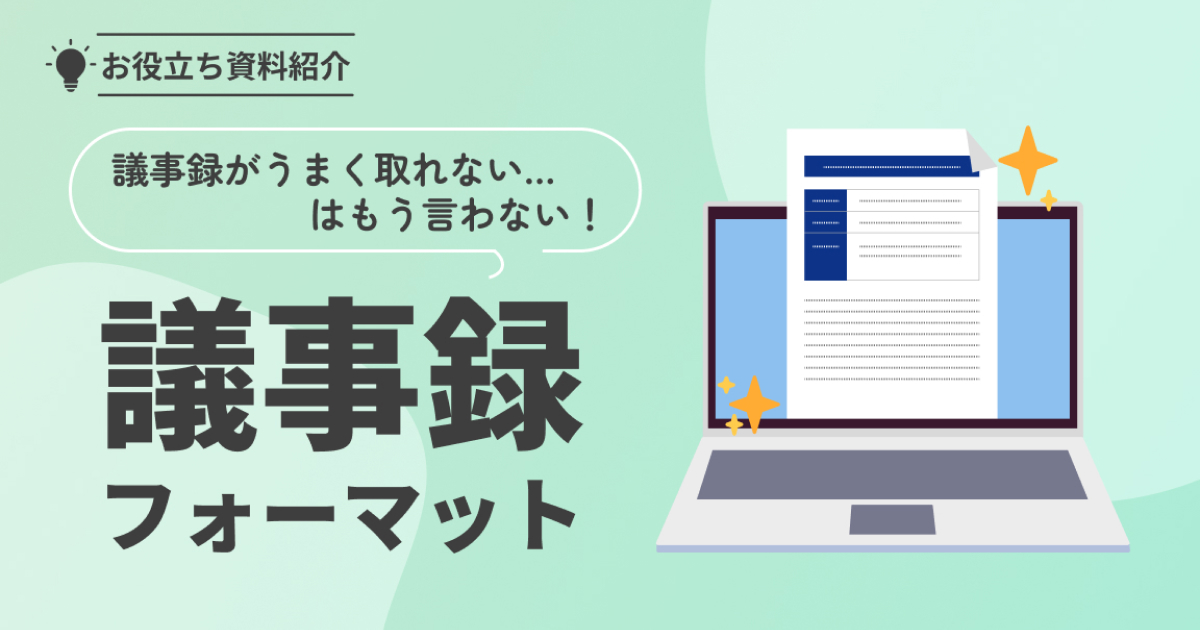1. コミュニケーションの仕組み化
コミュニケーションを仕組み化するために、”コミュニケーションプラン”を作成していきましょう。
コミュニケーションプランとは、仕事をスムーズに進めるために、対話の機会をあらかじめ計画し確保しておくことですので、
対話の内容により頻度や手法が変わってきます。
コミュニケーションプランを作成するために、「目的(内容)」「頻度」「手法」の3 つの事柄に分けて考えましょう。
- 目的(内容) 何を会話したいか? 「意見交換、相談、連絡、報告、承認」
-
頻度 どれくらい会話したいか? 「定期、不定期」
-
手法 どのように行いたいか? 「メール、チャット、対面、会議体」
- チームの組成時やプロジェクトの発足時には、関係者間で勘違いや認識ズレが発生しやすい時期ですので決定的なすれ違いによるリスクを低減するためにも、日次でのミーティングを設定しましょう。
- 決裁者など活動のカギを握る主要な関係者が参加される会議については、あらかじめ数ヵ月先まで定期的な接点を確保しましょう。
これは何かが起こってから、急に予定を確保しようとすると調整が難しいことが多いので、
情報交換や意思決定の遅れによるリスクを低減するためです。
(何か問題や会話したいことが発生した場合に、急にスケジュールを空けていただくよう調整するよりあらかじめ予定を確保し不要な場合にキャンセルする方が、相手への負担が少なく親切です。)
予定をキャンセルする際には、
「今週の会議で課題は解決したため来週までに追加のアジェンダがなければ次週定例はキャンセルします」など
理由をお伝えし、適宜関係者に連携を行いましょう
2. 関係性を深めるために効果的なこと
人との関係性はコミュニケーションの量に比例すると言われています。
チームの組成時やプロジェクト発足時などでは、関係性を深めるために頻度を高く対話することを意識しましょう。
また話し下手の方であっても、会う回数や相手の視界に入るだけ関係性を深める効果があります。
ザイアンスの法則
人が人に好感を持ち始める時は、話す内容や時間の長さは関係なく
実際に会う回数が多い人物であればあるほど好感を持ちやすい

加えて、日常的な接点だけではなく、より深い関係性を構築するためには普段とは別の交流の場を設けるとより効果的です。
- 仕事が一段落したタイミングでの「慰労会(打ち上げ)」
- 関係者の入れ替わりが発生したタイミングでの「歓送迎会」
- 新たなお付き合いを始める際の「交流会」
昨今は、対面での宴会を控える風潮もありますので、その場合はランチ会や業務時間内での振り返り会などを企画してみましょう。
3. 関連資料
▶▶【🎥動画】コミュニケーションプランフォーマット はこちら
おすすめ動画

1. コミュニケーションの仕組み化
コミュニケーションを仕組み化するために、”コミュニケーションプラン”を作成していきましょう。
コミュニケーションプランとは、仕事をスムーズに進めるために、対話の機会をあらかじめ計画し確保しておくことですので、
対話の内容により頻度や手法が変わってきます。
コミュニケーションプランを作成するために、「目的(内容)」「頻度」「手法」の3 つの事柄に分けて考えましょう。
- 目的(内容) 何を会話したいか? 「意見交換、相談、連絡、報告、承認」
-
頻度 どれくらい会話したいか? 「定期、不定期」
-
手法 どのように行いたいか? 「メール、チャット、対面、会議体」
- チームの組成時やプロジェクトの発足時には、関係者間で勘違いや認識ズレが発生しやすい時期ですので決定的なすれ違いによるリスクを低減するためにも、日次でのミーティングを設定しましょう。
- 決裁者など活動のカギを握る主要な関係者が参加される会議については、あらかじめ数ヵ月先まで定期的な接点を確保しましょう。
これは何かが起こってから、急に予定を確保しようとすると調整が難しいことが多いので、
情報交換や意思決定の遅れによるリスクを低減するためです。
(何か問題や会話したいことが発生した場合に、急にスケジュールを空けていただくよう調整するよりあらかじめ予定を確保し不要な場合にキャンセルする方が、相手への負担が少なく親切です。)
予定をキャンセルする際には、
「今週の会議で課題は解決したため来週までに追加のアジェンダがなければ次週定例はキャンセルします」など
理由をお伝えし、適宜関係者に連携を行いましょう
2. 関係性を深めるために効果的なこと
人との関係性はコミュニケーションの量に比例すると言われています。
チームの組成時やプロジェクト発足時などでは、関係性を深めるために頻度を高く対話することを意識しましょう。
また話し下手の方であっても、会う回数や相手の視界に入るだけ関係性を深める効果があります。
ザイアンスの法則
人が人に好感を持ち始める時は、話す内容や時間の長さは関係なく
実際に会う回数が多い人物であればあるほど好感を持ちやすい

加えて、日常的な接点だけではなく、より深い関係性を構築するためには普段とは別の交流の場を設けるとより効果的です。
- 仕事が一段落したタイミングでの「慰労会(打ち上げ)」
- 関係者の入れ替わりが発生したタイミングでの「歓送迎会」
- 新たなお付き合いを始める際の「交流会」
昨今は、対面での宴会を控える風潮もありますので、その場合はランチ会や業務時間内での振り返り会などを企画してみましょう。
3. 関連資料
▶▶【🎥動画】コミュニケーションプランフォーマット はこちら