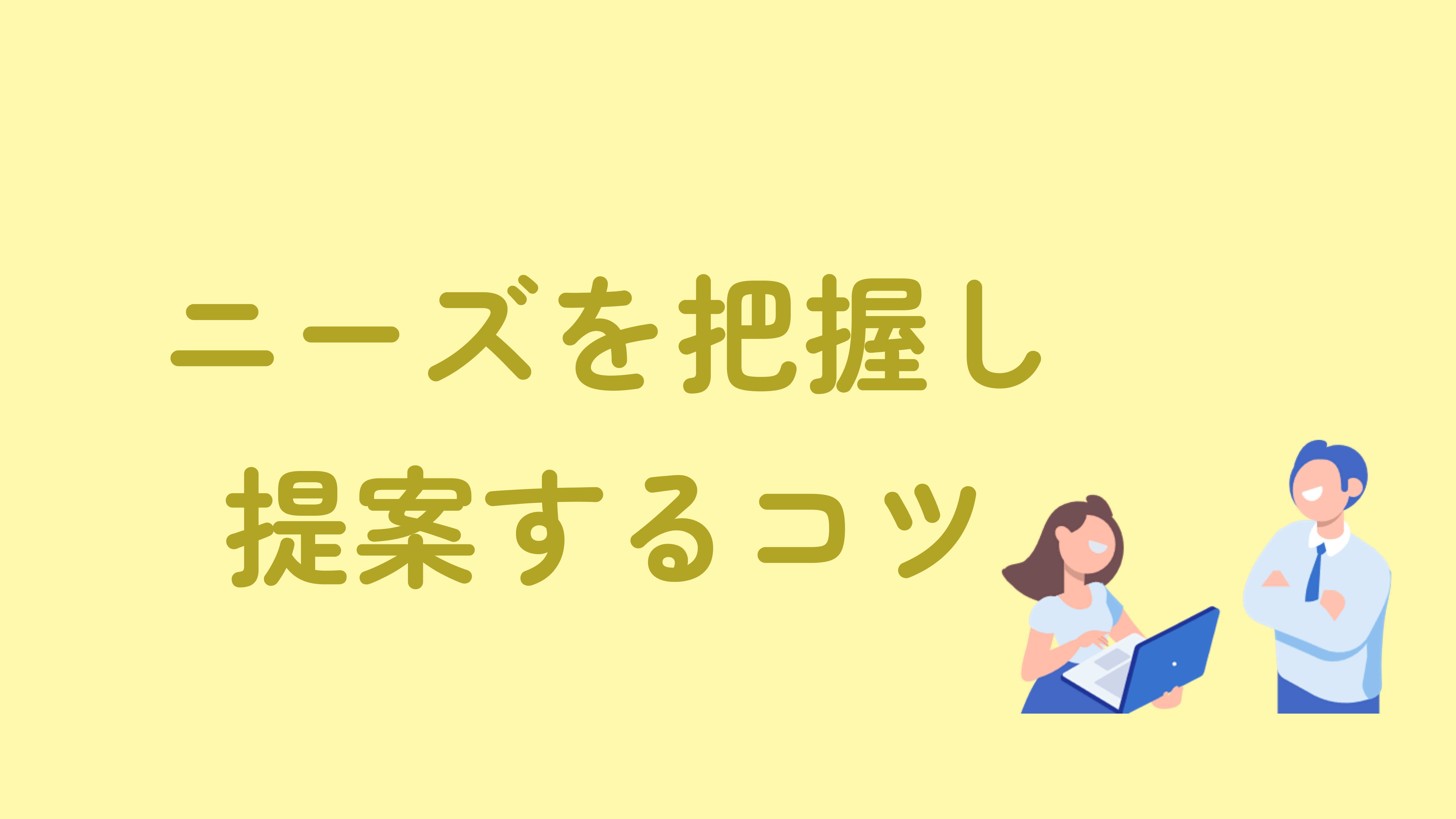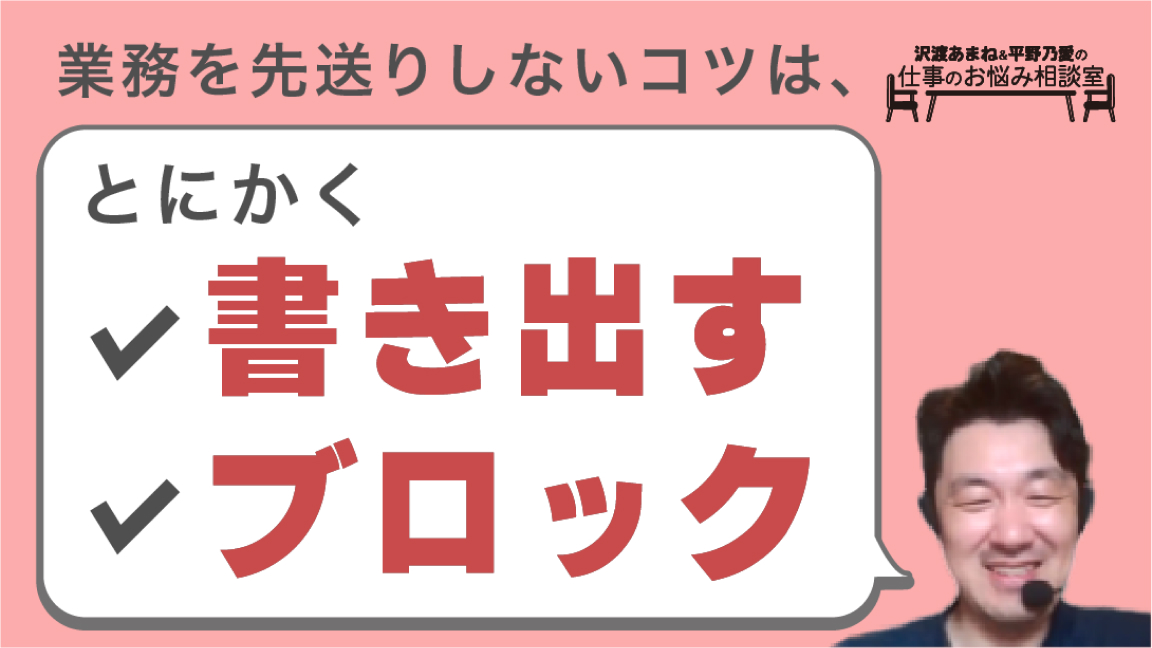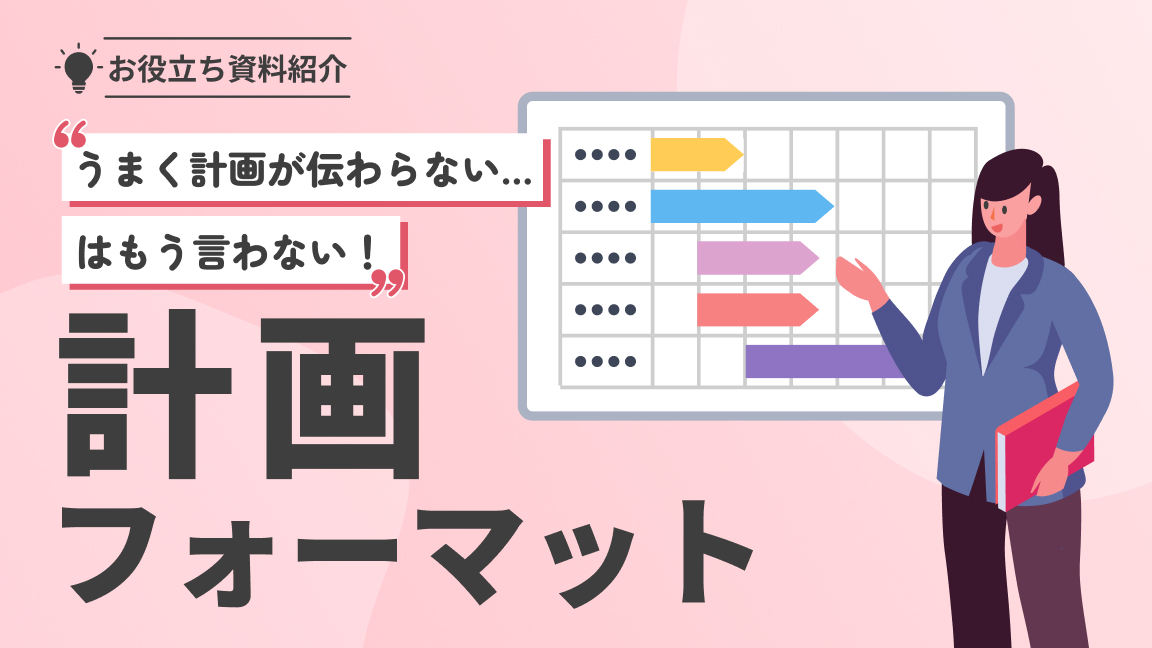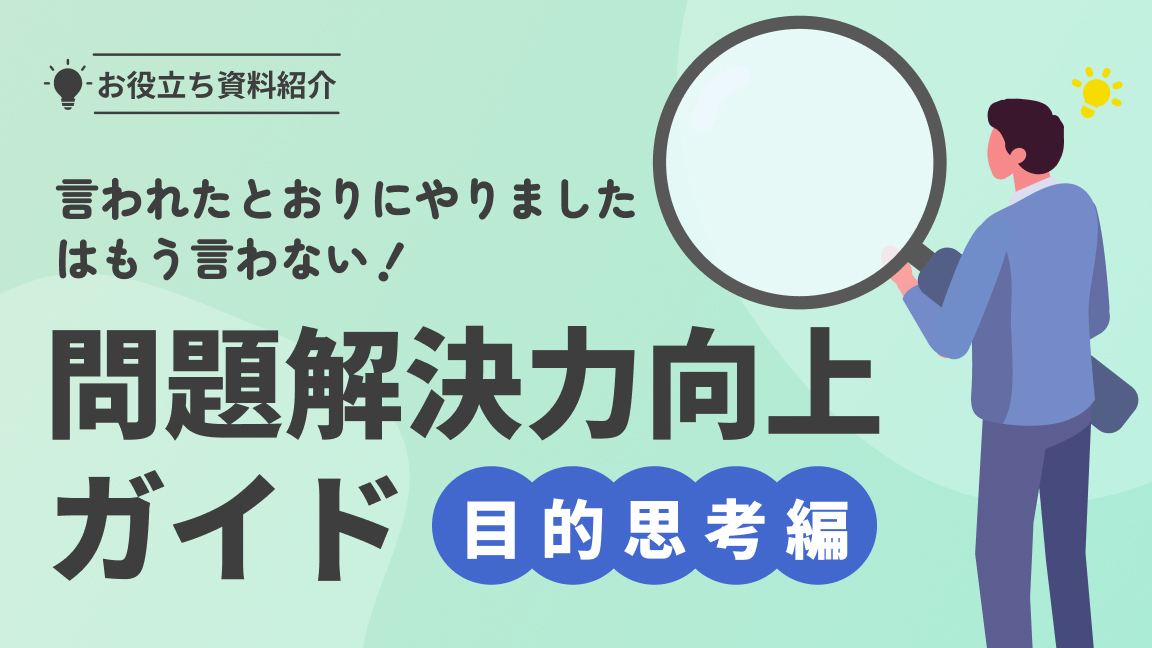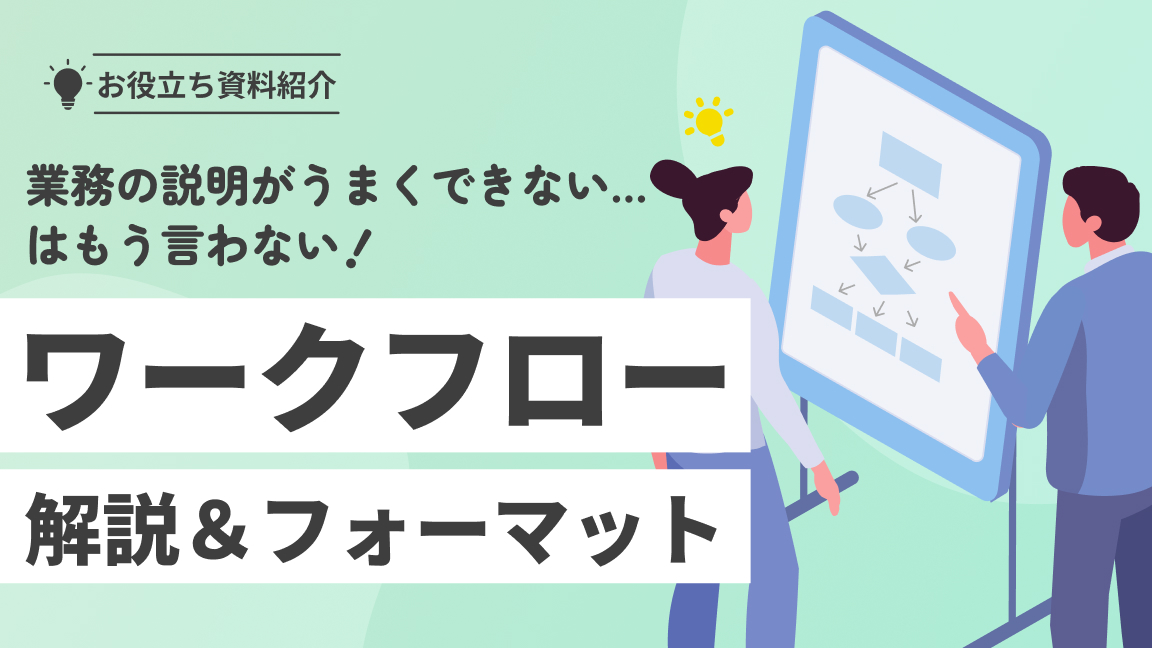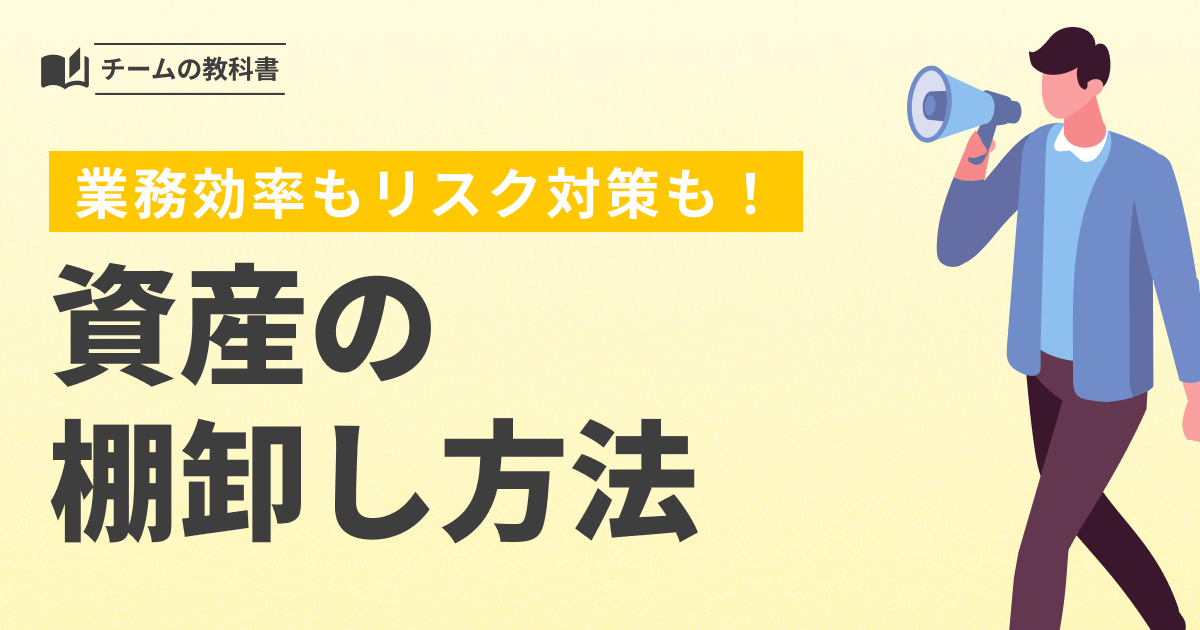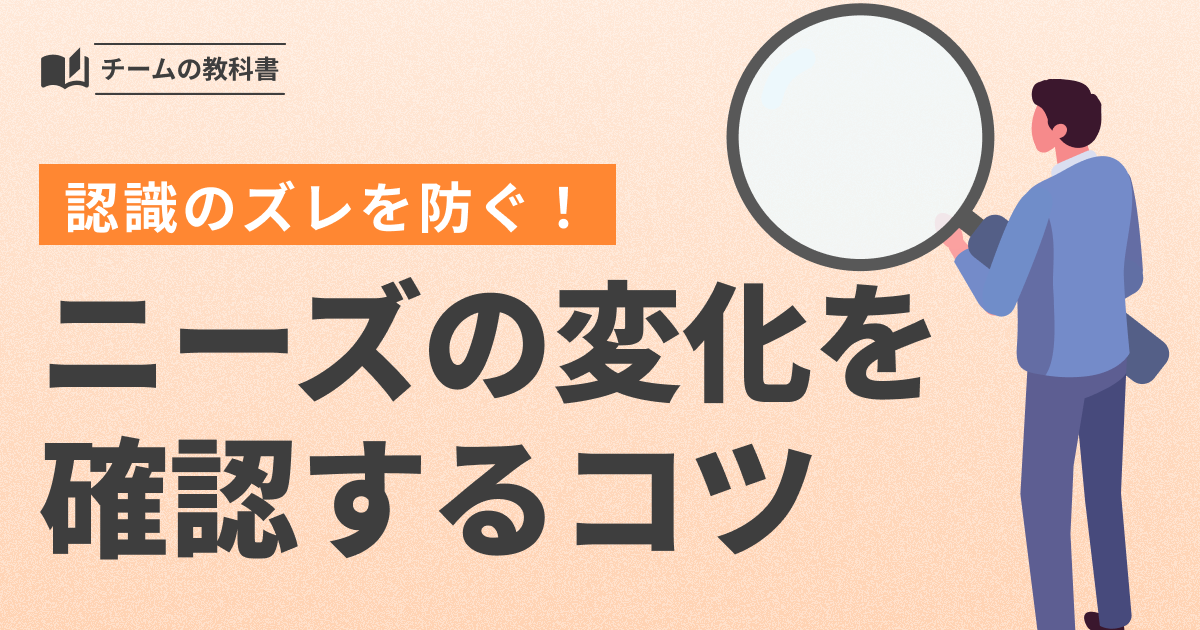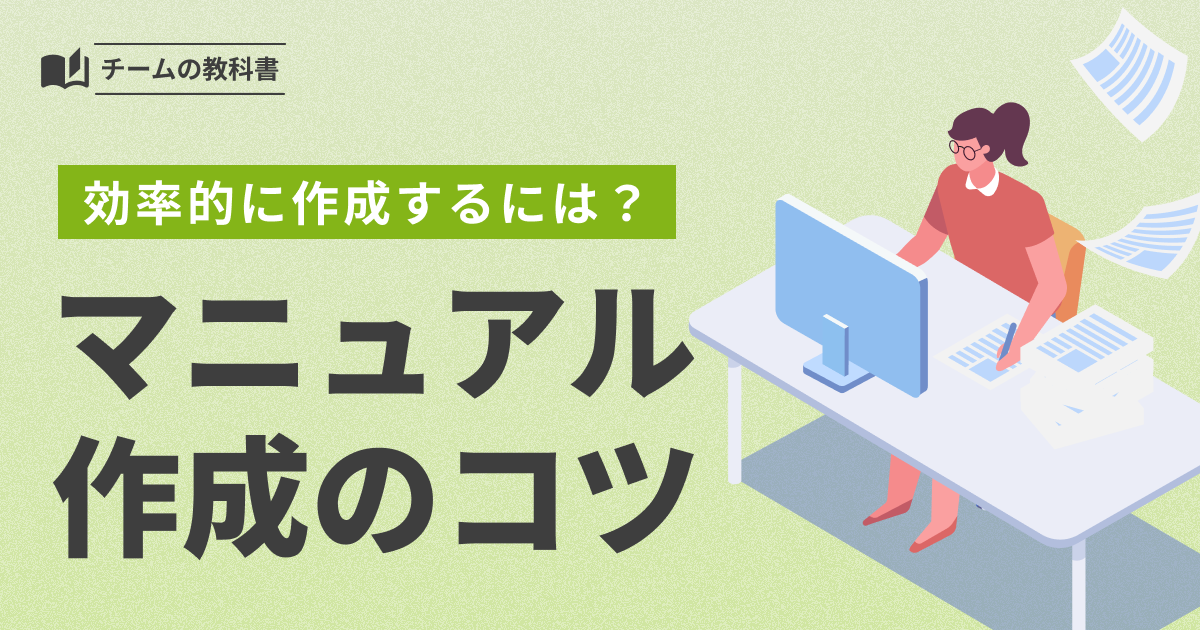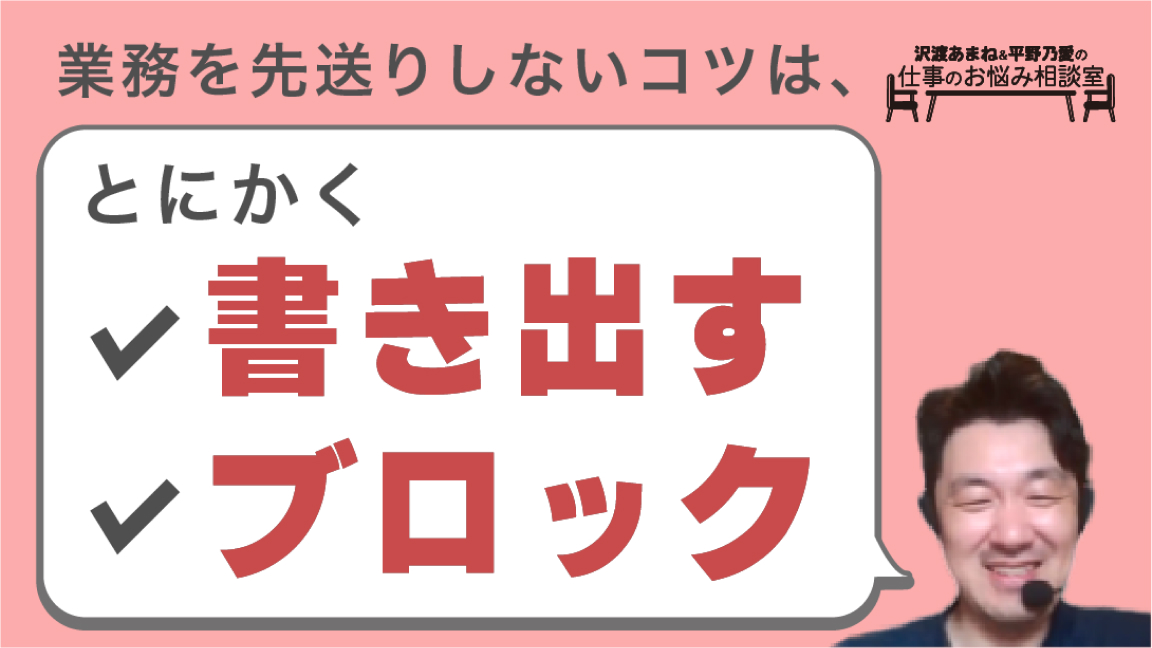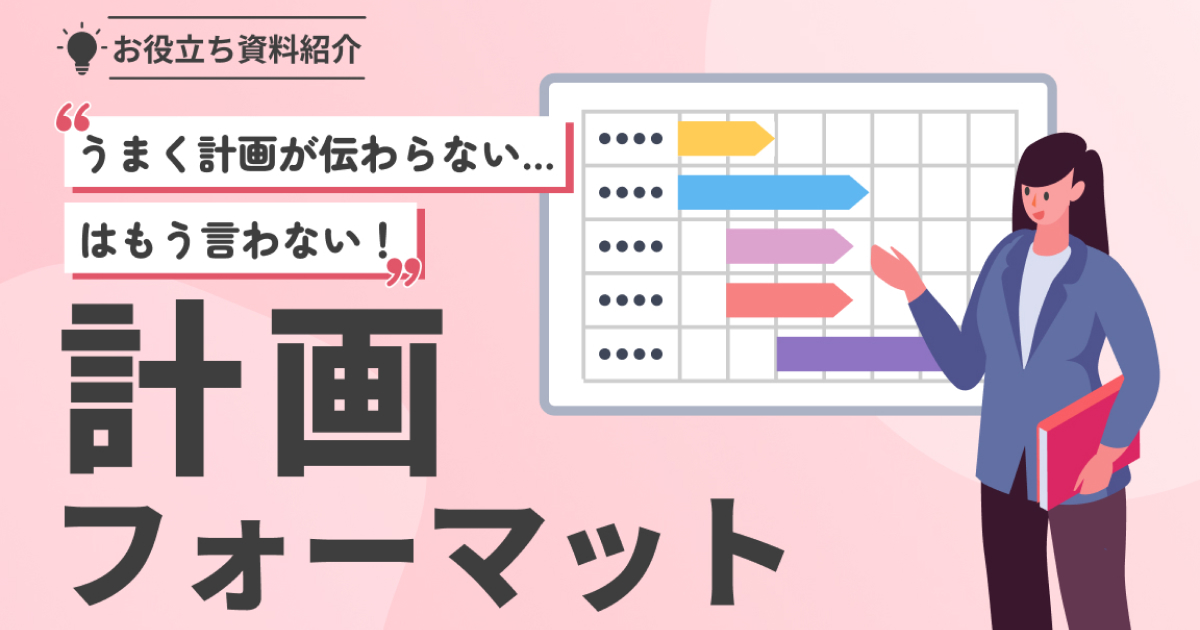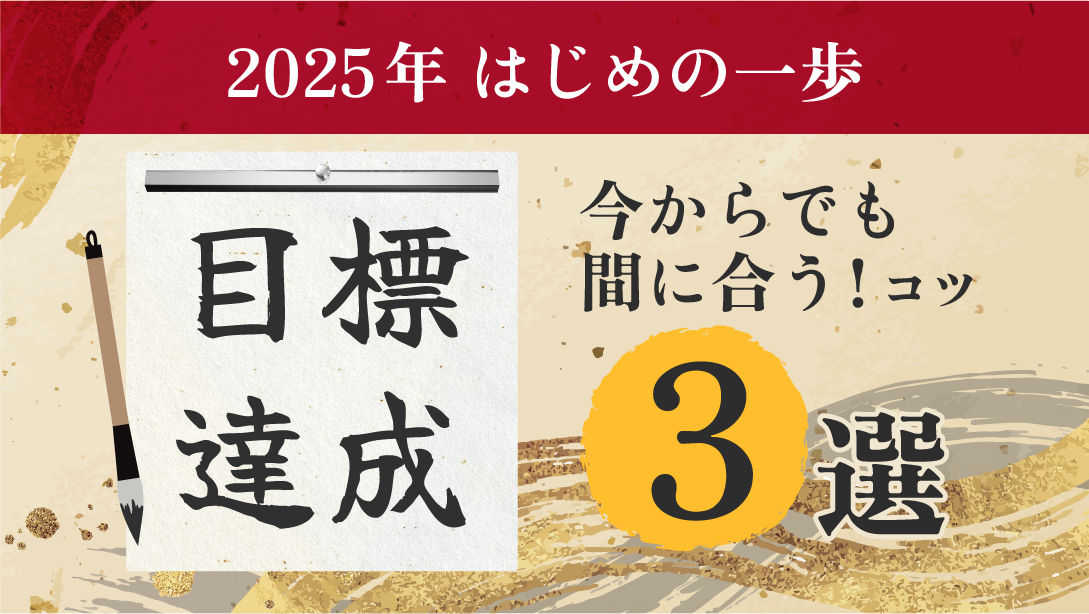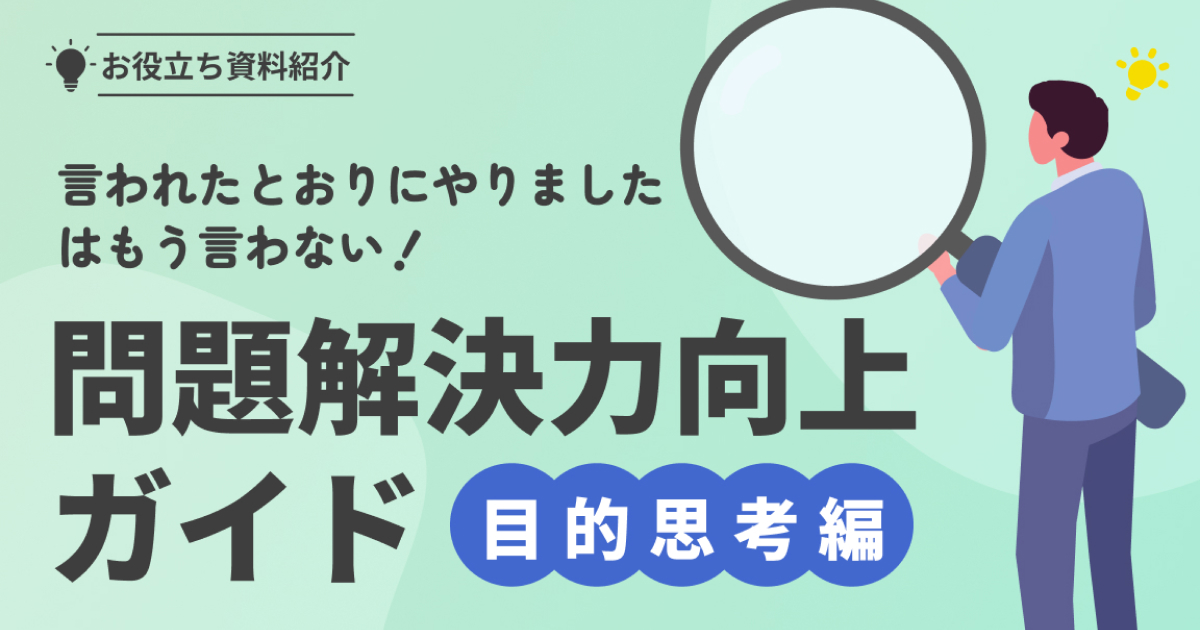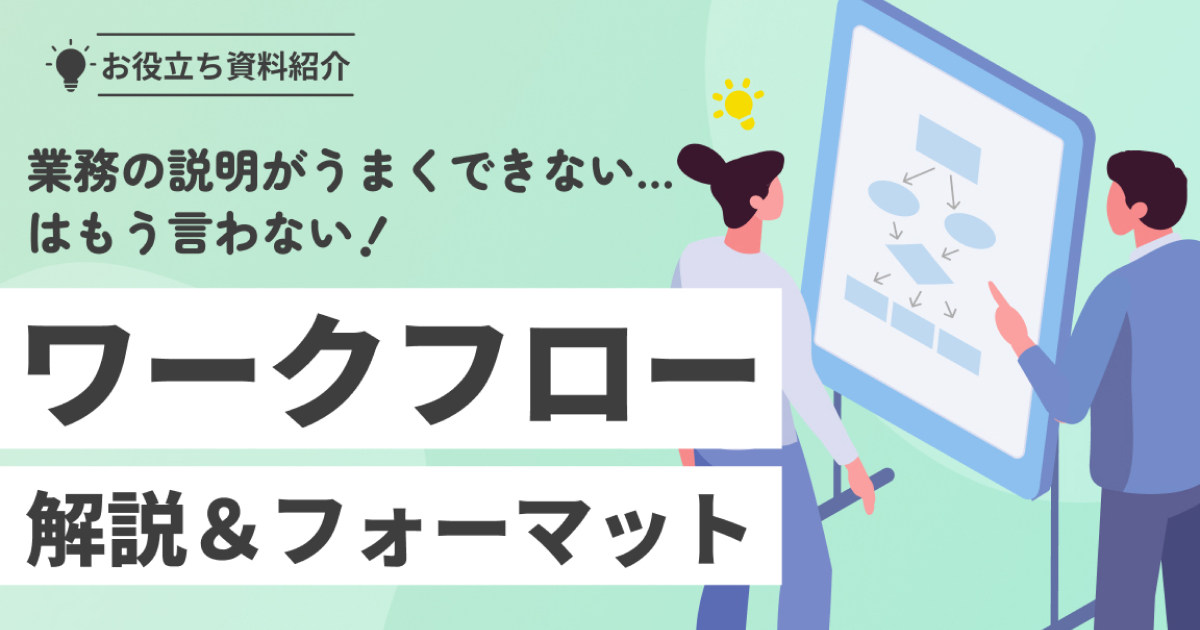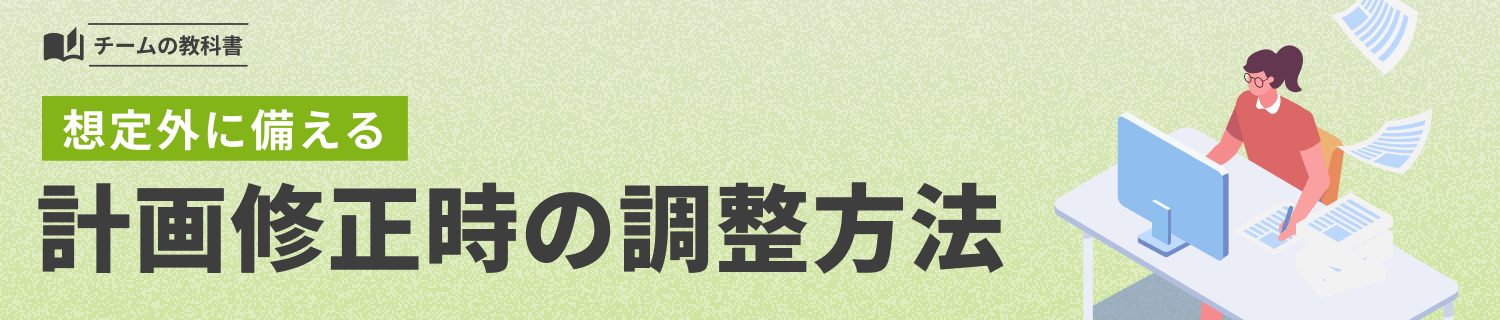
1. 業務計画と認識合わせ
業務一覧(WBS)を作成し、想定していなかった作業が必要である事や、想定している予算感やスケジュール感では対応できない事などを気づける状態を保つことが良いでしょう。
その中から許容範囲と許容できないレベルの確認を随時行ってください。
具体的に認識を合わせること
- Q:想定品質と測定方法
- C:予算と想定費用
- D:期限やスケジュールの想定
- S:想定作業量
2. 期待値調整のポイント
期待値の調整は重要ですが、ついついリスクの説明ばかりをしがちです。
そうなった場合、意図せず顧客や関係者の信頼を損ねることがあります。そらないように以下の点に注意すると良いでしょう。
- 全力で元の計画通りゴールや成果に近づけたいということを伝えながらもリスクを伝え、相手もリスクを認識してからトレードオフ案を出す
- いきなり100%のトレードオフ案ではなく、10%、20%、30%と小刻みにしたものを伝え、まずは最小対応として10%から承認を取る ※1
※1:人はいきなり大きな影響やリスクのあることを決断できません。
ただ、一度決断するとその後、そのレベルが上がっても同様の決断をしやすくなります。
考えたトレードオフ案のリスクや影響があまりに大きい場合は、全体を見せた上でより小さな範囲から承認をもらうように交渉するとスムーズに進む場合があります。
また、自分たちが考えたトレードオフ案も実際は正しいかどうか、どれほど効果があるか分からない、
という場合も小さな範囲で進めることでその後の更なる計画修正も容易になります。
3. トレードオフ案と説明の工夫
期待値の調整(特にトレードオフ案の提示)の場合、相手が関心あるのは圧倒的に「これからどうなるか?」という未来の話です。
なのに多くの人が「なぜ計画が乖離したか?」「現状がどうなっているか?」を説明することに必死になりがちです。
たしかに正しく現状と発生している問題を認識することは的確な修正計画を策定する上で重要ですが、
顧客や関係者にとって重要なのはその修正計画とそれによる影響です。
期待値調整に失敗する人のほとんどは、この勘違いをしているパターンが多いです。
特に自身で判断をする決裁者でそのレベルが上がれば上がるほどにより未来の話への関心が高まります。
相手の立場、役職に応じて経緯、原因、修正計画、影響のどこに比重を置いて会話するかを見極め、使い分けましょう。※2
※2:決裁者のレベルが上がるにつれて経緯>原因>修正計画>影響と関心が移っていきます。
4. 関連資料
おすすめ動画
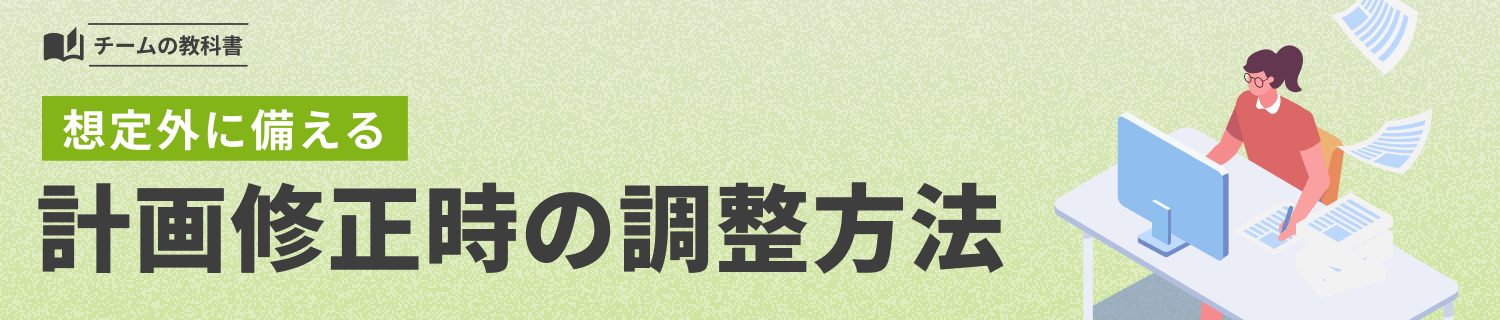
1. 業務計画と認識合わせ
業務一覧(WBS)を作成し、想定していなかった作業が必要である事や、想定している予算感やスケジュール感では対応できない事などを気づける状態を保つことが良いでしょう。
その中から許容範囲と許容できないレベルの確認を随時行ってください。
具体的に認識を合わせること
- Q:想定品質と測定方法
- C:予算と想定費用
- D:期限やスケジュールの想定
- S:想定作業量
2. 期待値調整のポイント
期待値の調整は重要ですが、ついついリスクの説明ばかりをしがちです。
そうなった場合、意図せず顧客や関係者の信頼を損ねることがあります。そらないように以下の点に注意すると良いでしょう。
- 全力で元の計画通りゴールや成果に近づけたいということを伝えながらもリスクを伝え、相手もリスクを認識してからトレードオフ案を出す
- いきなり100%のトレードオフ案ではなく、10%、20%、30%と小刻みにしたものを伝え、まずは最小対応として10%から承認を取る ※1
※1:人はいきなり大きな影響やリスクのあることを決断できません。
ただ、一度決断するとその後、そのレベルが上がっても同様の決断をしやすくなります。
考えたトレードオフ案のリスクや影響があまりに大きい場合は、全体を見せた上でより小さな範囲から承認をもらうように交渉するとスムーズに進む場合があります。
また、自分たちが考えたトレードオフ案も実際は正しいかどうか、どれほど効果があるか分からない、
という場合も小さな範囲で進めることでその後の更なる計画修正も容易になります。
3. トレードオフ案と説明の工夫
期待値の調整(特にトレードオフ案の提示)の場合、相手が関心あるのは圧倒的に「これからどうなるか?」という未来の話です。
なのに多くの人が「なぜ計画が乖離したか?」「現状がどうなっているか?」を説明することに必死になりがちです。
たしかに正しく現状と発生している問題を認識することは的確な修正計画を策定する上で重要ですが、
顧客や関係者にとって重要なのはその修正計画とそれによる影響です。
期待値調整に失敗する人のほとんどは、この勘違いをしているパターンが多いです。
特に自身で判断をする決裁者でそのレベルが上がれば上がるほどにより未来の話への関心が高まります。
相手の立場、役職に応じて経緯、原因、修正計画、影響のどこに比重を置いて会話するかを見極め、使い分けましょう。※2
※2:決裁者のレベルが上がるにつれて経緯>原因>修正計画>影響と関心が移っていきます。
4. 関連資料