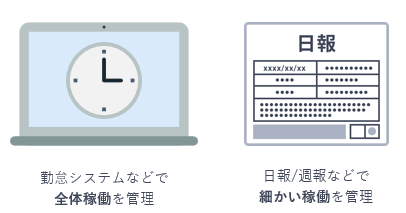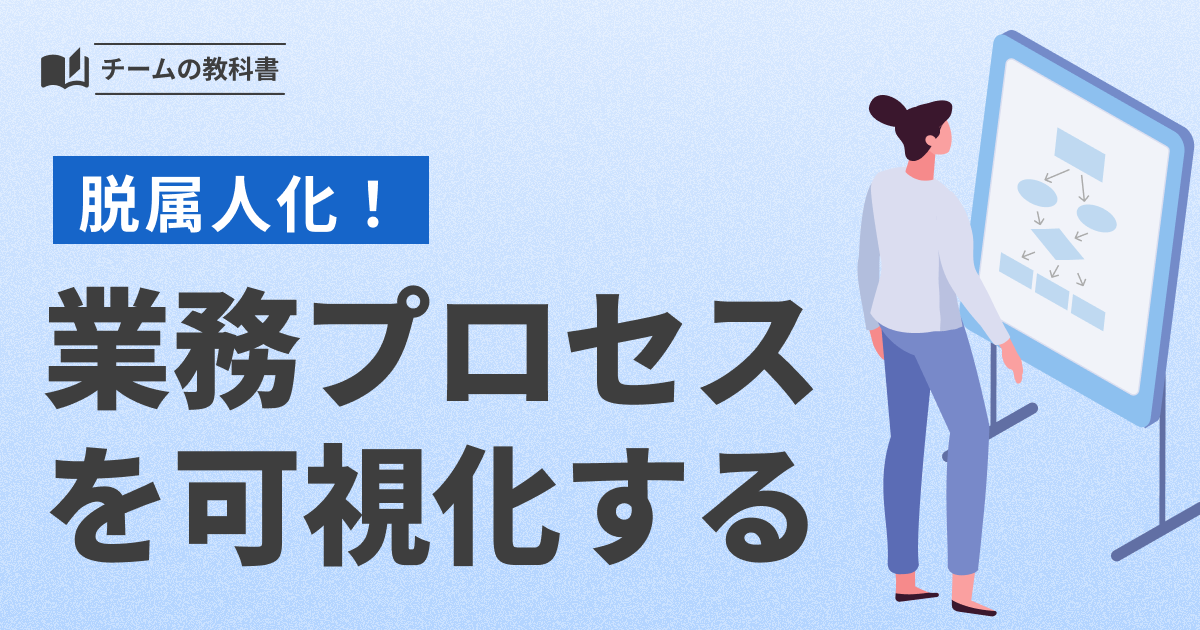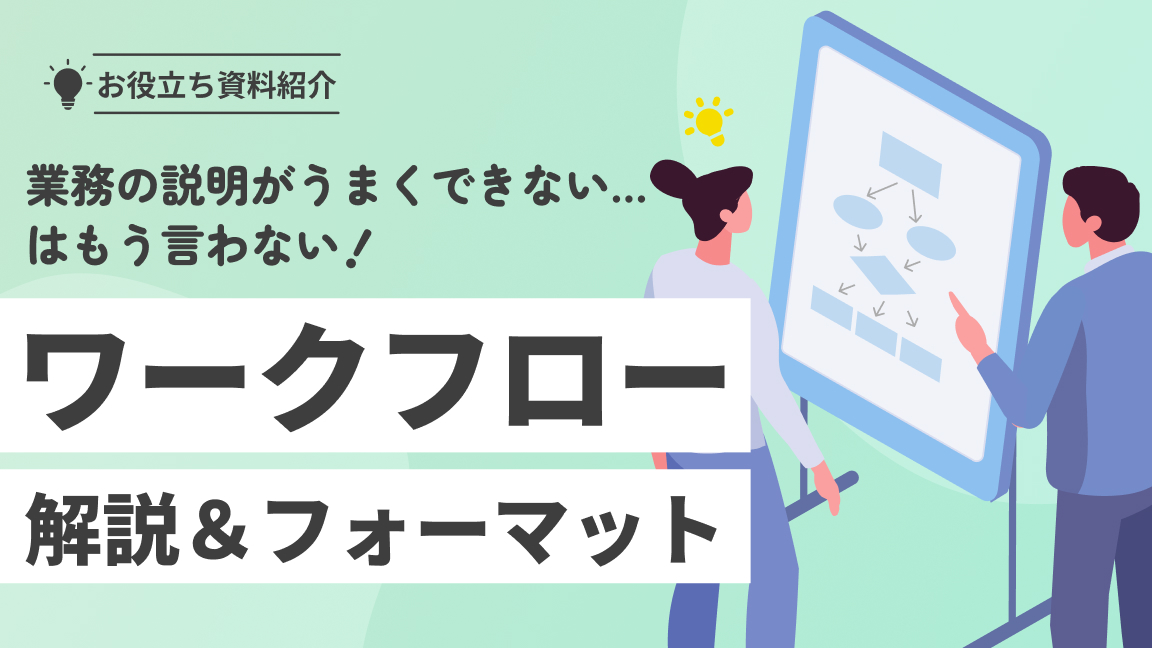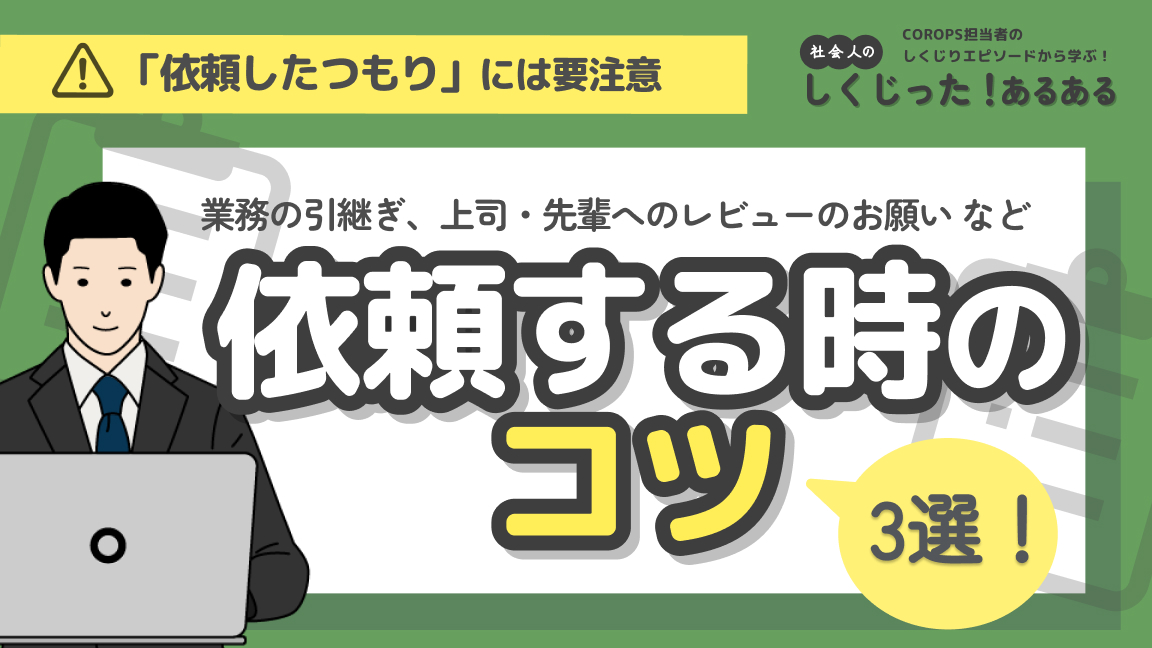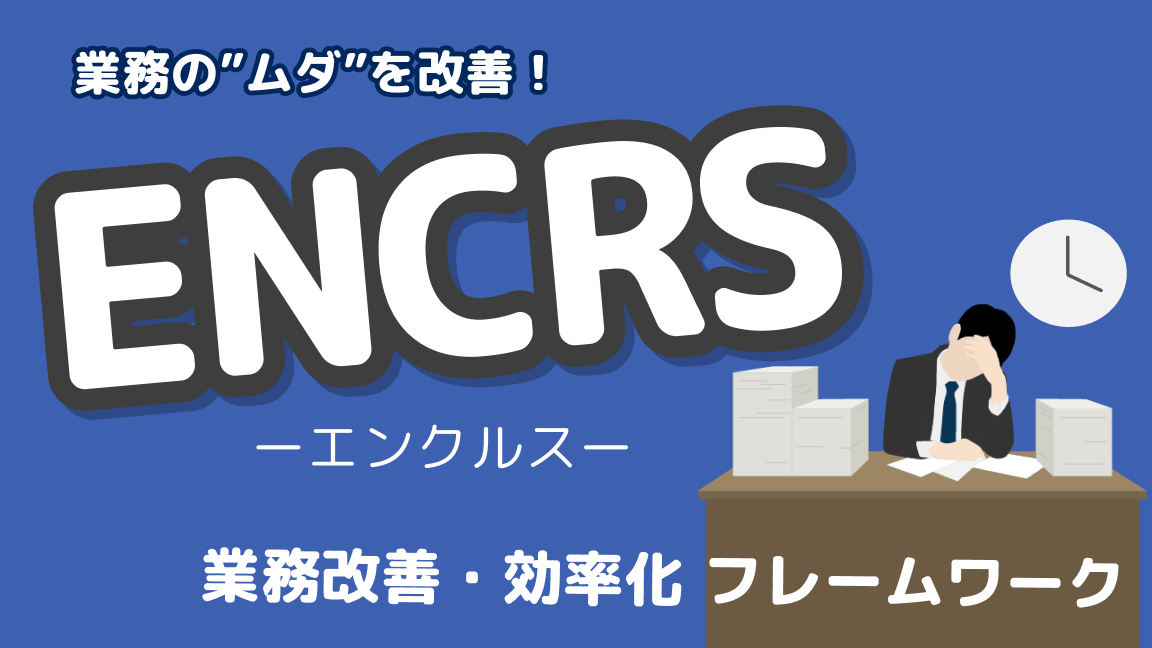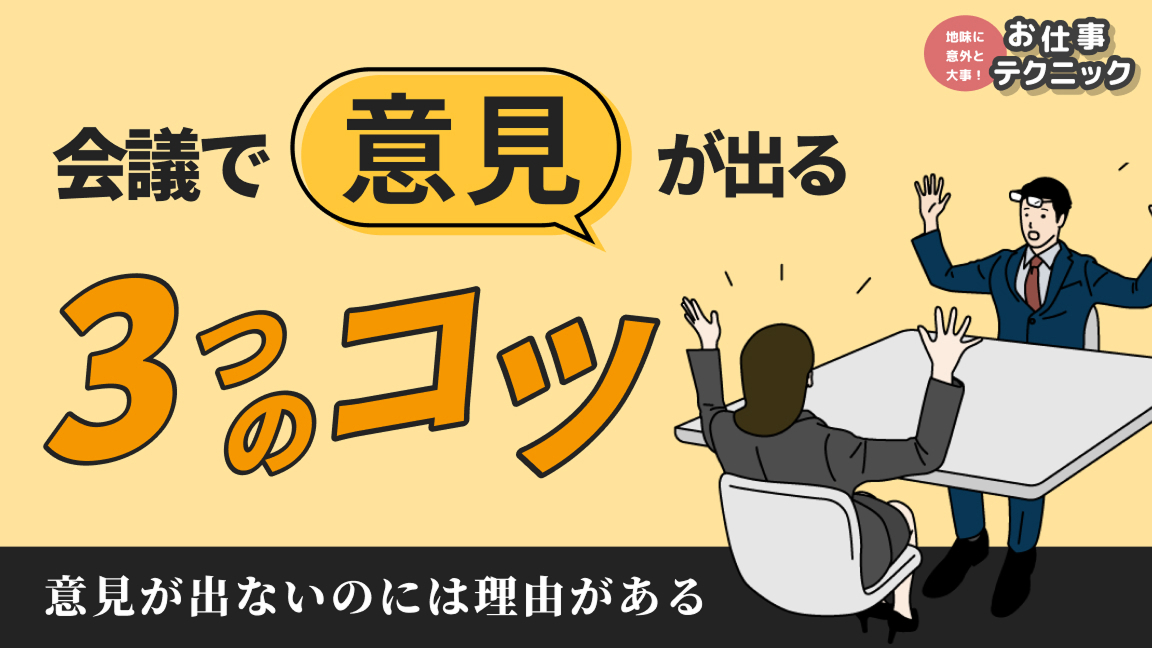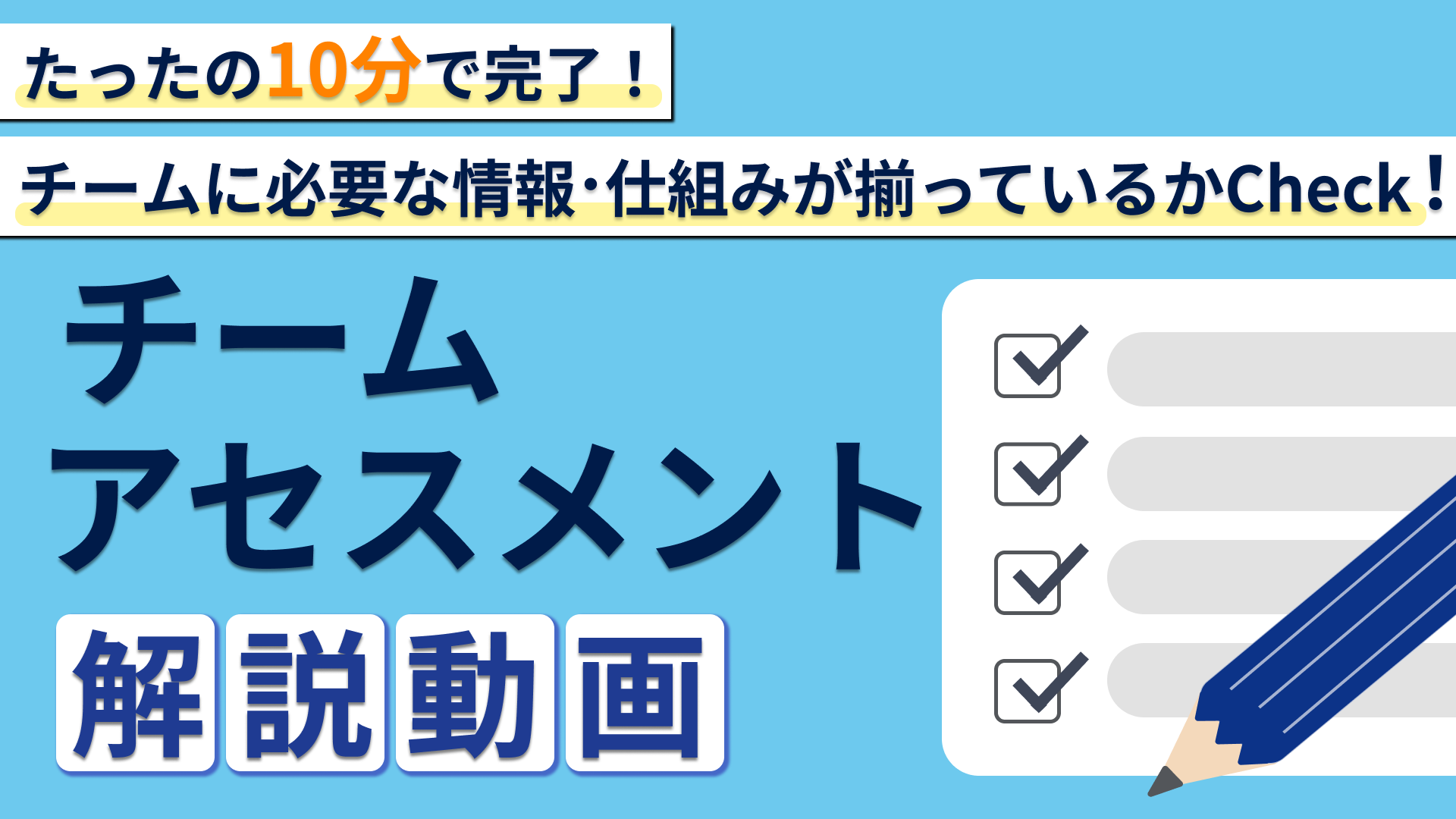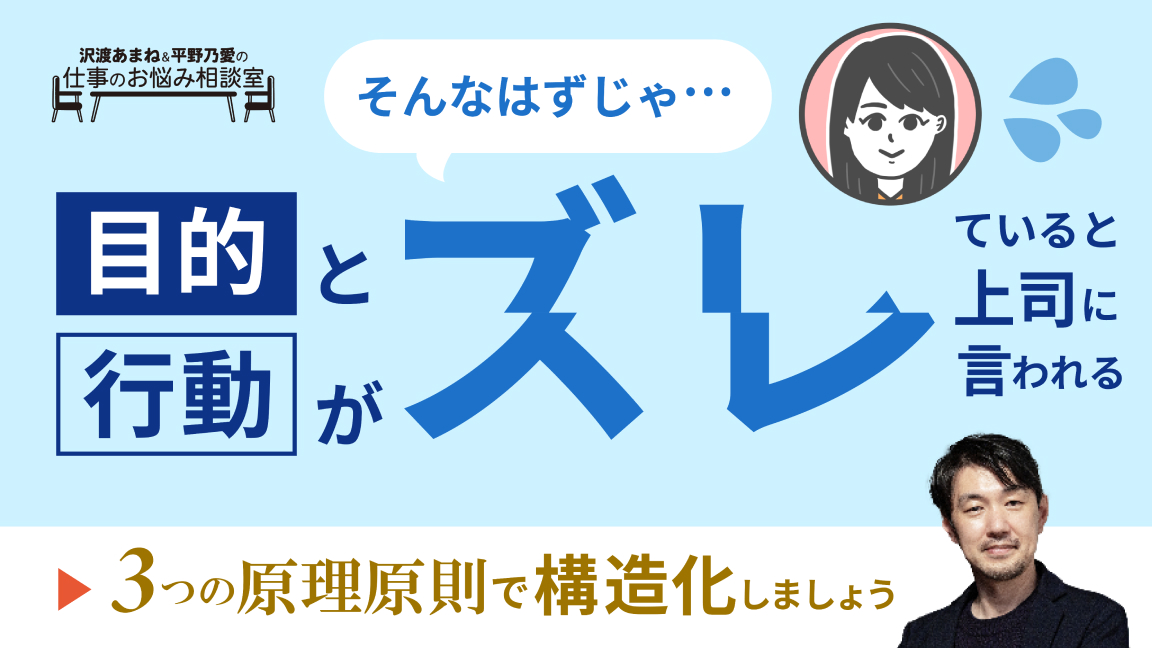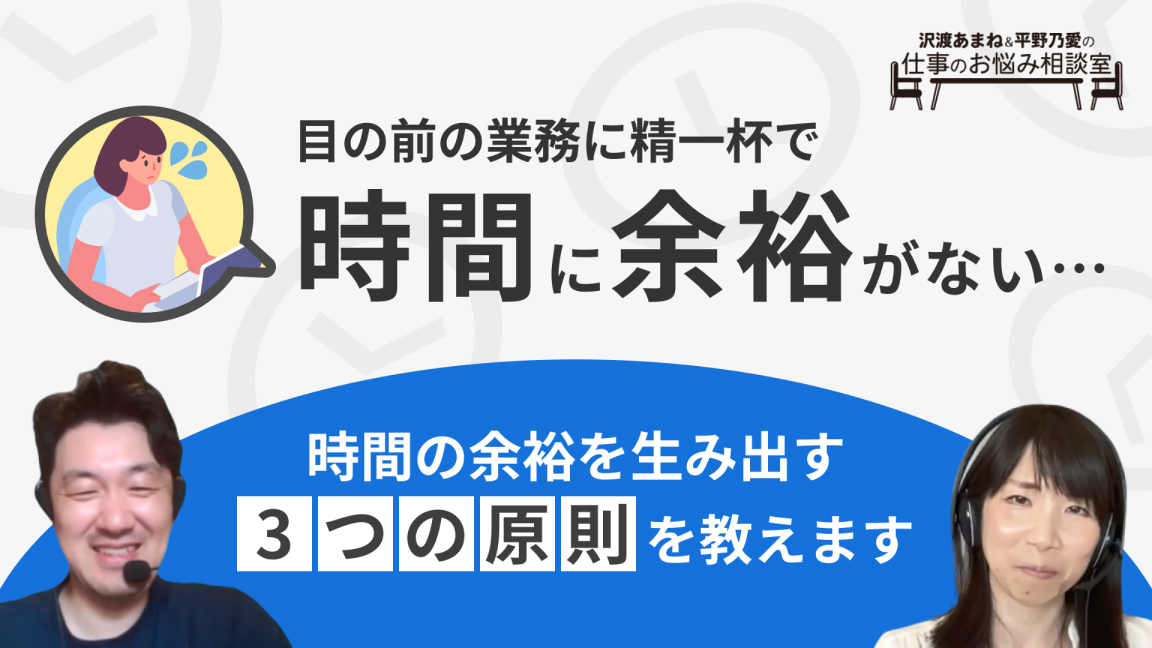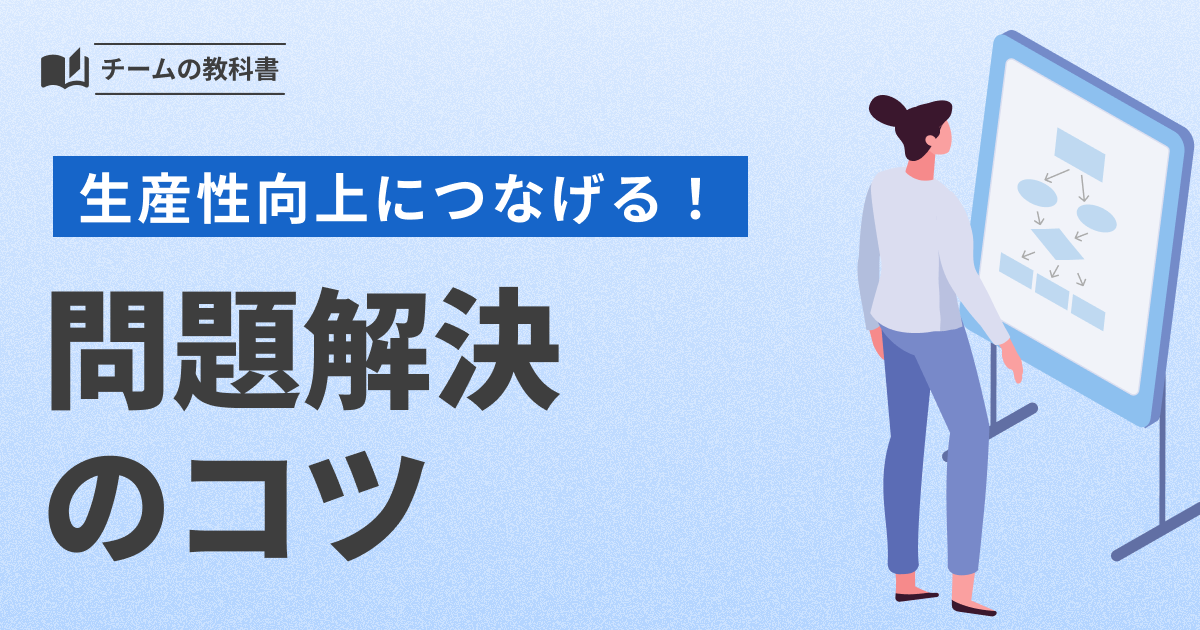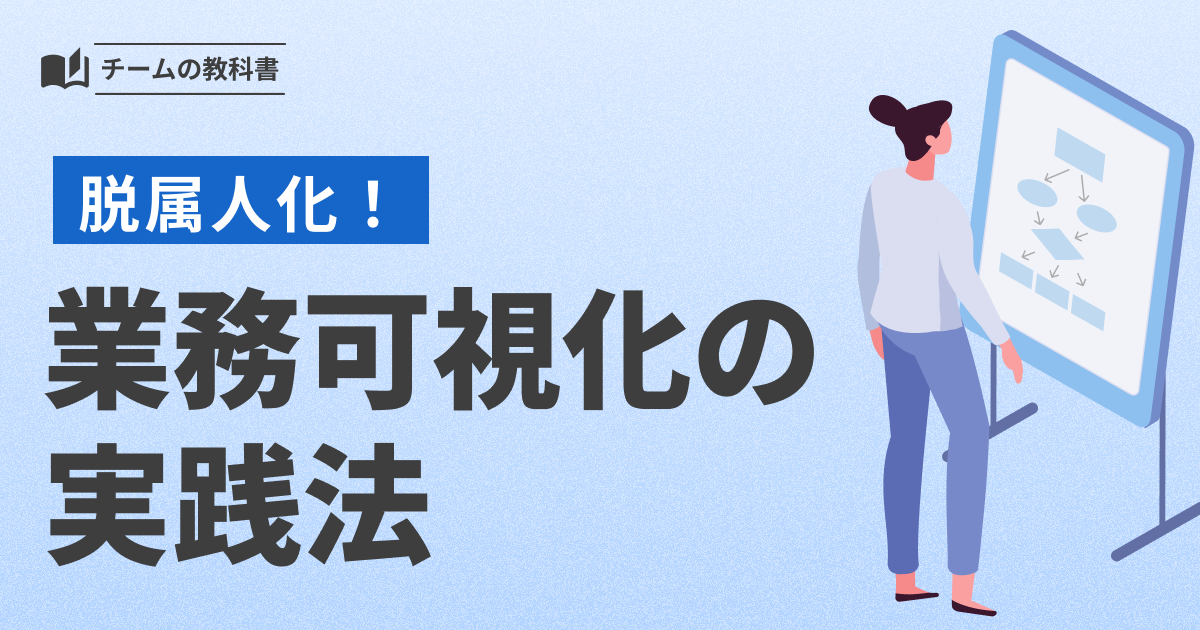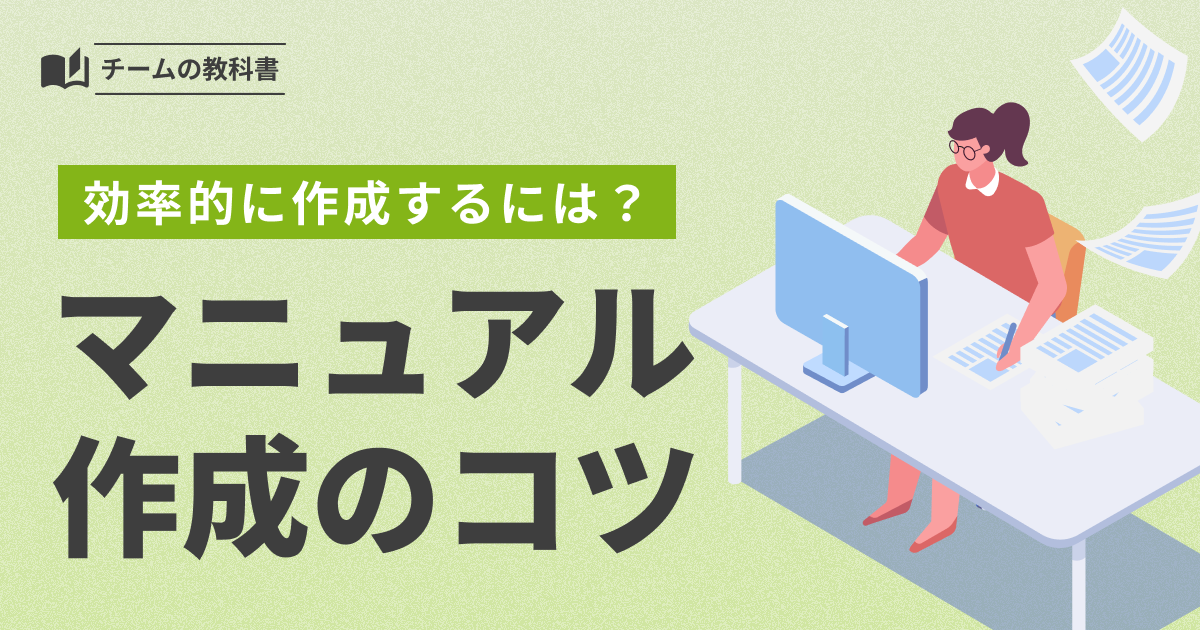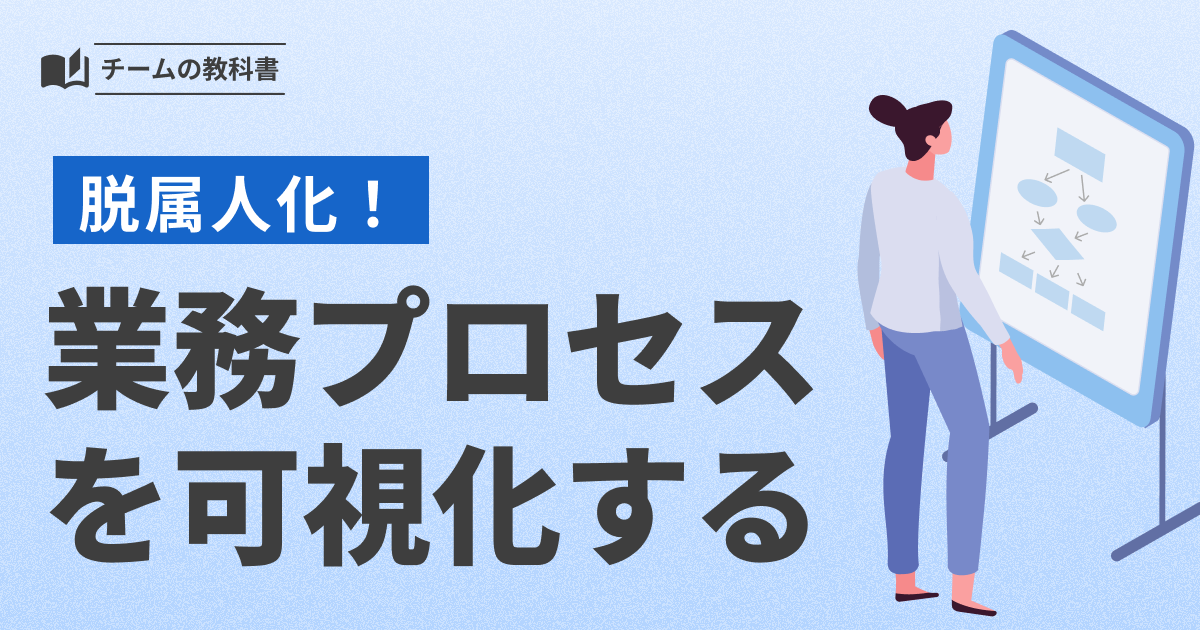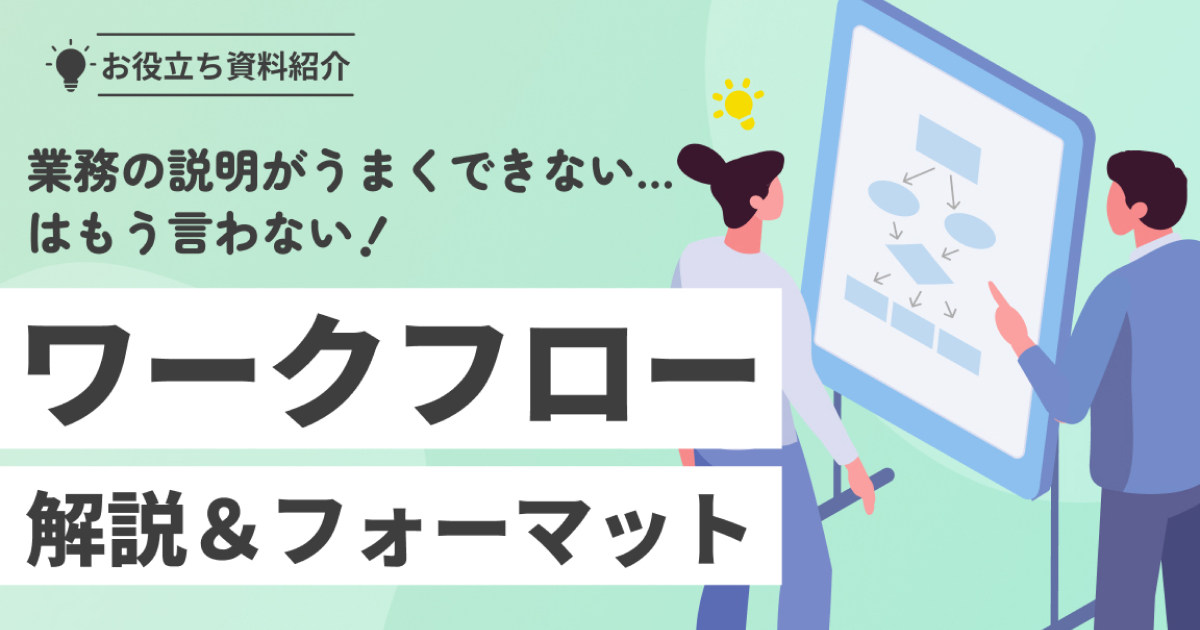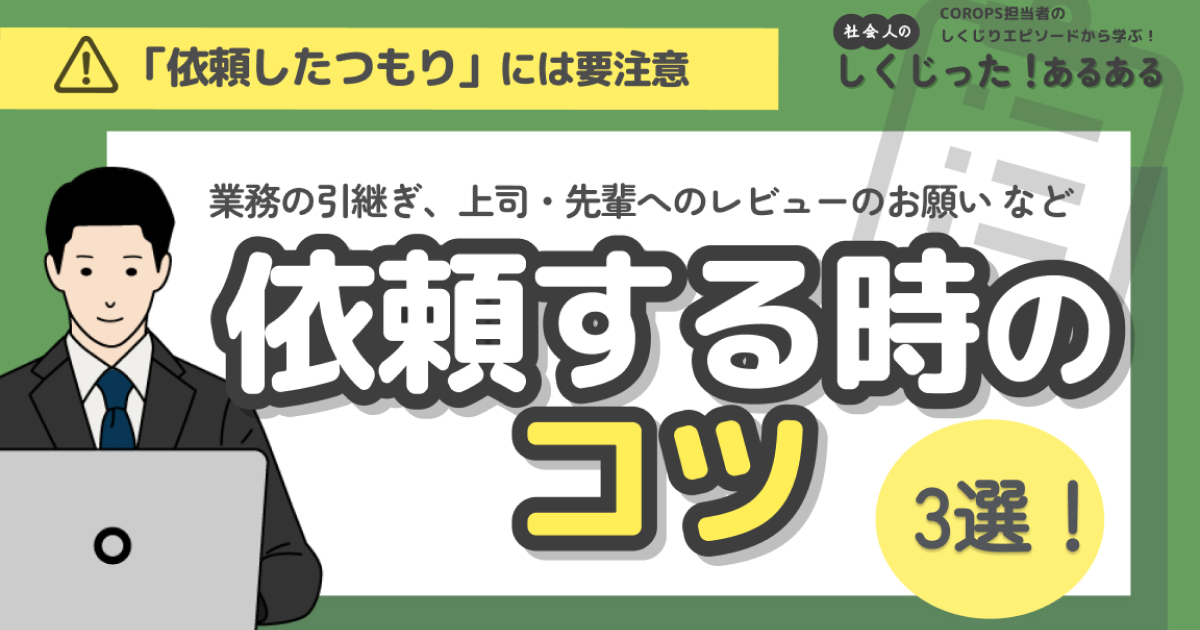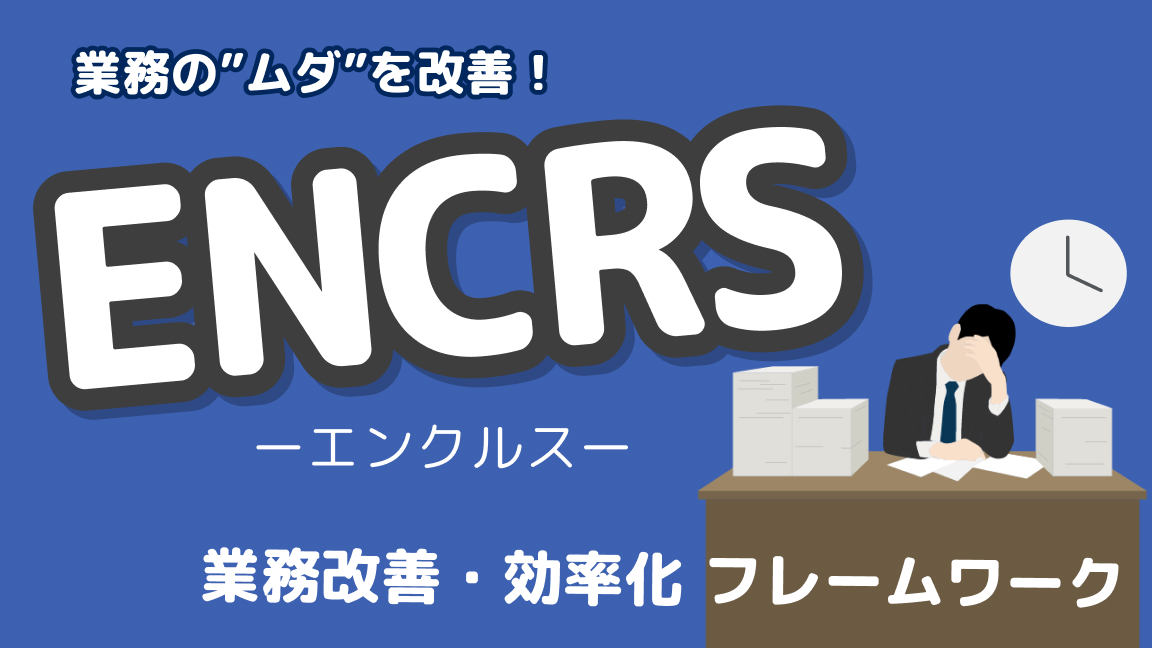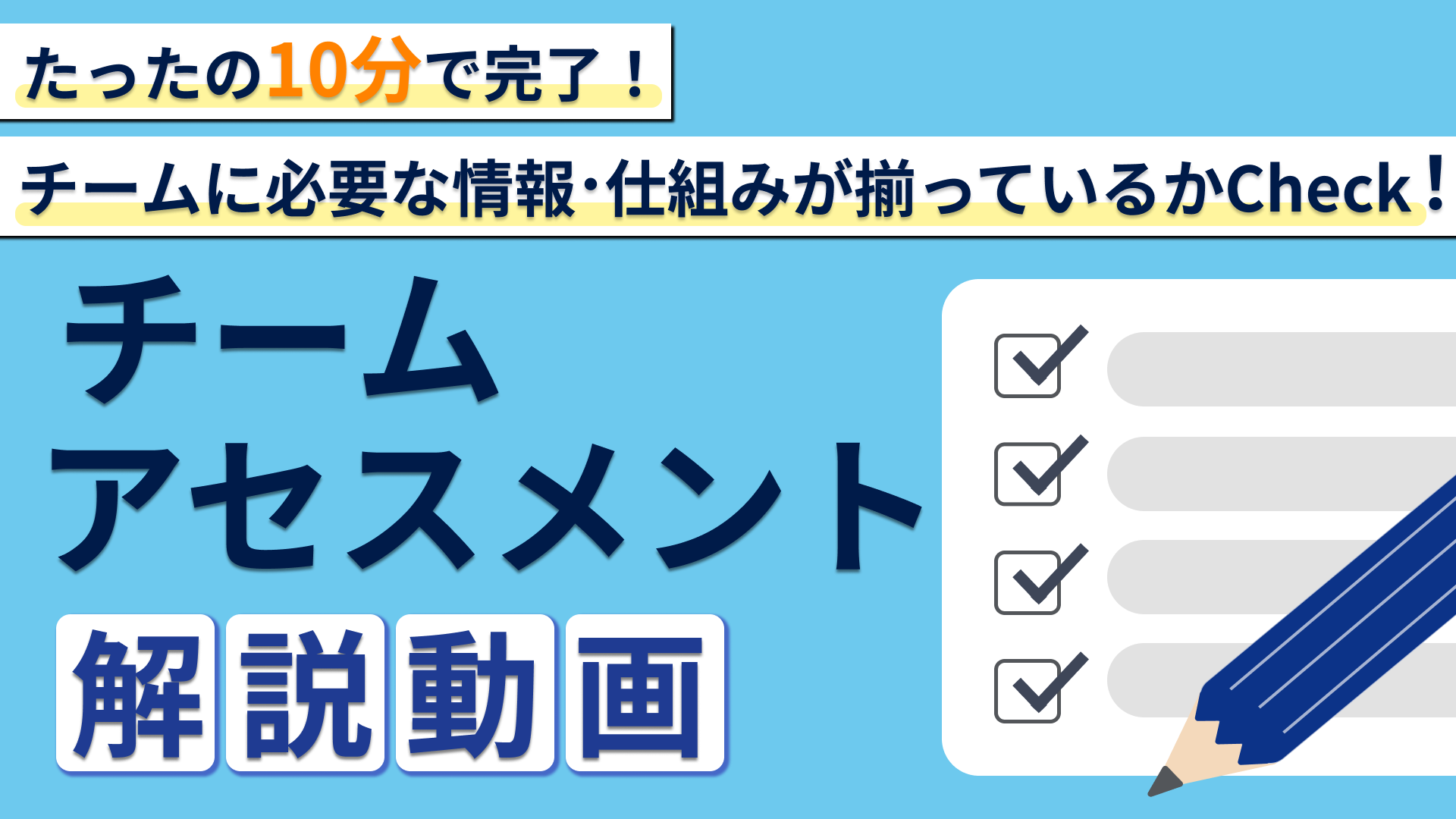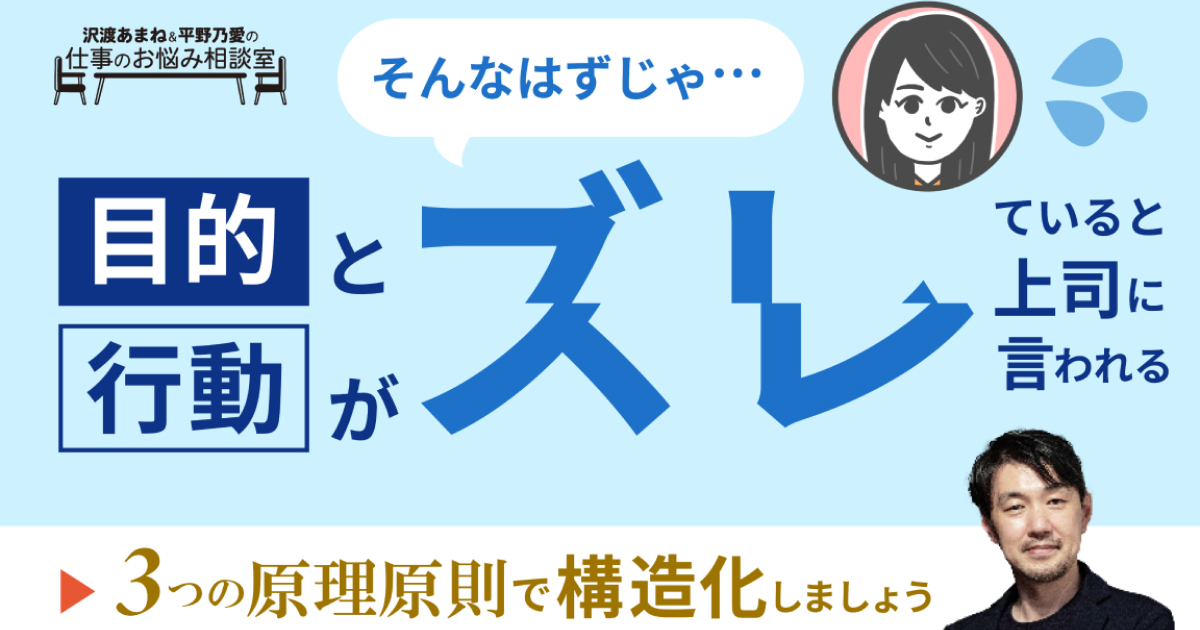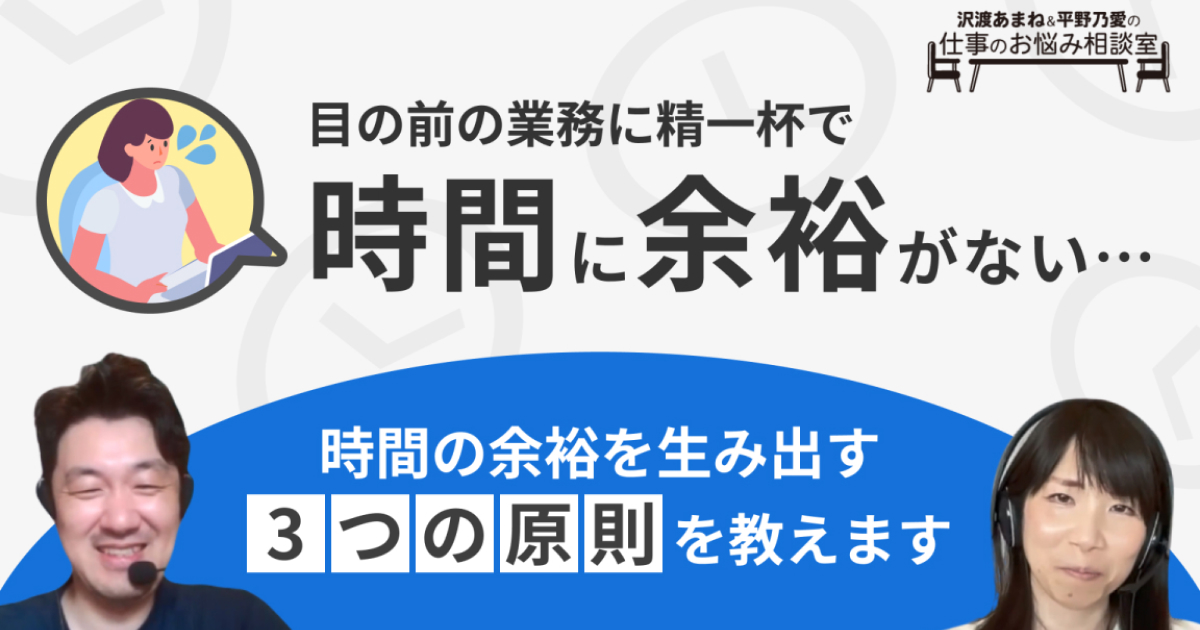チーム運営を強化する稼働管理の基本
業務の改善
チームの生産性を高め、適切なリソース配分や改善活動につなげるためには、
まず「稼働状況の把握」が欠かせません。 しかし、いきなり細かな作業単位で工数を洗い出すのは非効率です。
そこでまずは全体の稼働バランスを捉え、目的に応じた粒度で工数を測定し、実績との差分を定期的に確認していきましょう。
この記事では、稼働管理の基本から、工数の算出方法、実績の確認ポイントまで、
業務を「見える化し管理する」ためのステップをわかりやすく解説します。
1.稼働管理:まずは全体観を掴む
業務の稼働状況を把握する際、最初から一人一人が細かい作業単位で時間を算出するのは避けましょう。
まずは以下のような粒度で、チーム全体の稼働割合を把握することから始めます。
稼働内訳の例
①業務遂行(オペレーション)
②業務管理(ミーティング、数値管理など)
③業務改善活動(提案・標準化など)
一般的に、③の改善活動に15%のリソースを確保できる状態が理想とされています。
チームの成熟度(※)に応じて比率を調整していくことが重要です。
※タックマンモデル:形成期、混乱期、統一期、機能期、散会期を参考に、改善に割く時間を調整しましょう。
|
|
2.業務工数の算出:目的に応じた粒度で計測
チーム稼働の全体像を把握した上で、業務に必要な人や時間を計算していきます。
これを行うことで、増員判断やパフォーマンス改善に役立てることができます。
目的に応じて、どの単位で計測するかを明確にしましょう。
まずは大きな単位で測定を始め、必要に応じて細かい作業単位へと移行するのが効率的です。
計測方法の例
時間単位管理(例:1時間ごと)
目的:業務の大まかな配分を把握する
活用例:チーム全体の稼働割合の確認、業務カテゴリ別の傾向分析
ツール例:Outlook、Excelで実績入力
分単位管理(例:5分〜15分単位)※必要に応じて管理
目的:業務の細部を分析し、改善や効率化に活かす
活用例:ボトルネックの特定、原価管理、請求精度向上、ツール導入効果の検証
ツール例:タイマー、専用工数管理ツール
3. 稼働状況の把握:予定と実績の差分を定期的に確認
稼働状況の正確な把握には、当初の計画(予定工数)と実際の稼働(実績)との比較が不可欠です。
チェックポイント
- 工数の入力:勤怠システムや工数管理表を活用
- 実績の確認:計画との乖離や残業状況を把握
- 残業理由の確認:困っていることを具体的にヒアリング
- 業務の再配分:周囲との連携で負荷を調整
心理的に悪い状況を積極的に共有するのは気が引けるものです。
そのため、たとえ上司や先輩に、”大丈夫か?”問われたとしても、「まだ大丈夫です」と答えてしまう人が多いです。
状況は主観的な報告に頼らず、客観的なデータを把握することが必要不可欠です。
可能であれば毎日、少なくとも数日に一度は、チームメンバーの1日の総勤務時間を確認を基本としましょう。
まとめ
チーム運営において稼働・工数の「可視化と管理」は生産性向上の鍵です。
チーム全体のパフォーマンスを継続的に底上げすることができます。
関連資料
▶▶【📅ファイル】メンバー稼働管理表のダウンロード はこちら
▶▶【📅ファイル】工数推移(月・年単位)管理表のダウンロード はこちら
会員限定コンテンツで
仕事を進めやすくするヒントが見つかる!
おすすめ動画
チーム運営を強化する稼働管理の基本
業務の改善
チームの生産性を高め、適切なリソース配分や改善活動につなげるためには、
まず「稼働状況の把握」が欠かせません。 しかし、いきなり細かな作業単位で工数を洗い出すのは非効率です。
そこでまずは全体の稼働バランスを捉え、目的に応じた粒度で工数を測定し、実績との差分を定期的に確認していきましょう。
この記事では、稼働管理の基本から、工数の算出方法、実績の確認ポイントまで、
業務を「見える化し管理する」ためのステップをわかりやすく解説します。
1.稼働管理:まずは全体観を掴む
業務の稼働状況を把握する際、最初から一人一人が細かい作業単位で時間を算出するのは避けましょう。
まずは以下のような粒度で、チーム全体の稼働割合を把握することから始めます。
稼働内訳の例
①業務遂行(オペレーション)
②業務管理(ミーティング、数値管理など)
③業務改善活動(提案・標準化など)
一般的に、③の改善活動に15%のリソースを確保できる状態が理想とされています。
チームの成熟度(※)に応じて比率を調整していくことが重要です。
※タックマンモデル:形成期、混乱期、統一期、機能期、散会期を参考に、改善に割く時間を調整しましょう。
|
|
2.業務工数の算出:目的に応じた粒度で計測
チーム稼働の全体像を把握した上で、業務に必要な人や時間を計算していきます。
これを行うことで、増員判断やパフォーマンス改善に役立てることができます。
目的に応じて、どの単位で計測するかを明確にしましょう。
まずは大きな単位で測定を始め、必要に応じて細かい作業単位へと移行するのが効率的です。
計測方法の例
時間単位管理(例:1時間ごと)
目的:業務の大まかな配分を把握する
活用例:チーム全体の稼働割合の確認、業務カテゴリ別の傾向分析
ツール例:Outlook、Excelで実績入力
分単位管理(例:5分〜15分単位)※必要に応じて管理
目的:業務の細部を分析し、改善や効率化に活かす
活用例:ボトルネックの特定、原価管理、請求精度向上、ツール導入効果の検証
ツール例:タイマー、専用工数管理ツール
3. 稼働状況の把握:予定と実績の差分を定期的に確認
稼働状況の正確な把握には、当初の計画(予定工数)と実際の稼働(実績)との比較が不可欠です。
チェックポイント
- 工数の入力:勤怠システムや工数管理表を活用
- 実績の確認:計画との乖離や残業状況を把握
- 残業理由の確認:困っていることを具体的にヒアリング
- 業務の再配分:周囲との連携で負荷を調整
心理的に悪い状況を積極的に共有するのは気が引けるものです。
そのため、たとえ上司や先輩に、”大丈夫か?”問われたとしても、「まだ大丈夫です」と答えてしまう人が多いです。
状況は主観的な報告に頼らず、客観的なデータを把握することが必要不可欠です。
可能であれば毎日、少なくとも数日に一度は、チームメンバーの1日の総勤務時間を確認を基本としましょう。
まとめ
チーム運営において稼働・工数の「可視化と管理」は生産性向上の鍵です。
チーム全体のパフォーマンスを継続的に底上げすることができます。
関連資料
▶▶【📅ファイル】メンバー稼働管理表のダウンロード はこちら
▶▶【📅ファイル】工数推移(月・年単位)管理表のダウンロード はこちら
会員限定コンテンツで
仕事を進めやすくするヒントが見つかる!